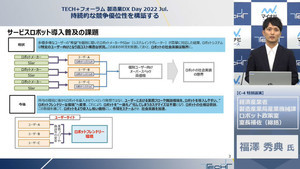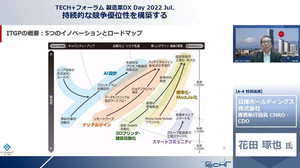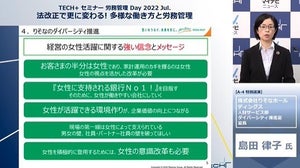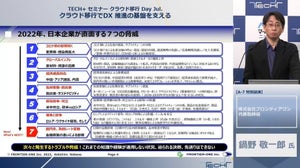カメラ向け部品、ビジネス向けのドキュメントスキャナー、ハンディターミナル/モバイル決済端末・モバイルプリンタ・歯科用加工機・医療機器などの開発・生産、各種ITソリューションの開発などを多岐に渡り手掛けているキヤノン電子。宇宙関連事業では、2020年10月に打ち上げた超小型人工衛星「CE-SAT-IIB(シーイー・サット・ツービー)」と、打上げから5年が経過した「CE-SAT-I(シーイー・サット・ワン)」の実証実験も順調に進められている。
8月25日、26日に開催された「ビジネス・フォーラム事務局×TECH+ EXPO 2022 for LEADERS DX Frontline 不確実性の時代に求められる視座」では、キヤノン電子 代表取締役会長の酒巻久氏が登壇。「何が変われば組織が変わるのか ~人と仕事を動かす経営~」と題し、同社が現在に至るまで実施してきた取り組みや、そのポイントなどを解説した。
“組み合わせの時代”を駆け抜けたキヤノン電子
講演の冒頭で酒巻氏は業界の現状について、「これまで日本の中では50~70年にわたり、ほとんど新しい技術は出ていない」と説明する。
「私が約50年前にアメリカを訪れた際、これからはソフト、つまり“組み合わせの時代”だと言われました。これは、優れたハードを組み合わせ技術によって応用する手法に変わっていくということです」(酒巻氏)
その時同氏は、今までの10年とこれからの10年では開発の時間軸が大きく変化すると悟ったそうだ。例えば、インクジェットの開発には約20年以上もの歳月を要した。複写機全体で考えれば、30年程度はかかったという。しかし現在では、組み合わせの技術を駆使することで、新しい製品の開発にそこまで長い開発期間を必要としない。スマートフォンなどは良い例で、3~5年のサイクルで進化を遂げている。
「私たちが入社したアナログの時代では、変化の期間が20~30年程度。当時は開発期間が長く、製造の難しさから熟練の技術が必要でした。その後に訪れたアナログとデジタルのハイブリッド時代には変化の期間が5~10年程度に短縮されました。そして現在、デジタルとネットワークによる組み合わせの時代においては、早いものならわずか数カ月から数年で開発が終わってしまうような状況です。経営者は、こうした時間軸の違いをもっと理解していく必要があります」(酒巻氏)
業界の企業規模も変化している。アナログの時代は、豊富な人材と熟練工、そして数多くの技術を持っている大きな企業が勝つ傾向が強かった。しかし、デジタルとネットワークの組み合わせの時代においては、小規模な企業が勝つことも多くなったという。
「スマートフォンで一世を風靡したAppleのiPhoneが良い例です。当時のAppleは通信技術的に見ると、中小企業の小に分類されていました。しかし実際には組み合わせの技術によって、Motorolaなどの大手企業が負けています。今後はそういう時代になる、と明示したような出来事でしたね」(酒巻氏)
初めての経営で、他人を真似ることを実践
1999年にキヤノン電子の代表取締役社長に就任した酒巻氏は、こうした時代背景において企業をどのように運営していくかを考えた。その当時、今から参加しても十分に勝機があるのではと考えたのが宇宙関係の事業だった。アナログの時代は海を制覇した国が世界を制覇し、その次には陸上。さらに空へと舞台が移り、次の分岐点では世界の注目が月へと注がれていたからだ。宇宙関連の事業を進めるには、当時の金額で最低でも数百億円の資金が必要とされた。しかし、当時の同社は累積負債や不良在庫、過剰設備などが300億円以上という状態。そこでまずは赤字を解消した上で、資金を貯めて宇宙関連事業に着手する計画を立てた。この計画は順調に進み、社内の改革(会社のアカスリ)を徹底した結果、わずか6年で売上高経営利益率10%超となった。
「私は長年にわたり技術系の業務に従事してきましたが、経営は初めての試みでした。そこでまずいと感じたのは、公の場で人と話す機会や経験が少なかったことです。技術系業務の場合、極端に言えば最低限の会話だけで仕事ができてしまいますが、経営者となると、そうもいきません」(酒巻氏)
そこで行ったのが、他人を真似ることだ。同氏は、新たな経験を得る上で真似ることはとても大事だと考えたという。しかし、自身と類似するような経歴を持っていない人の真似をしてもあまり意味がない可能性が高い。そこで、同じ理系で偉業を成し遂げた経営者の中から、かつて米国の銀行が次々と倒産の危機に陥った際に見事な手腕で立て直しを図った、元米シティバンク会長のジョン・リード氏に注目。彼が書いた論文を熟読したそうだ。
リード氏は、資産の縮小/人員の削減/不採算施設の閉鎖/不要な子会社の整理/採算の悪い海外からの撤退を実行しつつ、縮小均衡に陥るのを避けること、将来の利益を確保するために、自社の強みのコアビジネスを強化していくことが重要だと述べていた。また、当時の米国の銀行にはなかった、営業収支を重視するコンセプトを打ち出した。
前例や業態に捉われないリード氏の発想に感銘を受けた酒巻氏は、キヤノン電子でも同じような手法を採用。秀でた技術を“残さなければならないもの”とし、それ以外の事業については資産の縮小、開発費や営業経費の縮小、人員削減、施設の閉鎖、不要な子会社の整理などを行う決断をした。