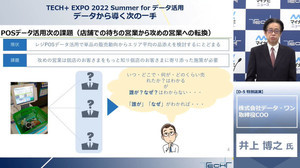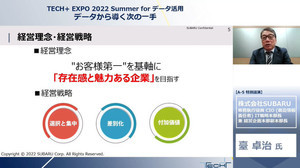2020年、新型コロナウイルス感染症の拡大により在宅勤務の普及が進んだ頃、とある話題が注目を集めた。それは、「捺印するために出社する」というものである。DXが推進され、あらゆる業務がデジタル化される中、契約書まわりの業務だけが取り残されていたことが浮き彫りになったのだ。
一方、2017年から電子サイン導入検討を進め、2019年には電子サインを導入、2021年3月には民間取引先との契約で100%電子化を達成したのがヤフーである※。ITリテラシーの高い人材が集まる大手IT企業とはいえ、多数の従業員と取引先を抱える同社が電子サインを導入するのは簡単ではなかったはずだ。
ヤフーはどのように課題を乗り越え、電子サインの導入を進めたのか。7月7日に開催された「TECH+セミナー バックオフィス業務のデジタル化 Day Jul.バックオフィスから次の一歩を」に、ヤフー オフィス・経営支援本部 業務運用支援部 部長の片岡徹氏が登壇。電子サイン化100%に至るまでの経緯について語った。
スロースタートで始まった電子サイン導入
ヤフーが電子サインの導入検討を始めたのは2017年のことだ。当時、経済産業省からは「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」の公表、そしてデジタル経営改革のための評価指標「DX推進指標」が提示されるなど、DX推進が声高に叫ばれ始めていた。
そうした中で、社内業務のDX化を先導していたのがヤフーだった。
「当社は2014年からリモート勤務制度『どこでもオフィス』を導入し、ノートPCやスマートフォンの配布、社内稟議・各種申請のオンライン化、ペーパーレス化の促進など、場所に捉われない、多様な働き方のためにデジタル化を進めてきました」(片岡氏)
一方で、そんなヤフーですら最後までデジタル化できていなかったのが、取引先との契約書だったという。
社内で完結する業務とは異なり、電子サイン化は取引先との調整も必要になるため、業務の煩雑化を招きかねないとして、反対の声も少なくなかった。実は、当時捺印を行う部門に所属していた片岡氏自身も「電子サイン化には消極的だった」と明かす。
そのような事情もあり、同社はまず電子サインの導入検討から慎重にスタート。社内各部門や取引先へのヒアリングを経て、2019年に電子サインの導入に至った。
「事前に調整していた企業との契約締結や内定通知書の電子サイン化といったところからスロースタートさせました。運用に関しても、導入を主導した法務部門が対応しており、手探りでの出発でした」(片岡氏)
状況が一変したのは、2020年に世界を襲った新型コロナウイルス感染症の拡大だ。緊急事態宣言が発令され、在宅勤務が普及。出社できないことから契約書の締結に遅れが発生し、「ハンコを押すための出社」を余儀なくされるなど、日本企業における契約書関連のデジタル化の遅れが世間でも話題となった。
「ビジネスへの影響を最小限に抑えるためにも、今こそ電子サインの活用を」――そんな機運がヤフー社内でも高まっていったのは自然な流れだろう。そして同社はついに「民間取引先との契約で100%電子サイン化」を目指す宣言を行う。その後、契約書関連のDXを積極的に進め、2021年3月には宣言通り100%を達成したのである。
3つの取り組みで電子サイン化を推進
ヤフーが電子サイン化を推進するために行った取り組みは、大きく3つある。
まず、会社規模での周知だ。執行役員 法務本部長や取締役 コーポレートグループ長など、役員が社内広報や全社集会で電子サインに関するメッセージを発信。さらに、社内掲示板でもアナウンスを行うなどして、ヤフーが電子サインを推進していくことへの意識を高めた。
次に業務運用支援部による個別対応だ。この段階で、電子サインの運用は導入を主導した法務部門から業務運用支援部に移っており、片岡氏も運用に携わっていた。
個別対応とは、例えば、紙での捺印申請を行った社員に対して、逐一電子サインへの切り替えを案内したり、紙で捺印した書類を送付する際に電子サインの案内チラシを同封したりするといった地道な活動だった。
こうした対応は着実な効果を挙げ、電子サインの普及を後押しするものになったという。
最後に対外的なメッセージの発信である。
ヤフーが100%電子サイン化に着手したという話題は大きな反響を呼び、メディアからの取材も殺到。同社の取り組みを対外的に発信することで、総合的に100%電子サイン化をさらに進める後押しになった。
こうしてヤフーは2021年3月、電子サイン化100%を達成するに至った。流れを聞く限りでは、何の問題もなく順調に進んだかに思える電子サイン化の取り組みだが、実際に導入を進める中ではさまざまな課題があったという。