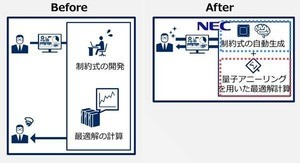新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、2018年2月27日に国立大学法人北海道大学と起業家支援の相互協力に関するとの覚書を締結したことを皮切りに、大学発ベンチャー育成に力を入れている有力大学と次々と同覚書を締結している。
2019年11月20日に国立大学法人金沢大学との覚書を締結した結果、現時点で合計13校の大学と締結済となった。これによって、日本での大学発ベンチャー企業の創業数を増やし、日本でのイノベーション創出数を高める環境づくりを一層進める構えだ。
NEDOと起業家支援に係る相互協力の覚書を提携した有力大学は、それぞれが独自のベンチャー企業創出エコシステムを構築しつつある。今回は、2019年2月20日にNEDOと同覚書を4校目として締結した東北大学側の契約担当者である矢島敬雅理事(産学連携)・連携機構長に、東北大のイノベーション創出を高める環境づくりについて聞いた。
--東北大が進めているイノベーション創出を高める環境づくりは?
矢島(以下、敬称略):東北大は現在の青葉山キャンパス(仙台市青葉区荒巻字青葉)の西側に「青葉山新キャンパス」の整備を進めています。ここを「グローバル・イノベーション・キャンパス」にするという、壮大な産学連携体制の構築を推進しています。
この産学連携体制強化の一環として、青葉山キャンパスの西端に位置する未来科学技術共同研究センター(NICHe)の建屋などに、本部機構の産学連携機構、関連会社のTLO(技術移転機構)である東北テクノアーチ(本社仙台市)を片平キャンパスから移転・集結させ、お互いが顔を合わせるアンダー・ワン・ルーフ体制を2018年度後半から築いています。
さらに、2015年(平成27年)2月23日に東北大が100%出資(6000万円)して設立したベンチャーキャピタルの東北大学ベンチャーパートナーズ(THVP、仙台市)も、このアンダー・ワン・ルーフ体制を支えています。
--グローバル・イノベーション・キャンパスとは?
矢島:東北大は「B-U-B(Business-University-Business)」という大学を中心として異分野の企業群が組織的に連携する新しい産学連携モデルの実現を図っています。このB-U-Bは、東北大を仲立ちとして企業間組織連携を目指すものです。このB-U-Bを国際的に実践する場として、青葉山新キャンパスを活用します。
このB-U-B連携構想の基になった先進事例が、東北大ではすでに稼動しています。2012年10月に設けた国際集積エレクトロニクス研究開発センター(CIES)です。工学研究科の遠藤哲朗 教授の研究開発成果と指導力を基に、集積化マイクロシステムという高度な半導体開発などとのさまざまな融合を目指す国際的な産学連携拠点です。
このCIESでは、2016年ごろから企業などから提供いただく外部資金を1年間に15億円程度集めて、自立運営を実践しています。米国の有力な半導体関連企業とも連携するなどの国際的な産学連携も確立し、国内・海外の集積エレクトロニクス産業の共同開発拠点になっています。このCIESが、今回のB-U-B連携体制を考える先進事例になりました。
その後、東北大はスピントロニクス分野を重点分野の1つとして、強力な研究開発体制を築いています。このスピントロニクス分野での産学連携の中核拠点としてもCIESは発展中です。スピントロニクス分野の研究開発分野では、理学研究科の平山祥郎 教授を中心に世界トップレベルの研究を推進しています。
このスピントロニクス分野でのB-U-B連携体制構築は産学連携での第一の矢です。
--B-U-B連携体制構築の第ニの矢は?
矢島:第二の矢はライフサイエンス分野です。2018年12月にオープンイノベーション戦略機構を設けて、連携活動を始めました。
このオープンイノベーション戦略機構は、総長直下の組織として設け、その機構長には東北大の青木孝文 理事・副学長(企画戦略総括、プロボスト)が就任し、予算から執行・資産管理、人事、共同研究契約などの管理権限を与えています。これによって、機構長は強力な権限を基に、組織的な産学連携を推進していきます。
青木機構長の下には、統括クリエイティブ・マネージャーを置いて、自立的・一体的な意思決定によって、先進的な推進体制を築いています。この統括クリエイティブ・マネージャーの下には、さらに知的財産・法務や財務、インキュベーションなどに詳しいクリエイティブ・マネージャーを配置しています(2019年12月時点で現在進行中)。さらに、第二の矢向けに、製薬分野に詳しいクリエイティブ・マネージャーを配置していきます。
このオープンイノベーション戦略機構は、2018年12月から活動を始め、薬学研究科や医工学研究科、工学研究科などにサテライト研究室を設けるなどや、製薬企業などとの共同研究を誘致などの活動を始めています。
日本のライフサイエンス分野では、企業などとの共同研究費が年率20数%と急成長している分野です。医薬品や医療機器などの共同開発プロジェクトを実践していきます。このライフサイエンス分野では、東北大は東北メディカルメガバンク機構や大学病院臨床研究推進センター(CRIETO)などがすでに活動させていて、大きな実績を築いています。
さらに、このオープンイノベーション戦略機構では、第三の矢としてマテリアル分野も推進していきます。東北大はマテリアル分野では、すでにJX金属との組織連携として、革新材料創成センターを設ける計画を推進中です。このJX金属との組織連携などを基に、次世代半導体配線材料の開発を目指したB-U-B連携を図っていきます。マテリアル分野は、東北大が元々、強みを持つ分野なので、B-U-B連携のモデルケースを示したいと考えています。
こうしたB-U-B連携を強力に推進し、2030年度には東北大は産学連携による収入を165億円と、現在の約5倍に増やしたいと計画中です。