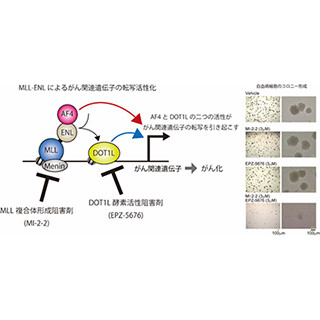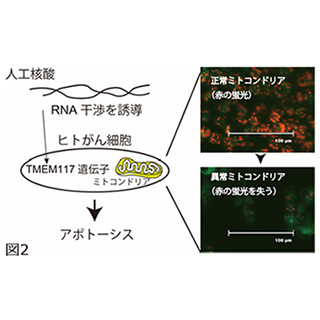科学技術振興機構(JST)と東京医科歯科大学は、JST戦略的創造研究推進事業において、同大学脳統合機能研究センター 味岡逸樹准教授らの研究グループが、脳梗塞領域に血管を誘引するスポンジ形状の人工細胞足場を開発したことを発表した。この研究成果は5月10日、ドイツ科学誌「Advanced Healthcare Materials」オンライン速報版に掲載された。
脳は一度損傷を受けると再生しない組織だと考えられていた。例えば脳の病気のひとつである脳梗塞は、脳の血管が詰まり、酸素や血液の供給が遮断され、脳のニューロンが壊れる疾患で、運動障害や言語障害などを引き起こすし、自然治癒力ではほとんど回復しない。しかし、哺乳類の脳にも潜在的な再生能力が秘められていることが、近年の研究で明らかになってきたという。
これら失われた機能を回復させる治療である脳梗塞の再生治療には、ニューロンの死を最小限に抑え、損傷した脳を修復し、再生させるために新たな血管を誘引する必要があるが、脳梗塞部位で局所的に新たな血管を誘引する方法はなく、それを可能にする技術開発が望まれていた。
今回、研究グループは、血管内皮細胞の足場として機能するラミニンたんぱく質を利用して、血管を誘引する機能を持つたんぱく質(血管内皮細胞増殖因子、VEGF)を結合させたスポンジ形状の人工細胞足場(VEGF結合ラミニンスポンジ)を開発した。さらに、この人工足場をマウス脳梗塞モデルの脳梗塞領域に移植し、VEGF結合ラミニンスポンジが脳梗塞領域に血管が誘引されることを明らかにした。
また、マウス脳梗塞モデルによる実験では、脳梗塞処理3日後に、脳梗塞領域へVEGF結合ラミニンスポンジを移植し、7日後に血管誘引能を評価したという。VEGFを結合していないラミニンスポンジ(コントロール)を移植した場合、新生血管がほとんど検出されなかったのに対し、VEGF結合スポンジを移植した場合は脳梗塞領域で顕著な新生血管が認められたということだ。
この成果は、損傷した脳を修復・再生させるためのステップであり、今後は開頭手術を必要としない非侵襲的な人工細胞足場の開発や、再生しないと考えられている損傷脳を修復し再生させる再生医療への展開が期待されると説明している。