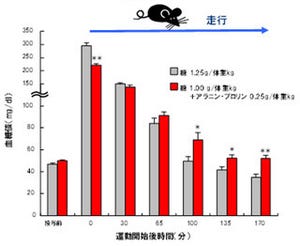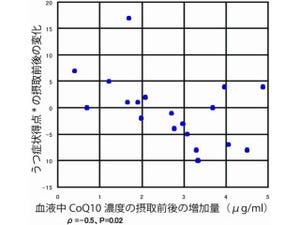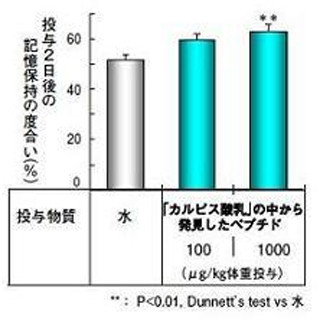理化学研究所(理研)、関西福祉科学大学、浜松ホトニクス、浜松医科大学の4者は12月12日、「慢性疲労症候群」患者の約半数の血中に見られる自己免疫疾患の原因となる「自己抗体」が、脳の神経伝達機能を低下させている様子をPET(陽電子放射断層撮影)検査で明らかにしたと発表した。
成果は、理研 分子イメージング科学研究センター 分子プローブ動態応用研究チームの渡辺恭良チームリーダー、同・水野敬研究員らと、関西福祉科学大 健康福祉学部の倉恒弘彦教授、浜松ホトニクス 中央研究所 PET応用PETセンターの塚田秀夫センター長、同・山本茂幸氏、浜松医科大 分子イメージング先端研究センターの尾内康臣教授らの共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間12月12日付けで米オンライン科学誌「PLoS ONE」に掲載された。
日本では、疲労感を自覚している人の割合は約6割に上り、その内約4割の人が、6カ月以上も疲れを感じたままの慢性疲労状態にあると報告されている(2004年文部科学省科学振興調整費「疲労および疲労感の分子・神経メカニズムとその防御 に関する研究」調査)。
このように長期にわたって強い疲労感が続き、健全な社会生活が送れなくなる病気を慢性疲労症候群と呼ぶが、日本のほか、欧米を中心に世界各国で報告されている。
1980年代にはレトロウイルス感染症が疑われたが、明確な原因はわかっていない。現在では、感染症を含めたウイルスや細菌感染、過度のストレスなど複合的な要因が引き金になり、神経・内分泌・免疫系の変調が生じて、脳・神経系が機能障害を引き起こすためと考えられている。しかし、その発症メカニズムは明らかになっておらず、正確な診断法や予防・治療法の確立が急がれている状況だ。
これまでの疫学調査から、慢性疲労症候群の患者の血中には、通常の血液検査では見つからない特殊なタンパク質が検出されることがわかっている。その1つが、自己免疫疾患の原因となる自己抗体だ。
これまでに、「ムスカリン性アセチルコリン受容体(mAChR)」に対する自己抗体が、慢性疲労症候群患者の約半数で見つかったという報告がなされていた。mAChRは、神経伝達物質「アセチルコリン」の受容体の1種で、大脳皮質や脳幹部、心臓などで働き、アルツハイマー型認知症やハンチントン舞踏病、パーキンソン病、統合失調症などに関わるとされている。
そのため、mAChR自己抗体がmAChRに結合して、慢性疲労症候群患者の脳の機能に影響を及ぼすと推測されていた。しかし、一般に血中の抗体は、「血液脳関門」の制限により脳神経細胞には移行しないため、脳への影響は未解明のままだったのである。
そこで研究グループは、mAChR自己抗体の脳への影響を知るために、慢性疲労症候群患者の脳でのmAChR発現量をPET検査での調査を実施した。PET検査に先立ち、200名の慢性疲労症候群患者に対して、mAChR自己抗体の陽性判定を先行報告よりも厳しい基準で行ったところ、検査できた200名の慢性疲労症候群患者の内8名が確実にmAChR自己抗体を持つことが判明し、その内の5名の協力が得られ、実験が進められたのである。
mAChRには、構造が似たM1~M5型という5つの型があるが、協力を得た5名が持つ自己抗体はM1型に対する抗体であることが判明。PET検査で用いたプローブ「11C3-MPB」は、神経細胞に存在するすべての型のmAChR分子と1対1で結合するため、脳内のmAChRの局在を定量的に調べられるという特徴を持つ。
PET検査は、mAChR自己抗体を持つ慢性疲労症候群患者5名、持たない患者6名、健常者11名の計22名に対して行われた(画像1)。その結果、mAChR自己抗体のある患者の脳のmAChR発現量は、ほかと比べて10~25%低下していることがわかったのである(画像2)。これは、血中のmAChR自己抗体が血液脳関門を突破して、脳神経細胞のmAChRに結合していることを示唆する。
画像1は、mAChRに対する自己抗体の陽性判定。健常者(NC)11名および慢性疲労症候群患者(CFS)11名の血中に存在する抗体成分の、mAChRに反応する強さ(Anyibody index:抗体指数)を測定した結果。今回の研究では、抗体指数が0.5以上の患者を自己抗体陽性(CFS(+))と判定している。
画像2は、慢性疲労症候群患者の自己抗体が脳の神経伝達に与える影響。mAChRを標的とするPETプローブ11C3-MPBを用いてPET検査した脳の断層図(左列は、大脳基底核と大脳皮質を主に含む断層、右列は大脳皮質を主に含む断層。いずれの写真も上方向が鼻側)。mAChR自己抗体を持たない慢性疲労症候群患者(中)は、健常者(上)と同様のmAChR発現量(黄色~赤色)を示すが、mAChR自己抗体を持つ慢性疲労症候群患者(下)は、mAChR発現量の低下を示している。
M1型を発現する神経細胞は、認知機能に強く関わる。そこで、22名のすべての被験者に対して、熟語の音読課題や記憶力などの認知機能を神経心理学的テストで比較したが、有意な点数の差は確認できなかった。これは、認知機能の低下には至らないmAChR発現量の微妙な変化を、PET検査が検出できたことを示す。
今回の結果は、血中の認知機能に関わる自己抗体が、脳の特定の神経伝達機能に直接影響を及ぼす可能性を示した形だ。通常は、体内分子に対する自己抗体が作られることはなく、血中の抗体が脳内に移行することもない。
しかし、ウイルスや細菌が感染すると、免疫系が破たんして自己抗体が出現したり、炎症反応で血液脳関門が機能しなくなったりすることがある。すべての慢性疲労症候群患者で自己抗体を検出するわけではないが、感染症と免疫系、疲労の関係解明につながると期待できるという。
また、自己免疫疾患の患者はしばしば頭痛やだるさ、疲労感などを訴える。これら原因不明の体の不調と自己抗体の正確な因果関係は不明だが、今回の手法を応用し、自己抗体の影響を受ける分子や神経機能をPET検査で調べることで、自己免疫疾患の発症メカニズムの理解が進むことが期待できるとしている。