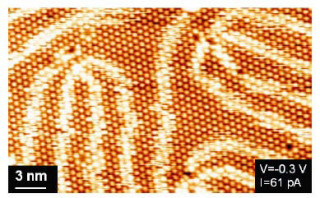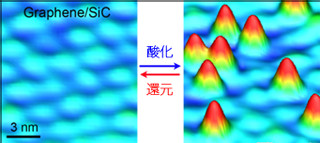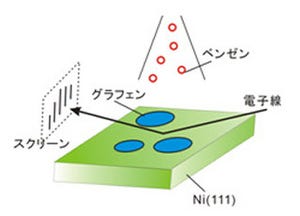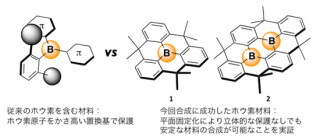科学技術振興機構(JST)、筑波大学、東京大学の3者は6月6日、東京理科大学も加えた共同研究により、ダイヤモンドと、同じく炭素原子が1層からなる2次元シート状物質グラフェン(2次元グラファイトシート)の複合構造が、優れた電気伝導特性と共に、高い放熱特性を示すことをシミュレーション解析により発見したと発表した。
成果は、筑波大の岡田晋准教授、東大 大学院工学系研究科 機械工学専攻の丸山茂夫教授、同塩見淳一郎教授、東京理科大学の山本貴博講師らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、6月4日付けで米物理学会誌「Applied Physics Letters」オンライン版に掲載。
これまで半導体デバイスでは、プロセスの微細化により高集積化、高速化、低消費電力化などの複数の性能を同時に向上させてきた。しかし、プロセスの微細化に伴った配線の電力ロスの増大や製造コストの高騰といった技術的、経済的な課題が大きくなってきており、かつ20nmを下回る超微細プロセスが実用化されるようになり、物理的な限界も見えるようになってきた。そのため、近年、こうした課題解決のためにSiに代わる新規材料やプロセス、デバイス構造の研究開発が各所で進められている。
中でも注目されているのが、カーボンナノチューブ(CNT)やグラフェンなどの炭素系材料である。炭素系材料は、低次元性・ナノオーダーの微細性・優れた電子輸送特性を有しており、Siに代わる新規材料としてだけでなく、Cu配線の代替材料としても期待されている。
また、炭素系素材はダイヤモンドに見られるような非常に強固な原子間結合を持ち、高い熱伝導性を示すことも特長の1つでダイヤモンド半導体は究極の半導体とも呼ばれている。そのため、もし複数の炭素系素材を組み合わせたハイブリッド構造を作ることができれば、高い電子伝導性と熱伝導性を兼ね備えた理想的なオールカーボン配線が実現可能だと考えられているのである。
今回の研究では、グラファイトでできた細線「グラフェンナノリボン」を、両端からダイヤモンドで挟み込んだ複合計(画像1)について、その構造安定性と電子状態について第一原理電子状態計算法を用いた詳細な調査が行われた。なお、グラフェンナノリボンとダイヤモンドの結合は、炭素原子間の共有結合でなされている。
画像1は、第一原理電子状態計算により得られた、グラフェン-ダイヤモンド複合構造のエネルギー安定状態。灰色の部分がダイヤモンド構造で、その間にグラフェン構造が挟まれている。
シミュレーションの結果、グラフェン-ダイヤモンド複合構造はエネルギー的に安定で、伝導電子のスピンが1方向にそろった強磁性金属状態であることが判明した(画像2)。
画像2は、グラフェン-ダイヤモンド複合構造の電子状態を表すバンドダイアグラム。エネルギーはフェルミ準位が基準だ。また、青線、赤線はそれぞれ異なる電子スピン状態を表し、伝導電子がスピン分極していることがわかる。
グラフェンとダイヤモンドの境界近くを流れているスピン分極した(スピンがそろっている)電子を使えば、グラフェンナノリボンは単に電荷を運ぶ配線としてだけでなく、スピンも活用できる配線材料として応用可能と考えられるという。
すでにダイヤモンドに挟まれていないグラフェンナノリボンが、電気伝導特性の優れた金属状態を示すことは知られていたが、ダイヤモンドに挟まれたグラフェンナノリボンも同様に電気伝導性の非常に優れた金属状態を示すことが、今回の研究により明らかにされた。
グラフェンナノリボンの電子状態がダイヤモンドの有無にかかわらず保持されるのは、ダイヤモンドとの界面においてグラフェン領域の「π電子」が完全に終端されるためであると考えられると研究チームでは説明している。
さらに、この複合系の熱伝導特性を「非平衡分子動力学法」を用いての調査した結果、グラフェン領域からダイヤモンド領域への界面熱コンダクタンスは7.01±0.05GWm-2K-1と計算された(画像3)。
画像3は、非平衡分子動力学法により計算された、グラフェン-ダイヤモンド間の界面熱コンダクタンスの温度依存性のグラフ。200Kの低温領域から400Kの高温領域の幅広い温度領域に渡って、7GWm-2K-1程度の高い界面熱コンダクタンスを示している。
このグラフェン-ダイヤモンド間の界面熱コンダクタンスは、高い熱伝導性で知られるCNT-シリコン間の界面熱コンダクタンスよりも2桁高く、グラフェンで発生した熱が、速やかにダイヤモンド領域へ拡散することを示している。
これらの結果から、今回の研究で提案されたグラフェン-ダイヤモンド複合構造が、高い電子伝導性と発熱を回避できる高い熱伝導性とを同時に利用できる、優れた配線構造であることがわかったというわけだ。
なお研究チームでは、今後、より大規模なグラフェン-ダイヤモンド複合構造に対して電子輸送シミュレーションを行い、配線材料としての具体的な特性を明らかにし、炭素系材料を用いた次世代デバイスの新たな設計指針を示したいとコメントしている。