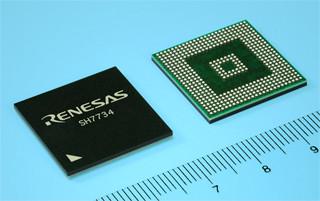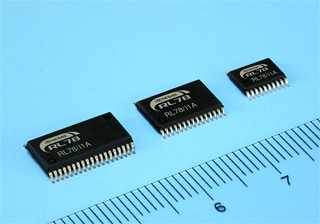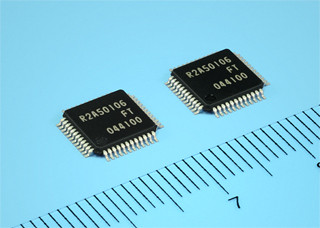ルネサス エレクトロニクスは、微弱な電力でセンサからの情報を携帯端末にデータ送信できる新しい近距離無線技術を開発したことを発表した。通常のBluetoothや無線LANを用いたデータ送信では、超小型端末(センサノード)の送信部で十数mWの電力を消費するが、今回開発した近距離無線技術の消費電力は数μWで済むため、環境電波から回収した微弱な電力での送信が可能となり、センサノードの電池レス化を実現できる。これにより、小型・軽量かつメンテナンスフリーの特性を活かし、センサノードの用途を拡大できる。
今回開発した技術は、数μWの低消費電力で通信可能な、(1)近距離無線技術と数μWの電力を確保する、(2)エネルギーハーベスト技術の2つ。技術の詳細は、2011年6月15~17日に京都で開催される半導体回路技術に関する国際会議「VLSI回路シンポジウム(2011 Symposium on VLSI Circuits)」の6月16日のセッションにおいて発表される。
数μWで通信可能な近距離無線技術
開発した近距離無線技術は、人を中心に約1mの距離を対象とし、通信状態の良し悪しを情報としてデータ送信を行うことで低消費電力での通信を実現する。
Bluetoothや無線LANの受信波形は、良好な通信状態の波形と悪い通信状態の波形に分かれる。悪い通信状態の時はデータ信号に多くのノイズが乗り、データ信号の振幅も小さい。同社では、良好な通信状態と悪い通信状態の違いそのものも情報であることに着目。また、無線通信の特徴として、反射によって通信状態が悪くなることに注目した。反射がない場合はアクセスポイントから携帯端末にダイレクトにデータが到達し、良好な通信状態で"1"と"0"の情報が分かりやすい。一方、壁や人などで電波が反射する場合、ダイレクトパスと反射パスが混在し積算されて受信するため、"1"と"0"の情報が分かりにくい悪い通信状態になる。この通信状態の良し悪しを使って、センサノードから携帯端末に情報を送信する。
開発したセンサノードは、アクセスポイントから携帯端末に向かう無線電波を反射・吸収することで"1"と"0"の情報を表現する。反射させると通信状態が悪くなるため"1"を表し、吸収すると通信状態が良くなるため"0"を表す。"1"と"0"の表現を反射・吸収だけで行うため、従来比3桁減の数μWの超低消費電力で通信が可能となる。
性能評価チップとアンテナを搭載した評価ボード試作し、数μWの電力での送受信を実証したところ、通信距離30cmにおいてデータレート5.5kbpsで情報伝達が可能なことを確認したという。なお、評価ボードのアンテナは直径15mmの配線をプリント基板上に形成した。チップ製造に特殊なプロセスは不要で、220μm×200μmのサイズの評価チップを90nm 標準CMOSプロセスにより製造した。
エネルギーハーベスト技術により数μWの電力の確保
エネルギーハーベストは、身の回りにある熱、振動、電波などのエネルギーを電気エネルギーに変換する環境型発電技術で、今回の開発技術は環境電波を回収し電気エネルギーとして利用する。
環境電波は、携帯電話の基地局や携帯電話、無線LAN、地上デジタル放送局が発している電波など多岐にわたるが、場所によって電波の種類や強度が異なる上、秒単位で電波の強度が変動する。エネルギーハーベストに共通する課題として、時間と場所によって得られるエネルギーが変動する問題がある。
この課題を克服するため、環境電波を自動追尾する技術を開発した。環境電波を検知する際に、環境電波エネルギーの高い領域に自動でアンテナの感度を移動させて回収する。従来の環境電波の回収はそれぞれの周波数に特化して回収していたが、自動追尾によりそれぞれの周波数で10μW程度の電力を安定的に回収できる。これによりセンサノードのデータ送信が可能になる。
次世代の情報・通信イノベーションの実現を目指す
今回開発した技術により、Bluetoothや無線LANを用いたスマートフォンやタブレットPCなどの携帯端末に対して1mの近距離にある電池レスのセンサノードから情報を伝達することが可能となる。Bluetoothや無線LANの通信が行われている環境で使用できるため、システム構築の障壁が低く導入が容易である。また、センサノードは電池レスのため、さまざまな応用が期待できる。
応用例としては、乳幼児の発熱を絆創膏に貼ったセンサから携帯端末に送信し、離れた場所にいる親に状況を伝えることができる。また、街頭のポスターの傍を通る通行人に必要な情報を送信するアプリケーションも考えられる。特にセンサノードはさまざまな分野で研究開発が進んでおり、開発技術はその応用展開に貢献する。そして携帯端末の活用や医療ヘルスケアでの情報管理など、近距離無線通信における様々なサービスを拡大する。
同社では今回の技術を、あらゆるモノが人をサポートする情報を発信する次世代の情報・通信イノベーションの実現や、あらゆる分野にセンサネットワークを張り巡らせて情報を管理するスマートシティの実現に必要な基盤技術と位置付けており、今後も研究開発を進めていく方針。2~3年後の製品化を目指している。