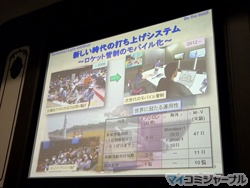次世代を担うイプシロンロケット
先輩2人に続いて登壇したのは、現役バリバリの森田氏である。JAXAはM-Vロケットの後継として、次期固体ロケット(通称イプシロン)の開発を進めているが、森田氏はこのプロジェクトマネージャを務めている。
次期固体ロケットは、M-Vロケットの上段とH-IIAロケットの固体ロケットブースタ(SRB-A)を組み合わせたものになる。大きくてコストが高い1段目には、量産されて安いSRB-Aを使い、打上げ能力に大きな影響が出る上段には、性能が良いM-Vをベースに改良する。これによって、ロケットの打上げ能力はM-Vの2/3になるが、コストを1/3まで削減することで、コストパフォーマンスの向上を目指す。
"イプシロン(E)"という名称については、筆者は以前、「Exploration」「Excellence」などの意味が込められていると聞いた覚えがあるが、森田氏は「内之浦から打上がり、記者会見したときに報告したい」として、命名の由来については明かさなかった。また打上げ時期について、以前は2012年度とされていたが、今回のスライドでは2013年度となっており、予算の遅れから1年延びたようだ。
M-Vロケットは、ペンシル以来の日本の固体燃料ロケットの集大成と言うべきもので、確かに性能はすばらしかったが(惑星探査にも利用できる世界唯一の固体ロケットである)、高いコストが問題となり、2006年9月の7号機を最後に廃止されてしまった。今年打上げ予定の金星探査機「あかつき」は本来、このM-Vを使う予定だったのだが、廃止によって、H-IIAロケットに乗り換えることになった。
M-Vロケットは高性能な反面、コストも高かったために、結果として10年間で7機しか打上げられなかった(うち成功は6機)。次期固体ロケットには、この反省がある。もっと小回りを良くして、高頻度に成果を得られるようにする。
そのために、機体の低コスト化を図ったわけだが、さらに画期的なのは、打上げシステム全体の革新を狙ったことだ。
その1つは運用性の改善である。本来、固体ロケットは即応性に優れるはずなのだが、M-Vは複雑だったために、射場での準備に47日間もの日数を要していた。次期固体ロケットでは、機体の自律化を図る。搭載機器をネットワークで繋ぎ、ロケット自身に機体のチェック機能を持たせることで、準備期間を6日まで削減する。これにあわせて、運用経費も10億円から1億円に削減できる。
ロケットの点検で手間がかかるものに、例えばバルブがある。液体燃料のロケットではエンジンにバルブがあり、固体燃料のロケットにはノズルを動かす装置にバルブがある。この正常か異常かの判定に、実際にバルブを動かしたときの電流波形を見ているのだが、「同じように波形を見ている心電図では、健康かどうかを機器が自動で判断している。医療分野で普及しているこういった機能を、ロケットの世界でもそろそろやろう、ということ」(森田氏)
もう1つは地上設備のコンパクト化である。これまでの管制はアポロ以来の「お祭り騒ぎ」(森田氏)だったが、上記のような自律化によって数人に集約、ネットワークを利用すれば射場にいる必要もなく、ノートPC数台の「モバイル管制」が可能となる。将来的に、飛行時の異常チェックも自律化できれば、ロケットを追跡する高価なレーダーも不要になり、さらにコンパクトにできる可能性もあるそうだ。