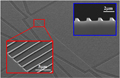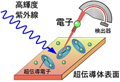東北大学大学院工学研究科の安藤康夫教授のグループは、強磁性トンネル接合(MTJ:Magnetic Tunnel Junction)として、従来構造と比べ信号出力を7割程度向上させる基本構造を突き止めたことを明らかにした。
従来のMTJの構造は、磁石の性質を持つ薄膜(強磁性膜)2枚で原子数個のオーダーの絶縁膜を挟んだ構造を採用していた。しかし、この構成による信号出力の向上は実験的にも理論的にも限界に近づいており、同グループではMTJの基本構造を強磁性膜3枚と絶縁膜2枚に変更、二重トンネル障壁構造としたことで、性能向上を実現したという。

|
|
図aはこれまでの強磁性トンネル接合(MTJ)の基本構造。強磁性薄膜2枚で薄い絶縁体薄膜をサンドウィッチした構造(強磁性膜における磁石の向きで0か1かを判断する)。図bは、今回開発された二重トンネル障壁の強磁性トンネル接合の基本構造。中間の強磁性薄膜(強磁性膜2)の磁石の向きを外部からの磁場で動かすことで、相対的な磁石の方向が平行と反平行をつくることが可能になる |
具体的には、従来の素子構造であるCoFeB/MgO/CoFeBのサンドウィッチ構造から、素子の構造をCoFeB/MgO/CoFeB/MgO/CoFeBのように、強磁性膜を3枚、絶縁膜2枚設けた二重トンネル障壁構造を持つMTJとした。特に、強磁性膜2(CoFeB部分)の膜厚を1.2nmと原子数個分のオーダとしたことで、磁気抵抗変化率は室温で1056%を達成した。
また、トンネル素子の抵抗値は絶縁層の厚さにより大きく変化するため、通常は絶縁膜を厚くすると抵抗値は極端に大きくなってしまう。そのため、絶縁層を2枚にした二重トンネル障壁MTJでは、抵抗が直列配列になることから素子の全抵抗値は大きく上昇してしまい、実用的ではなくなるという考えが常識的であった。しかし今回開発された素子は、中間の強磁性電極を最適な厚さとすることで、同じ絶縁層の膜厚を持つ基本構造のMTJ素子と比べ低い抵抗値を達成しており、これまでの常識が完全に覆される結果を示すこととなり、何らかの新しい物理的効果が存在していることが示唆させる結果となっている。
さらに、今回開発した技術を用いると、MgOの熱処理温度を350℃程度に抑えても高い磁気抵抗変化率を実現することが可能である。その結果、これまで開発してきた実績を持つ層構成をそのまま利用し、MTJ部分のみを新たな素子に置き換えることで性能向上を図ることが可能となる。
このほか、磁界を正→負とスイープさせたときと、負→正とスイープさせたときの磁化のジャンプする位置(磁界)の差が小さいことから、少ないエネルギー消費で大きな出力変化を得ることができる。そのため、抵抗値の"ハイ"と"ロー"を情報の"1"と"0"に対応させることで、不揮発性の磁気メモリとして用いることができるほか、外部磁界に対する抵抗値の変化そのものを出力とすることで高感度磁気センサとしての活用も可能となる。
また、中間電極が外部の電極から電気的に浮いている構造となっているため、同素子の外部にゲート電極を設けることで三端子素子への応用が可能となる。外部電界により素子の抵抗を制御することができれるようになれば、トランジスタ動作も期待できるとしており、素子単体で不揮発性記憶機能と演算機能の両特性を実現することが可能になるとしている。

|
|
今回開発した二重トンネル障壁MTJ における磁気抵抗変化率の印加磁界依存性(磁気抵抗曲線)(3つの強磁性層の磁石の相対的な方向に依存して抵抗値が大きく変化する。ここでは中間の強磁性層の磁石の方向の変化により、急峻な出力信号の変化を得ている) |
そのため、将来的に、同素子をスピントランジスタとして活用することで、電子機器の省電力化ならびにCO2排出量削減への寄与が期待されるとしている。