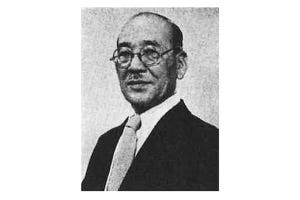フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
この文字では使えない
海軍水路部での写真植字機導入が順調に進み、2台目の機械の注文が入って安堵したのと入れ替わるように、1929年 (昭和4) 秋から1930年 (昭和5) 春までかけて写真植字機が納入された共同印刷、秀英舎、凸版印刷、日清印刷、精版印刷の5大印刷会社から、機械を実際に扱ってみたうえで「邦文写真植字機はまだ実用には不十分である」という厳しい指摘が入った。ようやく実用機が世に出たとおもっていたのに「まだ使えない」と言われてしまったのである。
-

1930年 (昭和5) 12月刊行の書籍に掲載された邦文写真植字機。印刷は、実用第1号機を導入した共同印刷。1932年 (昭和7) に完成したといわれるゴシック体、楷書体が使われている (印字見本用に途中段階の文字盤を製作したのだろうか?) (三谷幸吉『誰にも判かる印刷物誂方の秘訣』印刷改造社、1930.12、ノンブルなし。p.72とp.73のあいだ、5枚目の綴じ込み) 資料協力:今市達也氏
その理由は、つぎのようなものだった。
一、文字の字体が活字明朝と違っており、かつ字体そのものが洗練されていないから、印刷した時に力が足りない。また、文字の太さにムラがある。――これは字母の不完全さによるものであった。
一、印字したものを見ると、一行の中に文字が左右にハミ出しているものが目立つ。――文字盤に配置した文字の位置が正確でないためと、文字盤を固定するラックのピッチが正確でないためであった。
一、ふり仮名印字ができない。――普通の仮名をレンズによって縮小して、ルビの位置だけ右へ送りを与えて印字すればできることであったが、このような面倒なことは実用上不可能に近かった。
[注1]
また、大阪の精版印刷でこの邦文写植機を実際に扱った中田祐夫 (後の中田印刷社長、日本印刷学会長) が後年述懐したところによると、「レンズによる文字の大小の変化が10種類では不足」と感じたという。
〈その時の機械は一枚文字盤方式で、取りはずしに大変不便であった。レンズは六本しかなく、その上機械の安定性も悪く、シャッターが動かないこともしばしばで、動いても露出時間にムラがあり、何回も分解して調べたことがあった。また、電圧調整ができなかったから、傍にあった製版カメラに影響されて、ひどい濃淡のムラが出てしまい、二カ月くらいいろいろいじくってみたが、とうとう使いものにならず、親爺 (当時の精版印刷の社長) も大変なものを買い込んだものだと思った〉[注2]
中田の述懐のように機械工作上の不備への指摘もあったが、5社から「実用に不十分」といわれた大きな理由は、第一に文字 (文字盤) の欠点、第二にルビ印字不能だった。ルビについてはまったくの手抜かりだった。当時、ほとんどの新聞雑誌にはルビがふられていたのだが、茂吉自身がその重要さを察知できず、軽くかんがえすぎていたのだ。
こうした不備と欠陥から、5大印刷会社は各社とも邦文写真植字機の使用を中止した。5台の機械は結局1933年 (昭和8) ごろまで、各工場の隅に埋もれたままになってしまったのだった。[注3]
最初の文字盤「試作第1号機文字盤」
ふりかえると、茂吉はじつのところ、1925年 (大正14) 秋に試作第1号機を完成して以降、自分たちが用意した文字盤、そして文字に問題意識をもち続けていた。文字盤は、茂吉がずっと担当してきた。はじめて文字盤をつくったのは、1925年 (大正14) 秋に発表した試作第1号機のときだった。本稿では「試作第1号機文字盤」と呼ぼう。
本連載第29回、第30回でもふれたように、最初の「試作第1号機文字盤」は、秀英舎を中心とした活字の清刷りから約3,000字を湿板写真で1枚のガラス板にとったものだった。いわば、清刷りをそのまま複写したものである。[注4]
茂吉は邦文写真植字機開発に関わるまで、印刷や活字書体についての経験がまったくなかった。文字盤をつくるにあたっても、すでに活字書体というものが世にあるのだから、そんなにむずかしいことではないだろうとおもっていた。
ところが、いざ活字の清刷りから文字盤をつくってみると、とても使えたものではなかった。機械の精度からくる字並びの悪さもあったが、「試作第1号機文字盤」はなにより、文字の形そのものが崩れたり、つぶれたりしてしまっていた。活字の清刷りをそのまま撮影して文字盤をつくっていたからである。
このころの活版印刷にもちいられた活字は、種字彫刻師が手彫りする「種字」をおおもとの型として母型 (鋳造するときの文字の型) をつくる「電胎母型の時代」だった。使用する活字と同じ大きさ (原寸) 、鏡文字の状態で、ひとが手で彫った種字を型にしていたのだ。 使用するすべての文字、すべての大きさの種字が必要だった。
つまり当時の活字は、「あくまでもそのサイズで印刷する文字」として、原寸使用を前提に形がつくられたものだった。いっぽうの写真植字は、文字盤の文字をレンズで拡大縮小することにより、印字の大きさを変化させることができた。文字盤の文字より縮小するだけならともかく、拡大したときにもきれいな文字を得るには、「原寸使用を前提に製作された活字」をもとにしていてはむずかしい。しかも、複製元の原稿は「清刷り」、つまり印刷物である。
活版印刷は、凸状となった文字部分にインキをつけ、紙に押し当てて印刷する。ハンコに朱肉をたっぷりとつけて捺したときを想像してほしいのだが、紙に活字を押しつけたときに、程度の差こそあれ、かならずインキがはみだし、文字の輪郭が太る (このはみだしたインキにじみの部分を「マージナルゾーン」という)。印刷の時点で、文字の輪郭がにじんでしまうのだ。
そうした理屈は置いておいても、試作第1号機による印字物を見れば、文字盤の品質が低く、そのまま実用されることはありえないことは、印刷素人の茂吉にも一目瞭然だった。
「文字と文字盤をなんとかしなくてはならない」
茂吉もそうおもってはいたが、実用化に向けての優先順位としてはレンズのほうが上だった。とにかくレンズの計算を終えないことには、邦文写真植字機自体の完成がありえなかった。
茂吉がレンズの計算を終えたのは、1928年 (昭和3) はじめのことだ。文字と文字盤の研究に取り組み始めたのは、おそらくそれ以降のことだったのではないだろうか。[注5]
〈どうしても、そのための文字が必要になった。茂吉はこれにも手をつけた。どこにもそんな文字はなかったし、やってくれるところがなかったからである〉[注6]
(つづく)
[注1] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.112
[注2] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 pp.112-113
[注3] 『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 pp.112-113、「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 pp.24-25
[注4]『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.88、p.103
[注5] 写研の資料類を見ると、茂吉のレンズ計算が完了した時期は1928年 (昭和3) はじめと書かれている。例として、〈予定より早く一年半で六種のレンズの計算が完了した。昭和三年の初めのことだった〉など (「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975 p.16) 。文字盤研究に着手した時期は明記されていないが、レンズ計算もまた大変にむずかしい仕事で、朝から深夜までこれに没頭していた茂吉の様子をかんがえるに、文字盤の研究と並行できたようにはおもえない。このため本稿では、試作第1号機文字盤改良のために茂吉が文字盤研究に着手した時期をレンズ計算完了以降、すなわち「1928年 (昭和3) はじめ以降」とかんがえている。
[注6]『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969 p.103
【おもな参考文献】
『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969
「文字に生きる」編纂委員会 編『文字に生きる〈写研五〇年の歩み〉』写研、1975
馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974
「書体設計者はパイオニアの精神で……」『季刊プリント1』印刷出版研究所、1962.3
「活版及活版印刷動向座談会」『印刷雑誌』1935年5月号、印刷雑誌社、1935.5
倭草生「写真植字機の大発明完成す」『実業之日本』昭和6年10月号、実業之日本社、1931
【資料協力】株式会社写研、株式会社モリサワ、今市達也氏
※特記のない写真は筆者撮影