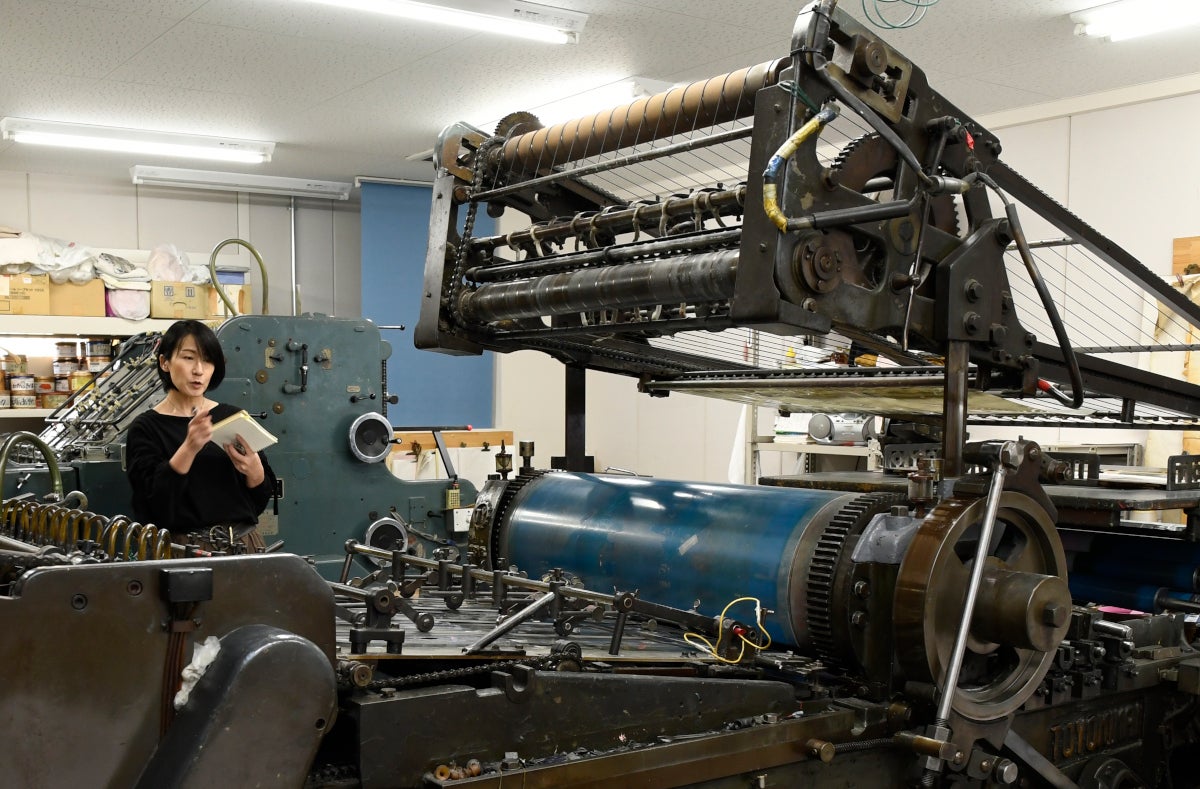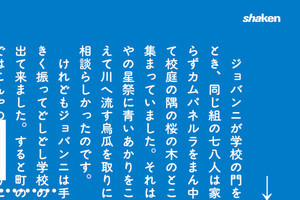フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
共同事業のはじまり
石井茂吉と森澤信夫は「邦文写真植字機の開発」という夢に向かって手を結ぶことにした。茂吉は37歳、信夫は23歳だった。
すでにふたりは1924年 ( 大正13 ) 7月24日に最初の特許、11月13日にふたつめの特許を出願していた。模型は最初の特許出願に先がけて、信夫が完成させていた。つぎに取り組むべきは、試作機の製作である。
作業場や仕事の分担を決めるにあたり、信夫は、あらたにふたりの仲間を加えることを提案した。ひとりは、東京高等工業学校 ( 現・東京工業大学 ) 出身で、もと星製薬の鉄工部主任だった吉川国広。そしてもうひとりは、信夫に海外の写真植字機の存在を教えてくれた、星製薬図案部長の長沢青衣だった。
茂吉は、そのふたりに多くは望めないと感じたが、資金面で力になるのではないかと考え、信夫の提案に賛成した。
吉川はこのころ、東京・鶯谷で、鶯湲製作所 [注1] という医療機械の製造工場を知人の佐藤某と共同経営していた。ここで試作機をつくろうということになった。
同1924年 ( 大正13 ) の暮れも押しせまった12月15日、茂吉と信夫、吉川、長沢の4人は、鶯湲製作所の2階に集まった。そして、茂吉が自筆作文してきた契約書に調印をした。といっても、4人とも認印は持ちあわせていなかったので、拇印をおした。
契約書の全文は、つぎのとおりだ。[注2]
( 原文は漢字カタカナ交じり文だが、ここでは漢字ひらがな交じり文で引用する。また同様に、漢数字を算用数字とし、漢字表記されている部分を適宜、ひらがなとしている )
契約書
甲 森沢信夫
乙 石井茂吉
丙 吉川国広
丁 長沢青衣
右当事者間において森沢信夫発明に係る写真装置 ( 大正13年特許出願第5120号および追加特許全部 ) の完成および該発明に関連する事業の遂行について契約すること左の如し
1、森澤信夫発明に係る写真装置の特許権は甲および乙の共有とす ただし右共有の手続は大正14年2月末日までに実行するものとす
2、乙は該写真装置の完成およびこれを使用して経営すべき印刷所の設立について全責任を負うものとす
3、丙および丁は乙の事業に対し最善の努力をなすものとす特に丙は事業の経営に対し丁は技術および営業に対し極力援助を与えるものとす
4、発明の完成はおよそ大正14年秋と予定すれども印刷所はこれに先んじ大正14年春 (可及的早く) 設立し事業開始するものとす
5、印刷所の資金は最初約5万円とし発明の完成に従い適当の時期において徐々に増資拡張を行なうものとす
6、発明実施の場合においては特許権は資本金の一部として提供するものとす
7、甲および乙は丙および丁の援助に対して必ず酬ゆることあるべきことを誓う
本契約書は4通を作成し各当事者1通を保有するものとす
大正13年12月15日
森沢 信夫 印
石井 茂吉 印
吉川 国広 印
長沢 青衣 印
こうして石井茂吉と森澤信夫は正式に提携し、共同事業がスタートした。日本の写真植字機の歴史の記念すべき1ページ目が、ここにはじまったのである。 茂吉が星製薬を辞職して、4カ月が経っていた。
ひとつ屋根の下
信夫はまだ星製薬に在職中だったが、早速オートバイで毎日、鶯湲製作所にかよいはじめた。ところが、ほどなくして吉川が鶯湲製作所の経営責任者と不仲になり、そのことから会社が倒産してしまった。当然、同社を作業場としては使えなくなり、試作機の製造は本所大島町 ( 現・東京都江東区 ) の小林製作所に依頼することになった。信夫は監督と指示のため、今度はこの小林製作所に毎日のようにオートバイでかよった。
やがて信夫は、写真植字機の開発に専念するため、1925年 ( 大正14 ) 3月に星製薬を辞職した。1925年 ( 大正14 ) 春までに事業開始という、契約書の内容にもとづいた行動でもあった。
信夫はそれまでの下宿を引きはらうと、王子の石井家の向かいにあった四軒長屋のひとつに住みこんだ。この長屋は石井家の持ちもので、借家としているものだった。引っ越しは3月23日。ちょうど信夫24歳の誕生日、その日であった。[注3]
鶯湲製作所の倒産を境に、吉川の足は自然に遠のいた。長沢も、最初から一度も顔を見せないまま、写真植字機の事業から離れていった。結局は、茂吉と信夫のふたりになった。
星製薬を辞めてから、信夫には一銭の収入もなくなっていた。三度の食事は茂吉の妻・いくが「森澤さんはお客さんだから」とこしらえてくれ、茂吉の家族と一緒に食べた。あてにしていた作業所の倒産という、おもいがけぬつまずきが招いたできごとだったが、茂吉と信夫がひとつ屋根の下に近い状況で暮らすことになったのは、写真植字機の共同開発にとってはよいことだった。
しかしもちろん、茂吉自身にも収入はない。資金面の援助をあてにしていた吉川と長沢は去ってしまった。写真植字機の開発費用は、石井家が経営する神明屋の収入と、茂吉の貯えでまかなわれた。覚悟はしていたものの、茂吉は研究だけでなく、資金面にまで心を配らなくてはならなくなった。
そこには、いくの内助の功も大きかった。茂吉は〈研究一途の、世事には全く無関心な人だった〉と、後年、いくたち家族はふりかえっている。のちに茂吉のあとを継いで写研社長となった三女の裕子 (ひろこ) は〈お父さんは研究一本、雑用は全部お母さん……〉と言い、いくは〈お父さんが人が好いもんで、私がいつも悪役。お金にきれいなんです。昔はね、東大出の学士さまってのには、ちょっとそんな空気がありましたね〉と語る。しかしそんな茂吉の話をする家族は、じつにあたたかな笑顔なのだった。[注4]
(つづく)
[注1] 読みは「うぐいすだにせいさくしょ」か。
[注2] 馬渡力 編『写真植字機五十年』(モリサワ、1974) pp.97-98
[注3] 森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』(モリサワ写真植字機製作所、1960) p.9
[注4] 「親子三人」『朝日新聞』1973年 (昭和48) 5月27日より。石井茂吉の妻・いく、三女・裕子、四男・不二雄の鼎談で、なごやかに話す3人の写真が掲載されている。
【おもな参考文献】
『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)
石井茂吉「写真植字機 光線のタイプライター」『書窓』第2巻第5号 、アオイ書房、1936年7月
「この人・この仕事 写真植字機の発明と石井文字完成の功績をたたえられた 石井茂吉氏」 『実業之日本』昭和35年4月1日特大号、実業之日本社、1960
森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960
馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974
産業研究所編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代(1) 』産業研究所、1968
日刊工業新聞編集局『男の軌跡 第五集』にっかん書房、1987
杜川生「印刷界の一大革命 活字無しで印刷出来る機械の発明」『実業之日本』大正14年12月号、実業之日本社、1925
橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社)
倭草生「恩賜金御下賜の栄誉を担った 写真植字機の大発明完成す ―石井、森澤両氏の八年間の発明苦心物語―」『実業之日本』1931年10月号、実業之日本社、1931
「親子三人」『朝日新聞』1973年 (昭和48) 5月27日付
【資料協力】
株式会社写研、株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影