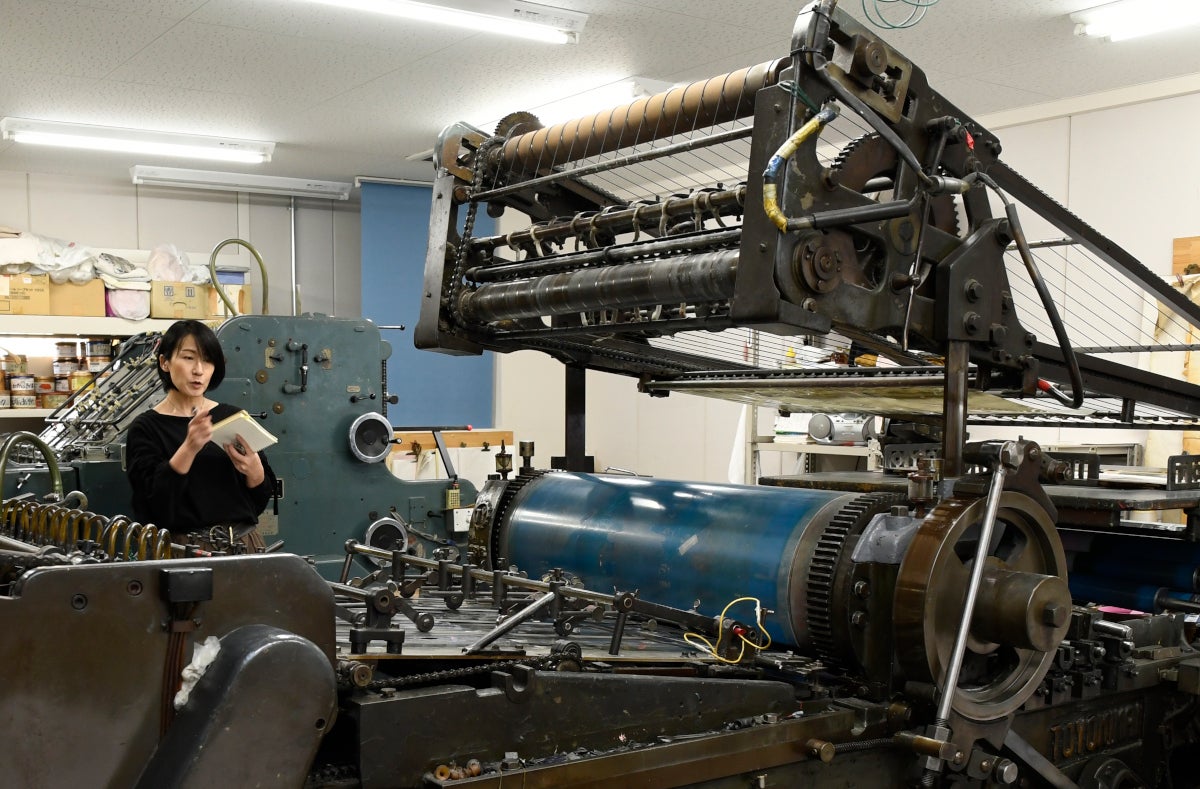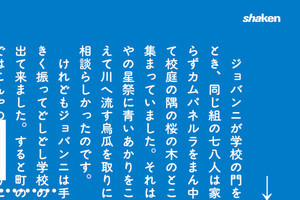フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
国字問題への興味
話はまたすこしさかのぼる。1924年 (大正13) 7月24日の特許出願に向けて、信夫の相談にのるかたちで茂吉も一緒に邦文写真植字機に取り組むなかで、ふたりはイギリスの『ペンローズ年鑑』や、オーギュスト&ハンター写真植字機のカタログなど、海外の写真植字機にかんする雑誌や資料を取り寄せては読んだ。
信夫に相談された時点では、茂吉は〈 ( 筆者注:自分は ) もともと印刷にはズブの素人であった、私は機械屋で、〉[注1]〈 それに深入りする考えはなかった〉[注2]、〈 ( 筆者注:写真植字の研究をはじめた理由を問われて) とりたてて、これだという程の強い理由があったのではありません 〉[注3] という様子だったが、信夫の話を聞き、海外の文献を読んでいるうち、この機械への関心がしだいに高まっていった。
欧米で研究されている写真植字機は、欧文タイプライターやライノタイプにヒントを得てスタートしたものだった。ならば日本の場合は、邦文タイプライターを発展させた形のものがよいのではないか。[注4] 茂吉は機械技術者の立場から、そんな漠然とした手がかりをつかんでいた。「光線のタイプライター」というコンセプトが、茂吉のなかに生まれかけていた。[注5]
もうひとつ、茂吉の心を刺激していたのは「国字問題」だった。日本では明治時代から、その表記をめぐりさまざまな議論が交わされていた。日本語は、漢字、ひらがな、カタカナの入り交じる複雑な表記であるうえ、数千もの漢字をもちいる。これが非効率であるとして、漢字を廃止すべきとか、使用する漢字の数を制限すべきという主張、あるいは、すべてをカタカナやひらがな、ローマ字表記にすべきといった議論がおこなわれていたのだ。
星製薬を辞める前に信夫が茂吉のところにもってきたのは、1924年 (大正13) 3月24日付の朝日新聞東京版に掲載されていた、郡山幸男による「写真植字機と国字問題」という記事だった。
記事はまず、1890年前後にアメリカで「ライノタイプ」と「モノタイプ」というふたつの画期的な機械が発明され、この恩恵によってアルファベットなど少数の文字が使われる国々では、活版印刷がおそろしいほど発達を遂げたと述べる。
ライノタイプは1874~1900年にマーゲンターラーとその後継者が完成した機械で、原稿にしたがってキーボードのキーを押すと、該当する活字母型が機械上部の母型庫の溝から落ちてきて、順番に並ぶ。1行分の母型が並ぶと鋳造部に送られ、所定の行長に調節されたのち、ここに地金が流し込まれて1行分の活字塊 (スラッグ) を鋳造する機械だ。
モノタイプは活字を1本ずつ鋳造する機械で、あらかじめ鑽孔機(さんこうき)[注6]で紙テープに原稿を入力し、この鑽孔テープをモノタイプにセットすると、機械内部の母型盤 ( 母型が多数収蔵された盤 ) が縦横自在に動き、入力された順番に活字を鋳造できるというものである。いずれも、活字棚から1本1本活字を手で文選して組版する手間を大幅に軽減する、画期的な発明だった。[注7]
日本でも、邦文タイプライターの発明者としても知られる杉本京太が1920年 ( 大正9 ) に邦文モノタイプを発表した。しかし、まだ手彫りの種字から電胎母型をつくっていた時代においては、漢字を含む数千字もがおさめられた母型庫が機械1台ごとに1つずつ必要な邦文モノタイプは普及が進まず、一部の印刷会社や新聞社で使用されるのみだった。[注8]
-

杉本京太が発明した邦文モノタイプ。鑽孔テープに打ち込んだ順番どおりに、活字を1字1字鋳造する。(「いよいよ邦文自働植字機 邦文モノタイプ完成」『印刷雑誌』大正9年5月号、印刷雑誌社、1920 p.12より
-

邦文タイプライター、邦文モノタイプの発明者・杉本京太 (1882-1972 ) [注9] (「いよいよ邦文自働植字機 邦文モノタイプ完成」『印刷雑誌』大正9年5月号、印刷雑誌社、1920 p.11より
専門家が思いもよらぬ機械
話を郡山の記事に戻そう。
この記事の内容を、茂吉は後年の寄稿文でつぎのように書いている。
当時の同僚の森澤信夫が、ある日自分のところへ、「国字問題の将来」( 筆者注:実際のタイトルは、前述のとおり「写真植字機と国字問題」) とかいうタイトルの朝日新聞の記事を持って相談にきた。記事には「イギリスの『ペンローズ年鑑』によると、イギリスでは数年前から写真植字機の研究が行なわれており、すでに見本機械もできている」と写真つきで掲載されていた。
さらに記事には、「 ( アルファベット26文字という ) 少ない文字数で成り立つ欧文圏では、使用する活字も少ないため、『ライノタイプ』という活字自働鋳植機もさかんに活用されているし、写真植字機のような、さらに革命的な機械の実現も可能だろう。しかし、漢字というやっかいな文字を数千字も必要とする日本では、ライノタイプや写真植字機の実用化はとうていだめだ」と〈絶望的に書いてあった〉というのである。[注10]
前掲の朝日新聞の記事を実際に読んでみると、そこまで「絶望的に」は書かれていない。記事では、同年2月刊行の『ペンローズ年鑑』でバウトリー写真植字機の詳報が掲載されたことにからめて、欧米ではライノタイプやモノタイプが発明されて活版印刷が飛躍的な進化を遂げ、ただでさえ日本よりもはるかに進んでいるのに、さらに写真植字機という、活字を使わない自動組版機が実現すれば、日本との差がますます広がってしまうという見地から、国字問題の解決の必要性を提示している。漢字、ひらがな、カタカナで数千字をもちいる日本の国字をなんとかしないと、日本をただ退歩させるだけだ、というのだ。郡山自身は国字問題にかんして、「世界をみすえて日本語をすべてローマ字表記にすべき」との主張をもっていた。[注11]
印刷の専門家や業界人たちは、郡山の記事を見ても、邦文モノタイプの普及ですら遅れている日本で、「写真植字機の開発に取り組もう」などとは思いもよらなかっただろう。しかしその「思いもよらない写真植字機」に茂吉は惹かれていた。それをつくることができたら……。機械屋としての興味だった。信夫が星製薬で、なにも知らずに活版輪転印刷機の組み立てを請け負ったように、素人とはえてして無鉄砲なものである。
だが、茂吉はすでに37歳である。妻とふたりの子どもに加え、母と弟妹をも養う身だ。そんな状況では、「機械屋の興味」だけで飛びこめる仕事ではない。その気になれば、茂吉は職が得られないわけではない。東京帝国大学を出て、神戸製鋼所、星製薬で機械技師として働いた経歴は、ひとのうらやむ条件だった。もとめれば職が得られるのに、あえて開拓者の茨の道に踏みこむことは、家族のことを考えると、ためらわれた。
(つづく)
[注1] 石井茂吉「写真植字機 光線のタイプライター」『書窓』第2巻第5号、アオイ書房、1936年7月 p.399
[注2] 橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社) p.93
[注3] 「この人・この仕事 写真植字機の発明と石井文字完成の功績をたたえられた 石井茂吉氏」 『実業之日本』(昭和35年4月1日特大号、実業之日本社、1960) p.132
[注4] 邦文タイプライターは1915年 (大正4) に杉本京太が発明していた。〈欧文タイプライタのキーの代わりに多数の活字を入れた活字盤があり、この活字盤上を自由に運行する印字機構があって、これを求める文字の活字上に止めてその活字を自動的につかむ。つかんだ腕は欧文タイプライタのタイプバーと同様に働き〉〈タイプバーが持ち上がり、プラテンに巻いた紙の面を打つ。〉日本印刷学会編『印刷事典 第五版』(印刷学会出版部、2002) p.310
[注5] 「光線のタイプライター」は、志茂太郎が主宰するアオイ書房の雑誌『書窓』第2巻第5号 (1936年7月) に茂吉が寄稿した記事のタイトルである。
[注6] 鑽孔機:さんこうき。鑽孔とは、〈テレタイプ・漢字テレタイプ・自動モノタイプ・自動写真植字機などで符号化文字データを保持するために紙テープ上の符号孔を用いていた。〉。この符号孔をあける機械のことを「鑽孔機」という。日本印刷学会編『印刷事典 第五版』(印刷学会出版部、2002) ライノタイプ p.214
[注7] 日本印刷学会編『印刷事典 第五版』(印刷学会出版部、2002) ライノタイプ p.542、モノタイプ p.529
[注8] モノタイプは機械1台1台に母型庫をもつ必要があったため、邦文モノタイプが本格的に使用され始めたのは、国産ベントン彫刻機が普及した1949年 (昭和24) 以降とおもわれる。ただし、大印刷会社や新聞社など、一部では早々に邦文モノタイプを導入していた。『印刷雑誌』1926年 (大正15) 8月号 (印刷雑誌社) に掲載された日本タイプライター株式会社 (杉本京太らが設立) の広告によると、各社の所有台数は、大阪毎日新聞社36台、株式会社秀英舎46台、日清印刷株式会社20台、印刷局15台、時事新報社12台、朝鮮印刷株式会社12台、その他新聞社、雑誌社、活版印刷所に約200台で、合計300台以上が使用されていると書かれている。
[注9] 杉本京太 (1882-1972) は、日本語のタイプライターおよび植字機の完成は不可能ではないと信じ、1909、10年 (明治42、3) ごろからこれらの発明に取り組み、1915年 (大正4) に邦文タイプライターを発明。その後、邦文モノタイプの発明に注力し、1920年 (大正9) 5月、東京・築地にある東京府立工芸学校にて、多くの印刷業者や学者立会の上、杉本自身によって発表、実演がおこなわれた。「いよいよ邦文自働植字機 邦文モノタイプ完成 邦文タイプライターの発明者 杉本京太氏の苦心遂に酬ふ」『印刷雑誌』大正9年5月号 (印刷雑誌社、1920) pp.10-14などを参照。
[注10] 石井茂吉「写真植字機 光線のタイプライター」『書窓』第2巻第5号 (アオイ書房、1936年7月) p.399 原文は次のとおり。
〈当時社僚の森澤信夫君が、或る日私のところへ、「国字問題の将来」とかいう朝日新聞の記事を持って相談に来られた。その記事の中に、ペンローズ年鑑 ( 英国で発行される印刷年鑑 ) の所載するところによると英国に於ては数年前から写真植字機の研究が行なわれて居って既に見本機械も出来て居ると、その機械の写真まで掲載してあって、文字の数の少い欧文圏ではライノタイプという活字自動鋳植機も盛んに活用されて居るし、写真植字機のような更に革命的な機械の実現も可能ではあろうけれど、漢字という厄介な文字を必要とする我が国では到底駄目だ、と絶望的に書いてあった〉
[注11] 郡山幸男は「写真植字機と国字問題」『朝日新聞』(1924年3月24日付、東京朝刊3面) の記事に先がけ、1921年 (大正10) 6月21日、おなじく朝日新聞に「活版よ左様なら」という寄稿をしたことがあった。どちらかというとこちらの記事のほうが、国字問題について強い口調で、カナやひらがなにすべきという主張を退け、世界的になるべき日本人にとって日本語改善の最初の準備がローマ字採用であると強く主張している。この時期、国字問題についてはさまざまな議論がかわされていた。茂吉は、信夫がもってきた3月24日付の記事から国字問題に関心を寄せ、さかのぼって1921年の記事なども読み、それをふまえて『書窓』第2巻第5号p.399への寄稿で「絶望的」と表現したのかもしれない。
【おもな参考文献】
『石井茂吉と写真植字機』写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)
石井茂吉「写真植字機 光線のタイプライター」『書窓』第2巻第5号 、アオイ書房、1936年7月
杜川生「印刷界の一大革命 活字無しで印刷出来る機械の発明」『実業之日本』大正14年12月号、実業之日本社、1925
橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社)
倭草生「恩賜金御下賜の栄誉を担った 写真植字機の大発明完成す ―石井、森澤両氏の八年間の発明苦心物語―」『実業之日本』1931年10月号、実業之日本社、1931
「いよいよ邦文自働植字機 邦文モノタイプ完成 邦文タイプライターの発明者 杉本京太氏の苦心遂に酬ふ」『印刷雑誌』大正9年5月号 、印刷雑誌社、1920
日本印刷学会編『印刷事典 第5版』印刷学会出版部、2002
郡山幸男「写真植字機と国字問題」『朝日新聞』1924年3月24日付、東京朝刊3面
矢野道也「日本に於けるオフセット印刷」『印刷雑誌』大正15年11月号、印刷雑誌社、1926
【資料協力】
株式会社写研、株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影