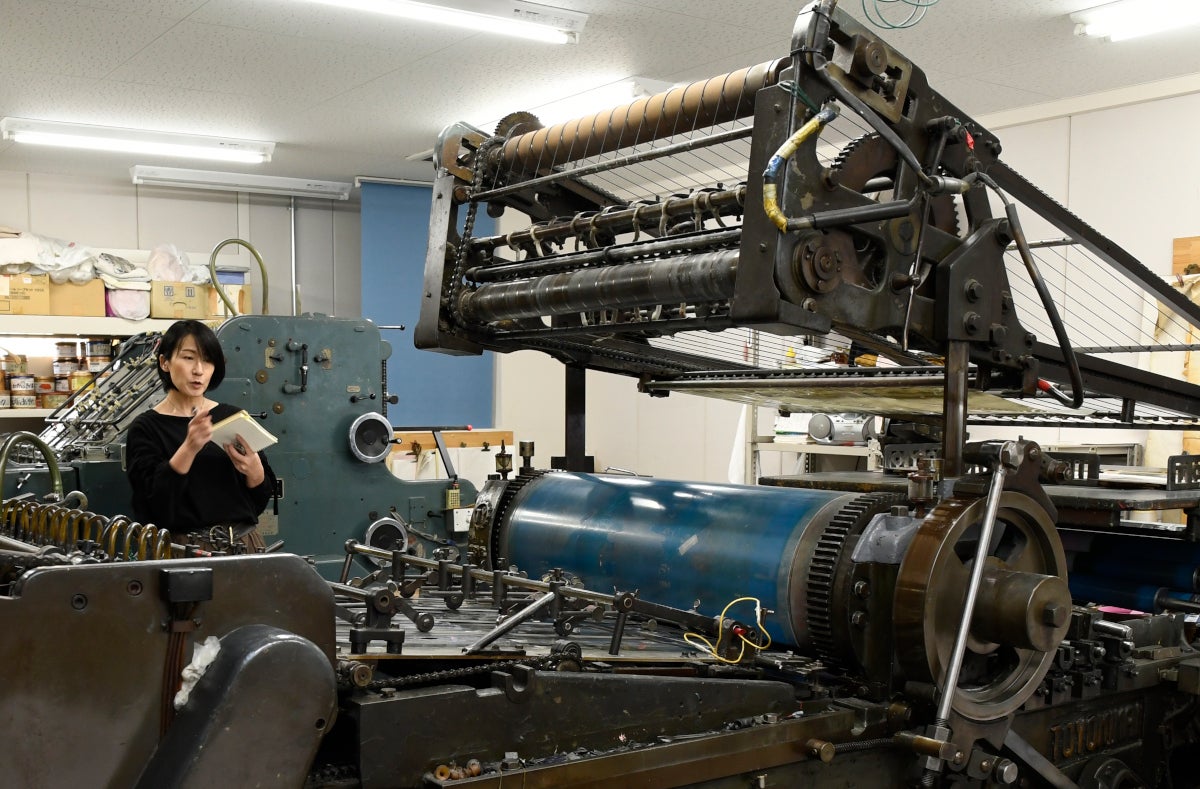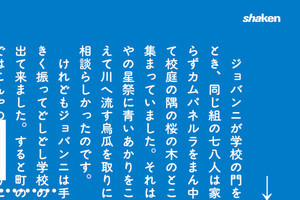フォントを語る上で避けては通れない「写研」と「モリサワ」。両社の共同開発により、写研書体のOpenTypeフォント化が進められています。リリース予定の2024年が、邦文写植機発明100周年にあたることを背景として、写研の創業者・石井茂吉とモリサワの創業者・森澤信夫が歩んできた歴史を、フォントやデザインに造詣の深い雪朱里さんが紐解いていきます。(編集部)
「写真装置」
ときは1924年 (大正13) 、春から初夏へと季節が移り変わるころのことだったろうか。ちいさな機械を抱えた森澤信夫が、同じ星製薬に勤める石井茂吉のもとにやってきた。
3月の終わりごろ、信夫が朝日新聞の「写真植字機と国字問題」という記事をもって茂吉の意見を聞きにきたことがあった。イギリスで研究されているという写真植字機を、自分は日本語でやりたいとおもっているが、どうおもうか、という相談だった。
茂吉が「おもしろそうじゃないか。やってみたらどうだ」と答えると、信夫はうなずきながら去っていったのだった。
その信夫が「できた!」といって、ちいさな機械を持ってきたのである。
「先日相談した機械の模型です。名前は『邦文写真植字機』にしました」
茂吉はまず、図面もなにもないことに驚いた。信夫の模型は、茂吉には御所車 [注1]の車輪がないような形のものに見えた。
( おもいつきだけを形にあらわした模型のようだ。実用にはまだほど遠い )
茂吉はそうおもったが、日本にはまだ誕生していない機械の構想である。特許はとっておいたほうがよいと考えた。
「森澤くん、まず特許をとったほうがよいだろう。知人の弁理士を紹介するから、特許申請文の作成を依頼するとよいよ」
茂吉は弁理士の馬場頴一 (えいいち) を紹介してくれた。信夫はさっそく図面を描きはじめたが、製図法の知識をもっていない。正式な基礎教育を受けていない信夫に、茂吉は図面の引き方や、手を加える個所をアドバイスしてくれた。
こうして信夫は苦心に苦心を重ね、写真植字機の図面を完成させた。そして、馬場の作成した文書とともに、特許を出願した。1924年 (大正13) 7月24日。特許権者 (発明者) は森澤信夫。そして、申請書作成の過程でくり返し助言をした石井茂吉も、特許権者として名を連ねた。この特許は翌1925年(大正14) 3月11日に公告され、同6月23日に特許がおりた。日本で最初の「写真植字機」の発明である。
ただし名称は「写真装置」となった。出願にあたり、信夫は「邦文写真植字機」を名称としていたが、〈特許局より、そんな名称はないからといって、「写真装置」となおされた〉という。[注2]
一方で茂吉の見方はきびしく、『石井茂吉と写真植字機』では〈今日の写真植字機の基本の形となるものに比べるとまだまだ幼稚なオモチャに等しいものであった。「写真植字機」という言葉が納得できなかったのか、それを納得させるだけの実質をもっていなかったためか、「写真装置」の名前に変更されて特許がおりた (後略)〉[注3] と記述されている。「写真植字機」の名称を特許局が受け付けだしたのは、1929年 (昭和4) 1月からであった。[注4]
ふたりの交流
特許を出願してまもなく、同年8月に、茂吉は星製薬を退職した。本連載第17回で述べたとおり、社内の不祥事を星社長に訴えた茂吉は、しかし結局、星から退職勧告を受けることになった。誤解を受けてのことだったが、茂吉にはもはや反論する気もなかった。
関東大震災で倒壊した実家の神明屋 ( 米屋兼雑貨屋 ) は、このころすでに再建し、茂吉一家と母、弟妹は梶原 ( 現・東京都北区堀船町。王子の近く ) に戻っていた。神明屋の経営は、妻のいくが母から引き継いでおり、自分が星製薬を辞めても、当面の生活には困らない。茂吉は、次の仕事を慎重に探そうと考えていた。
信夫が邦文写真植字機の構想について、茂吉の話をしきりに聞きにきていたのは、そんな時期だった。信夫は、7月24日に特許を出願したあとも、まだ改良すべき点があると感じていた。実用化に向けては試作機だってつくらなくてはならない。しかしさすがに試作機は、信夫の下宿でつくることはむりだった。
茂吉は星製薬に入社したときにオートバイを買ったが、彼の身体が弱いことを心配した妻のいくから「なるべく乗らないでほしい」と言われていた。それで信夫は、茂吉のオートバイを時おり借りるようになった。しばらく使って返しに行くと、いくが「また持っていってください」と言い、食事をごちそうしてくれた。そんなことがくり返され、茂吉のオートバイは結局、信夫の下宿にほとんど預けっぱなしになっていた。
そうした諸々の理由から、信夫は茂吉が8月に星製薬を退職したあとも、梶原に住まう茂吉の家を、たびたび訪ねるようになった。行くたびに写真植字機について聞く信夫に、会社を離れて自適の身だった茂吉は、いやな顔もせず、相談にのった。
やがて茂吉と信夫のあいだには、絆のようなものが生まれていった。信夫が試作機に向けて図面を描く過程で、機械の専門家である茂吉がなにかとアドバイスをして信夫の作業を側面的に助ける関係が、自然とできあがっていったのだ。
信夫は、機械技師としての知見を豊富にもつ茂吉に助けられていた。茂吉は、信夫が取り組んでいる「写真植字機」という未知なる機械に、しだいに興味を抱くようになっていった。
信夫は言う。
この事業に興味をもつようになった茂吉が、あるとき、「できれば自分にもこの仕事を手伝わせてくれ」と協力を申し出た、と。[注5]
茂吉は言う。
いつものように王子の家を訪ねてきた信夫が、あるとき「あれこれやってみるんやけど、どうもあんじょう (うまく) いきまへん。どないしてもやってみたい思うんやけど、自分ひとりの力ではあかんですよって、ひとついっしょにやってもらえまへんやろか」と茂吉の出馬を求めてきた、と。[注6]
2人の言い分は正反対のようでいて、どちらも真実なのかもしれない、と筆者はおもう。ひとは、当然ながら、それぞれ自分の立場から物事を見る。同じ事象を見ても、ひとによって受け止めかたは変わるものだ。写真植字機にまつわる茂吉と信夫の物語には、しばしばそうした場面が登場する。
信夫は、茂吉に助けられていた。きっと、「手伝ってほしい」という言葉が、本人も意識せぬあいだに漏れたことがあったのではないか。信夫はまだ23歳と若く、発明の事業化の経験がなかったし、事業を進めるための資金もなかった。模型に着手した当初は、星社長のポケットマネーから研究資金をもらっていたが、ちょうどこのころ、星製薬の経営は厳しい状況に追いこまれている。信夫を描いた文献にも、星の名は模型の完成以降、現れていない。
茂吉は、写真植字機に興味を抱いた。これは自分の取り組むべき仕事かもしれないと、機械技師としての嗅覚も働いただろう。彼がしだいに関心を深めるさまが、信夫には「手伝わせてほしい」という申し出に感じられたのではないか。
いずれにしても、「どちらが一緒にやりたいと言い出したのか」はさほど重要な問題ではない。大事なのは、石井茂吉と森澤信夫、2人の男が「邦文写真植字機の誕生」に向けてタッグを組みはじめた、その事実だ。
1924年 (大正13) 11月13日、ふたりはふたたび「写真装置の改良」という特許を出願した。7月の出願と同じく、特許権者 (発明者) は森澤信夫、特許権者は石井茂吉。
写真植字機の開発にふたりで取り組んでいく、その方針が固まっていった。
(つづく)
[注1] 御所車 (ごしょぐるま) :昔、貴人が乗った、屋形のある牛車 (ぎっしゃ) 。( 『新明解国語辞典』第7版、三省堂、2011 )
[注2] 森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』(モリサワ写真植字機製作所、1960) p.7
[注3] 『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969) p.81 ただしこの本は石井茂吉逝去後に書かれた文章であり、茂吉本人の記述ではない。
[注4] 森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』(モリサワ写真植字機製作所、1960) p.7
[注5] 森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』(モリサワ写真植字機製作所、1960) pp.93-94
また、同書には、1924年(大正13) 7月24日の特許を森澤信夫が出願した後、石井茂吉が森澤に「この仕事を手伝わせてくれ」と申し出たことにより、特許権者 (発明者) 森澤信夫のほかに、石井茂吉が特許権者として1925年(大正14) 1月に連記された、と書かれている。
[注6] 『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969) p.81
【おもな参考文献】
『石井茂吉と写真植字機』(写真植字機研究所 石井茂吉伝記編纂委員会、1969)
森沢信夫『写真植字機とともに三十八年』モリサワ写真植字機製作所、1960
馬渡力 編『写真植字機五十年』モリサワ、1974
産業研究所編「世界に羽打く日本の写植機 森澤信夫」『わが青春時代(1) 』産業研究所、1968
日刊工業新聞編集局『男の軌跡 第五集』にっかん書房、1987
橘弘一郎「対談第9回 書体設計に菊池寛賞 写真植字機研究所 石井茂吉氏に聞く」『印刷界』1961年10月号 (日本印刷新聞社)
郡山幸男「写真植字機と国字問題」『朝日新聞』1924年3月24日付、東京朝刊3面
倭草生「恩賜金御下賜の栄誉を担った 写真植字機の大発明完成す ―石井、森澤両氏の八年間の発明苦心物語―」『実業之日本』1931年10月号、実業之日本社、1931
【資料協力】
株式会社写研、株式会社モリサワ
※特記のない写真は筆者撮影