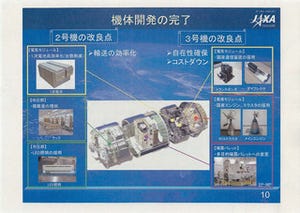超高速の"デコトラ"衛星?
福岡工業大学が開発した「FITSAT-1」(にわか衛星)のミッションは2つ。
1つは、高速な送信機の実証実験だ。従来、1Uサイズの超小型衛星(一般にキューブサットとも呼ばれる)では、通信に430MHz帯を使うことが多かったが、通信速度は1,200bps程度と、非常に遅かった。通信が遅いと、せっかく画像を撮影しても、データをたくさん送ることが難しいという問題がある。
FITSAT-1には、ロジカルプロダクトという福岡市の企業が開発した5.8GHz帯の送信機を搭載。およそ100倍高速な、115.2kbpsという通信速度の実現を目指す。衛星の開発責任者である田中卓史教授は、同一時間で送ることができる画像の大きさについて、「切手サイズが絵はがきサイズになる」と説明する。
もう1つのミッションがユニーク。LEDを搭載して光らせ、モールス信号でメッセージを描こうというのだ。
ただ、このとき問題になるのは衛星の姿勢。せっかくのLEDが地上から見えないと意味がないので、姿勢を制御するために、FITSAT-1には永久磁石を搭載した。これで、磁力線の向きに沿った姿勢で飛行するようになるので、ちょうど福岡の緯度あたりでLED面とアンテナ面が地上を向くよう設計した。
しかし、1面だけだと南半球を飛行しているときに実験ができないため、反対側の面にもLEDを搭載した。北半球で見える面には緑色LED(3W×50個)、南半球で見える面には自動車のテールランプをイメージして、赤色LED(3W×33個)を用意。電力をかなり使うので、周回中に充電しておいて、数分間だけ発光させる。
なお、この衛星は放出時に、前方と後方を撮影するためのカメラも搭載する。10秒ごとに交代して撮影するとのことで、離れていく国際宇宙ステーション(ISS)や、前方を進む他の衛星の様子が見られると期待される。
あの宇宙メーカーが衛星本体に初参入
「WE WISH」を開発した明星電気は、宇宙分野での実績が豊富なメーカー。その歴史は古く、1955年に打ち上げられたベビーTロケットのために、テレメータ送信機を開発したところまでさかのぼる。特に観測機器には強く、小惑星探査機「はやぶさ」では蛍光X線スペクトロメータ(XRS)を開発し、月周回衛星「かぐや」ではハイビジョンカメラをはじめとする8つの装置を担当した。
搭載機器の開発には慣れた同社だが、衛星本体を開発するのはこれが初めて。今回の公募について、「衛星を1から10まで作る技術はもっていなかった。それを習得する絶好のチャンスだった」と同社技術開発本部装置開発部の永峰健太氏。人材育成としても考えられており、社内の20代の若手技術者が中心となって開発したという。
ミッションは、小型熱赤外カメラによる地表温度の観測。初めての衛星となれば、普通は光学カメラを搭載して見栄えのいい写真を撮りたくなるところだが、そこをあえて熱赤外カメラにしているのは、いかにも観測装置を多く手がけた同社らしい。
このカメラは新開発されたもので、小型、低消費電力、広視野角、冷却が不要、といった特徴がある。地上分解能は2km、500×500kmの範囲を撮影することができる。地表面の温度分布が分かるようになっており、同社は「ヒートアイランドの様子が見られれば」と期待する。
キューブサットながら、様々な展開機構を持つこともWE WISHの特徴。両側に50cm伸びるブームは、重力傾度安定のためのものだ。このようにすると、ブームが垂直方向になるよう力が働いて姿勢が安定するのだが、上下が反対になる可能性もある。もし逆になっても反転できるように、磁気トルカも1軸分だけ搭載した。
|
WE WISHの展開の様子。太陽電池パドル、ブーム(受信アンテナ)、送信アンテナの順番で展開する |
50kg級衛星の機能をぎゅっと圧縮
今回の3機のうち、唯一2Uサイズと大きいのが、和歌山大学、東北大学、東京大学が合同で開発した「RAIKO(雷鼓)」だ。重量は2.6kgで、製造は東北大学が担当。同大学は50cmサイズの超小型衛星「RISING」(雷神)シリーズを開発した経験があるが、その技術を「このサイズにどれだけ転用できるか挑戦した」(坂本祐二助教)のがコンセプトだという。
まずカメラは、カラー広角CMOS、カラー魚眼CCD、モノクロCCDというタイプの異なる3台を搭載する。主に、カラー広角CMOSは放出時のISSを、カラー魚眼CCDは地球を撮影することが目的。モノクロCCDはスターセンサーであり、写っている星の位置を地上で分析して、衛星の姿勢を判断する。
ちなみにISSからの放出時には、30秒~1分間隔で、合計46枚の画像を撮影する計画。使うのは後方に設置されたカラー広角CMOSだが、姿勢がずれていく可能性があるため、3枚だけカラー魚眼CCDも混ぜるようシーケンスを組んでいるとのこと。
また、高速通信のために、このクラスのサイズでは異例のKuバンド(13GHz帯)送信機を搭載。これはアドニクスという東京・八王子市の企業が開発したもので、最大500kbpsというデータ通信が可能になる見込みだ。RAIKOにはこのほか、Sバンドの送信機と受信機、Uバンドの受信機も搭載。送受信をそれぞれ2系統用意することで、信頼性も向上している。
そして注目なのが、全てのミッションを終えてから最後に実施する予定の膜展開実験。一辺50cmの薄膜を展開し、空気抵抗を大きくすることで、より短期間で再突入させることを狙うもの。今回の投入軌道では、もともとの高度が低いため、何もしなくても放出後数カ月程度で落下する見込みだが、デブリを増やさない技術として注目されており、今後の超小型衛星への応用が期待される。
薄膜はポリイミド製でアルミ蒸着したもの。側面に収納されており、メジャーのような支柱が解放されることで展開する仕組み。通常、高度300kmからだと再突入まで1カ月半ほどかかる見込みだが、膜を展開すれば「5日くらいであっという間に落ちてくる」(同)とのこと。膜を展開すると通信ができなくなるが、追跡して効果を検証する予定。
HTVからの放出というアイデアも
HTVに搭載することで、打ち上げ環境が緩和されるというメリットがあることは前回述べた通りだが、一方で、通常のロケット相乗りに比べ軌道高度が低いために、宇宙での滞在期間が短くなってしまうというデメリットも存在する。
これについて、和歌山大学の秋山演亮特任教授(宇宙教育研究所長)は、「基本的には、教育や技術革新のためのツールだと思っている。本来はもっと上の高度の方が使いやすいが、教育のためのニーズはたくさんあるし、いろんな実験をもっと気軽にやりたいという要求もある。そういったものに、この方法は非常に適している」とコメント。
ただし、貴重な打ち上げ機会をもっと有効に活用するために、なるべく軌道上寿命が長くなる高度の軌道を使いたいという希望は当然ある。秋山教授は「ISSから分離したときのHTVにはまだ燃料が残っている。今後、分離後のHTVを使って放出するなどのオプションも検討して欲しい」との要望も述べた。
また、有人施設であるISS内に運び込まれ、宇宙飛行士が扱うということで、衛星に対し、安全面での要求が増えるのではないかという懸念もあるが、東北大の坂本助教は「シャープエッジには特に気をつけた。じつは一カ所削り忘れていた所があって、組み上がった状態のまま処置するのに苦労した」という開発時のエピソードを披露した。
「月刊宇宙開発」とは……筆者・大塚実が勝手に考えた架空の月刊誌。日本や海外の宇宙開発に関する話題を、月刊誌のような専門性の高い記事として伝えていきたいと考えているが、筆者の気分によっては週刊誌的な内容も混じるかもしれない。なお発行ペースについては、筆者もどうなるか知らないので気にしないでいただきたい。