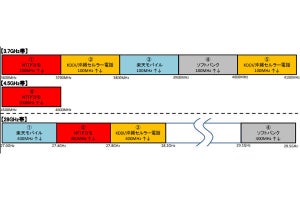KDDIとNPO法人離島経済新聞社が離島事業者を対象とした販路拡大・商品PR講座「しまものラボ」を、大分県の離島(姫島、大入島、屋形島、深島)で開始した。2015年12月からスタートしたプロジェクトで、今回は6回目の開催となり、県単位で複数の離島を対象にする最初の試みとなる。参加事業者に対して2019年9月までに全5回のPR講座を提供することで、社会の持続的な成長に貢献する会社として離島を支援、事業者による厳選商品をau WALLET Marketで順次販売していく。
離島の特産品をECサイトで販売
大分県には7つの離島がある。そのひとつ、姫島の姫島村長でもあり、大分県離島振興協議会会長でもある藤本昭夫氏は、離島7つはどこも過疎で悩んでいると離島地域の現状を訴える。さらに、基幹産業の漁業が厳しい状況で、一部の事業者が品物を作って売るようなチャレンジをしているものの、島なので情報の入手も難しく、商品を船で運ぶ輸送コストもかかるという。
それでも姫島はITアイランド構想(離島におけるITの可能性を広げ、IT人材の育成などを目指す取り組み)で島の復興を目指しているたぐいまれな離島だ。外部からIT事業者を招致したり、ITに詳しい人材を育成したりするなどの取り組みにも熱心だが、島民がこうした事業を進んでやるのは無理がある。そこにKDDIから声がかかったのだという。まさに渡りに船である。
姫島の立地は、大分空港から一般道で約35キロ45分、大分駅から大分自動車道経由で約83キロ90分のフェリー乗り場から船に乗って約20分の距離にある。大分駅より空港に近い。だが、たった20分の乗船でも離島は離島だ。このフェリー以外に交通手段はないが、1日に12往復も便がある。普通に東京への日帰り出張も可能だ。それに人口も2,000人いる。
姫島対岸の国東市からの距離は約6キロ。光の海底ケーブルが敷かれているものの、島内に入ったところで村営のケーブルテレビ網に切り替えられ、帯域幅も現状では数Mbps程度しかでないという。村ではこの同軸ケーブルによる村内網を、今後2年間をかけて新しい光ケーブル網へと置き換える計画で事業を進めている。NTT西日本は島内に村営の同軸ケーブル網があることから、そのビジネスを邪魔しないためにも光網を整備しようとしないという背景もあるらしい。
参加者の熱心さがハンパない
インターネットへの取り組みがかなり早期に行われたゆえの悩みでもあり、この姫島村の果敢なITアイランド構想は、離島に対する先入観を打ち破る。新しいものへの取り組みに関する熱心さがハンパではないのだ。
とにかく参加事業者の顔ぶれが明るい。若い世代のメンバーが集まっていることもあるが、島の名産品を付加価値の高いオリジナル商品にして売るということに懸命になっている。日本全国で開催される催事などにも積極的に出店し、そのブランドの知名度を高めることにも熱心だ。
鯨本あつこ氏(NPO法人離島経済新聞社統括編集長)は、対岸からはすぐそこに見えても離島への移動にはすごく時間がかかるという。それだけにモノを作っても資材や移送コストがかかる上18人、25人などしか人口がない離島はたくさんあり、そういう島はこどもがいない。そんななかで、大分県の離島の場合は、家族がいて、若い事業者がいるのが特徴。人数が少ない割にパワフルだという強みがあるのが大分の離島だと説明する。だからこそ、講座でワンステップ上の次元に到達してほしいし、責任を感じながらも島の未来を明るくしていきたいという。
また、山中直樹氏(KDDI理事 九州総支社長)は、これまでの実績として22島を支援し、35商品・約5,600万円の売上げをかなえて、さまざまなメリットを感じてもらっている経緯を解説した。このプロジェクトで、KDDIが離島地域の産品や文化を発信していく特集ページ「しまものマルシェ」の売上げを約10%増加させた事業者もいるなど、全国販売による認知度向上をかなえたと効果をアピールする。KDDIが目指すSDGs達成だが、地方創生はそのひとつであり、これからもこの事業に積極的に取り組んでいきたいとした。
令和の離島はしたたかに進む
SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)は、外務省によると、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標だ。地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓うもので、離島支援はその典型的な取り組みのひとつだということだ。
とはいえ、今回の参加事業者を見る限り、大分の離島に悲壮感は感じられない。島民自らのエネルギーとパワーが感じられ、大企業の取り組みを利用してやろうというしたたかささえ感じられる。それが令和の時代の離島であり、自らをブランド化して高めていく力を感じる。
(山田祥平 http://twitter.com/syohei/ @syohei)