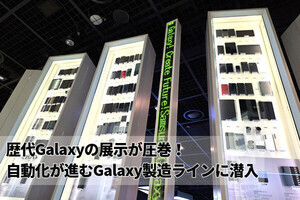大阪・関西万博の会場で、SamsungとQualcommが「真のAIパートナーになるための人間中心AI:壁を乗り越え、次に目指すもの」と題したパネルディスカッションを開催。両社の考えるスマホAIの将来像が語られた。
大阪・関西万博では、各国がテーマに沿った議論を行う「テーマウィーク」が設けられており、今回の企画は「学びと遊び ウィーク」において韓国が主催したもの。韓国SamsungとQualcomm Koreaの代表者によるパネルディスカッションとなっていた。
登壇したのはSamsung ElectronicsのMobile experience BusinessでTechnology Strategy Teamを率いるソン・インガン氏と、Qualcomm KoreaのSales & Business Development担当Vice Presidentであるキム・サンピョ氏。
-

左はSamsung ElectronicsのMobile experience BusinessでTechnology Strategy Teamを率いるソン・インガン氏。右はQualcomm KoreaのSales & Business Development担当Vice Presidentであるキム・サンピョ氏
スマホAIの2つの柱が「オンデバイスAI」と「マルチモーダルAI」
Samsungは、「Galaxy AI」としてGalaxyシリーズにAI機能を搭載してのにかち。このAI機能は2024年の「Galaxy S24」シリーズに初めて搭載され、2025年モデルの「Galaxy S25」シリーズでもさらに進化したものが搭載された。「Samsungは早くからAIの重要性を認識し、本当のスマホAI時代を切り拓いた」とソン氏はアピールする。
AI開発のためには継続的な投資が必要だとソン氏。ただ、AI開発はSamsung単体では難しく、QualcommやGoogleなどの戦略的パートナーと協力して開発しているという。特にQualcommとは、「オンデバイスAIとマルチモーダルAIの実現のために戦略的に親密な関係にある」とソン氏は話す。
キム・サンピョ氏は、このオンデバイスAIとマルチモーダルAIがスマホAIを支える2つの柱だと指摘する。オンデバイスAIは、AIの演算とデータ処理をデバイス内で完結させ、クラウドに依存しないAI技術。これによって、演算速度の高速化、低消費電力、低遅延、データを安全に保護できるといったメリットがあるという。
人間は聴覚/視覚/触覚といった感覚を使って物事を認識しているが、AIが人間と同様に触覚や音声、視覚情報で理解を行ってAIサービスを提供するのがマルチモーダルAIだ。
こうした技術を実現するための背景としてはAIモデルの軽量化があり、例えば2023年3月に175Bサイズ(1,750億パラメータ)だったモデルが、2024年7月には同性能でも8Bサイズに軽量化された。加えて、QualcommはSnapdragonにおけるCPU/GPU/NPUの性能を向上させており、これらがオンデバイスAI実現に繋がっているという。「2007年からAIに関連した技術を研究開発しており、これまでに20億以上のデバイスにAIエンジンを搭載してきた」とキム氏は強調する。
SamsungはさらにGoogleとも密接に協力しており、GoogleのAIであるGeminiを基盤としつつも、オリジナルのAI機能を独自のOne UIに深く統合することで、アプリレベルのAI機能とは異なる体験を提供できることが他社とは異なる点だとソン氏は話す。
AIを頻繁に利用するユーザーの数が、この6カ月で2倍以上に増加しており、50%が生産性向上、40%がクリエイティブ活動のためにAIを活用しているという調査結果もあるそうだ。そして「Galaxy S25」シリーズのユーザーの70%以上が「Galaxy AIを積極的に利用している」とソン氏は説明する。ちなみに最もよく使われているのは「かこって検索」だったという。
とはいえ、まだ多くのユーザーが「AIは自分の役に立つのか」「使うのが複雑で難しいのではないか」「個人データが安全に保護されるのか」といった疑問を感じているとソン氏は言う。こうした疑問に対してSamsungは、単に機能を提供するのではなく、「体験」というアプローチで利用拡大を狙っており、それにはユーザーの入力が最小限で、出力は最大化できるAIが必要というのがソン氏の考えだ。
例えば「かこって検索」では、今まで正確に文字で入力しなければならなかった検索も、画面に円を描くだけで検索できる。カメラに写した外国語を翻訳するといった機能も、スマホを向けるだけで翻訳できるようになった。
ソン氏は「タイピングは、人間にとって直感的な入力方法ではない」とし、対話をするかのようにAIに複雑な機能を命令できるのが直感的な入力方法だという。例えば、好きなスポーツの試合の予定をWebで検索して、カレンダーアプリに登録して、メッセージアプリで予定を共有するといった一連の作業を、音声で簡単に行えること。これがアウトプットの最大化に繋げられる。
ソン氏は、Galaxy AIが提供する3つの体験として、生産性/創造性/コミュニケーションという3点を挙げる。
生産性向上では、会議においてAIが話者を分析して議事録作成や要約を自動化したり、外国語の記事を翻訳/要約したりできる。SNSの投稿でも、キーワードと状況を伝えると、AIが自分のいつもの話し方を考慮した文章を提案してくれる。
創造性の領域では、不要な被写体を削除したり、服装を変更したり、動画の音声からノイズを除去したりできる。コミュニケーションでは、リアルタイム通訳機能で双方向のやりとりを翻訳して言語の壁を取り払ったり、通話内容をテキスト変換したり、要約したりといったことが可能になる。
SamsungとQualcommは、オンデバイスによるセキュリティやプライバシーの保護、個人データの保護を重要視する。Qualcommは、信頼性確保のために「責任あるAI原則」を策定し、国際的枠組みであるMLCommonsのAI Safetyワーキンググループに参加。AI生成コンテンツに電子透かしを加えるC2PAやTruePicとも協力しているとキム氏は説明する。
こうした両社の協力において掲げられているAIビジョンが「アンビエントAI」。スマホだけでなく、PC/ウェアラブル/IoT機器/家電製品といった様々なデバイスが有機的に繋がり、ユーザーの生活に浸透して自然にAIサービスが利用できるという未来だという。ソン氏は、「より自然で直感的になり、ユーザーが望むことを言わなくても、 AIがあらかじめユーザーの状況を理解することになる」と話し、それによってよりパーソナライズした体験を提供するという。
キム氏は、全世界の人口の71%がスマートフォンを保有し、1日の使用時間が4.5時間に上るというデータを紹介し、AI基盤の中心は変わらずスマートフォンとなり、さらに発展していくと予測。AIがよりパーソナライズして進化していくという方向性を示した。
「モバイルAIはSamsungが開拓している分野であり、今後も多様な機能を提供できる」とソン氏は強調し、今後もユーザーニーズを捉えながらスマホAIを強化していく方針を示していた。