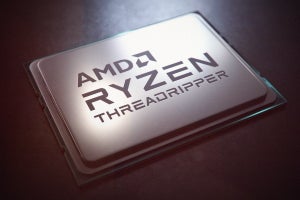米AMDは10月19日、Ryzen Threadripper Pro 7000 WXシリーズ及びRyzen Threadripper 7000シリーズを発表した。現状はまだ製品発表のみで、発売開始は11月であるが、まずは概要をご紹介したい。
Ryzen Threadripper Pro 7000WXは、2022年3月に発表されたRyzen Threadripper Pro 5000 WXシリーズの後継にあたる。基本的にはZen 4コアを使ったRyzen Threadripperというか、EPYC 9004シリーズのサブセットというか、そういう製品である。ただRyzen Threadripper Pro 5000 WXから数えると1年半ほどで、ある意味順当な投入タイミングともいえるが、Ryzen 7000シリーズの発表からだと1年2カ月、EPYC 9004シリーズの発表からでも11カ月が経過しており、もう少し早くても良かったのでは?と思わなくもない。
ラインナップとしては12コアの7945WXから96コアの7995WXまでトータル6製品。TDPそのものは280Wから350Wに引き上げられたが、その分動作周波数も全体的に高めに設定されている(Photo01)。5000 WXシリーズと比較した場合、Zen 3→Zen 4でIPCが向上し、動作周波数も引き上げられ、かつ最大96コアとコア数も増えている結果として、アプリケーション性能も当然相応に向上するとしている(Photo02)。そして主要な競合といえばXeon Wシリーズになる訳であるが(Photo03)、性能比較がこちら(Photo04~07)。複数SKUでのトータルでの比較がこちら(Photo08)だが、正直判り難い気がする。
-

Photo01: EPYC 9004シリーズのSKUと比較しても、全体的にBase/Boost共に動作周波数が高めに設定されている。
-

Photo03: 思うにXeon W 1400/3400の発表時にあわせて発表していれば圧倒的だったろうに、と思わなくもないのだが。
-

Photo04: Software and science。Softwareは判らなくも無いがscienceは関係ないだろうという気もする。あとChromiumだが、5000シリーズの比較の際のChromium 86.0.4199.0と今回利用したChromium 115.0.5740では構造が大きく変わり、コンパイルに猛烈に時間が掛かる様になったとの事で、数字は間違いではないとしている。
-

Photo05: Media and entertainment。EncoderやRenderingである。Encoderで性能差が少ないのはなんとなくわかるが、コア数が効くRenderingでの性能差が極端である。
-

Photo06: Design and manufacturing。こちらも最終的にはレンダリングである。PTC CreoとSolidworksはSPECapcを利用しての結果との事。こちらは32core vs 36coreの比較である。
-

Photo07: Architecture, engineering and construction。基本はCAD系のベンチマークだが、一部Rendererも入る。ここも32core vs 36core。
ちょっと話を戻すと、Ryzen Threadripper Pro 7000 WXシリーズの構成がこちら(Photo09)。プロセッサ側はEPYC 9004と同じく最大12個のZen 4 CCDにIoDが組み合わされる構成(Photo10)である。ただしメモリは8chに減じられ、また1 DIMM/ch構成のみがサポートされることになった。その代わり速度は5200MT/secまで引き上げられている。ちなみにメモリ容量は8chで最大2TBであるが、これはあくまでもRyzen Threadripper Pro 7000 WX側の仕様であって、これを実現するためには256GB DIMMが必要になる。これをOEMメーカーがサポートするかどうかはまた別の話であり、なので最大1TBという構成の製品もありえるとの事だった。
余談になるが、ある種のアプリケーションではコア数が大きく性能に効いてくる。レンダリングなんかがその代表例で、Photo05のChaos V-Rayなんかは最右翼だろう。こうした用途向けではZen 4コアよりZen 4cコアの方が向いているのでは? と思ったのだが、David McAfee氏(CVP&GM, Client Channel Business)曰く「Zen 4cは確かにCore Densityは高いが、動作周波数は低く抑えられており、Overclockingには向いていない」との事。例えばCG StudioにおいてRendering用のBackendには向いているが、そうした用途にはBergamoベースのEPYC 8004ベースのサーバーの形で入り始めている。Threadripper Proは、デザイナーのWorkstationで使われる用途で、ここはむしろThreadあたりの性能を高める方が重要」との返事であった。また3D V-Cacheについても搭載するSKUは予定していないとの事。
話をメモリに戻すと、これもEPYC由来であるがRyzen Threadripper 7000 WXはNPS(Nodes Per Socket)を1/2/4の構成にすることが可能だが、デフォルトではNPS1が利用されるという話であった(Photo11)。
-

Photo11: EPYCではVirtual Machine同士を物理的に異なる環境で稼働させるためにNPSを分離するといった利用のされ方がしばしばあるが、Workstation用途でVirtual Machineやらコンテナやらを、しかもそれぞれ物理的に隔絶するニーズは相当少ないと思われる。
さて、これと一緒に発表されたのがRyzen Threadripper 7000 HEDT(High-End Desktop)である(Photo12)。Socket形状はRyzen Threadripper Pro 7000 WXと一緒(Socket sTR5)であるが、チップセットはTRX50に切り替わる。メモリは4chになり、PCI Expressは最大88レーンに減るが、それでもDesktop向けとしてはかなり重厚である。何しろ現行のX570ですら最大36レーン(しかもこちらの記事で以前説明したように、B650をディジーチェーン接続するという力業である)でしかないから、軽く倍である。ただWRX90がCPUから128レーンのPCIe Gen5、Chipsetから16レーンのPCIe Gen4が出るのに対し、TRX50ではCPUからは48レーンのPCIe Gen5、Chipsetから40レーンのPCIe Gen4が出る構造になっている(Photo13)。他にAMD Proの機能も当然無効化されているのは良いとして、ちょっと残念なのがUnbuffered DIMMのサポートが無い事。これは恐らくIoDがUnbuffered DIMMに対応していないためだろう。速度そのものはDDR5-5200までサポートしている。
-

Photo13: なんとなくこのChipsetから40レーン、という数字に不穏なものを感じなくもない。またディジーチェーン方式でなければいいのだが。というか、まさかと思うが今度は2つのチップセットがそれぞれCPUにx4で繋がる構造だったらどうしよう?
このRyzen Threadripper 7000 HEDTであるが、まずは24/32/64coreの3製品がラインナップされる(Photo14)。「まずは」と書くのは、こんなスライド(Photo15)も公開されているからで、性能としてはRyzen Threadripper Pro 5995WX比(Photo16)及びXeon W9-3495X比(Photo17)のものが示されているが、どう見てもHEDTというよりもWorkstation向けである。
問題はこのRyzen Threadripper 7000 HEDTのターゲットである。何人かのAMDのスタッフに質問を投げたのだが、Enthusiast Userといえばそうながら、例えばGamingであればRyzen 9 7950X3DとかRyzen 7 7800X3Dの方が遥かに適しており、Ryzen Threadripper 7000 HEDTを選ぶ理由には乏しい。比較的理解できる回答としては、「Socket AM5を超える拡張性が欲しいユーザー向け」という話で、これはまぁ理解できる。ちなみに別のスタッフには「AMDの熱狂的ファン向けだ」と返事を貰ったので「俺はGen 2 Threadripperに2枚のGPU刺して7枚のモニターを繋ぎ、RAID 1を4組ぶら下げてるけど、熱狂的なファンじゃねーぞ?」と返したら「それは既に熱狂的ファンだ」と返されてしまった。解せない。
さてRyzen Threadripper Pro 7000 WXとRyzen Threadripper 7000はどちらも11月21日に発売開始となっている。World Wide PartnetとしてはDell/HPE/Lenovo/Supermicroの4社の名前が挙がっており(Photo18)、一方Ryzen Threadripper 7000対応のTRX50マザーボードの方は複数(説明ではASUS、MSI、ASRockの名前が挙がっていた)のベンダーから製品がリリースされる予定との事だ。Dell(Photo19)及びHPE(Photo20)については製品のPreviewも紹介された。
ところでRyzen Threadripper Pro 7000 WXシリーズとあわせてRadeon Pro W7000シリーズの説明も行われており、概ね既に公開された情報で目新しい話は無いのだが、一つだけこのスライドが目を引く(Photo21)。これは先日発売されたNavi 32ベースのRadeon RX 7700XT/Radeon RX 7800 XTのRadeon Pro版ということになる。まぁこれは驚く様な話では無く、既定路線ではあるが、このRadeon Pro W7700がRadeon RX 7700XTとRadeon RX 7800 XTのどちらに寄せてあるのかは興味あるところだ。