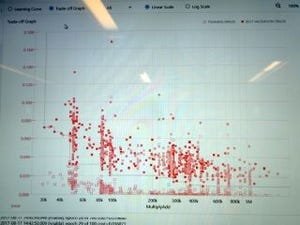1999年5月に発表されたソニーの犬型ロボット「AIBO」。当時小学生の筆者は、25万円という価格をよく理解せず、「これ欲しい」と親にねだった覚えがある。ついぞ買ってもらえることはなかった。
そして11月1日に「AIBOらしき何か」を発表すると示唆した動画「New story with…」が、ソニーのYouTubeチャンネルに公開された。
AIBOの再生は、ソニー 代表執行役 社長 兼 CEOの平井一夫氏が2016年6月の経営方針説明会でロボット事業への再参入を示唆したことから一気に現実のものになった。ではなぜソニーがロボットを今、改めて作る必要があるのか。
社内に残ったAIBOの遺産
ソニーは世間的に知られるAIBOのみならず、二足歩行の人型ロボット「QRIO」、ロボットとはやや異なるが「踊る音楽プレイヤー」として一部で話題となった「Rolly」といったさまざまな製品を世に送り出してきた。もちろん、いずれの商品も家庭内のロボットのデファクトスタンダードとなれたわけではなく、むしろ過去の遺物、失敗作、ソニーの凋落の要因として語られることも少なくなかった。
一方で、こうした知見は今も脈々と受け継がれている。例えば、先日発表されたソニーモバイルコミュニケーションズのコミュニケーションロボット「Xperia Hello!」においても同社 スマートプロダクト部門 エージェント企画開発室 室長の倉田 宜典氏が「技術はエンジニアが脈々と受け継いでいた」と発言している。
また、現在は別会社となったVAIOの長野・安曇野工場は、もともとAIBOの生産拠点。同社は現在、EMS事業(受託製造)でロボティクスを手がけており、トヨタの小型ロボット「KIROBO mini」などを生産している。この2社が今、ロボット事業を本格化させるのは過去の挑戦からの思いつきではなく、自社内に秘めていた技術を活かすという側面もあることが伺える。
AI技術の進化、米大手の独壇場
一方で、10年前と大きく変わるのはむしろ、ロボットに対する今の消費者の考え方、そしてソフトウェア面の進化だろう。
Google AssistantやAppleのSiri、AmazonのAlexa、MicrosoftのCortana、LINEのClovaなど、いわゆる音声アシスタントの登場で人々は「自分が質問・お願いしたことをこなしてくれる執事」に対する期待度が高まっている。もちろん、これらのサービスもまだまだ開発途上にあり、実用性に欠ける部分もある。
しかし、例えばAmazonのAlexaは「スキル」と呼ばれる製品・サービスの連携機能を持っており、10月26日時点で2万件のスキルが用意されている。このスキルは、さまざまな企業・開発者が自由にスマートスピーカー「Amazon Echo」との連携機能を開発できるため、AndroidやiOSのような一大プラットフォームとなりつつある。
Amazon Alexaは年内に日本語対応する予定とアナウンスされているが、一方でこの10月からスマートスピーカーを先行投入しているのがLINE Clovaを搭載した「Clova WAVE」とGoogleの「Google Home / Home mini」だ。筆者はGoogle Homeを利用しているが、音楽・ラジオの再生や玄関の電源ON/OFF、ちょっとした雑学の収集など、声による操作は確実に新しい価値を生み、将来的には消費者に広く支持されるだろうと感じる。
特にAmazonとMicrosoft、Googleはエンタープライズクラウドの分野でAWS、Azure、GCPがしのぎを削る。3社はそれぞれ音声アシスタントのベースとなる自然言語処理や音声認識技術、音声合成技術などを企業向けにAPIとして提供している。これらは、ディープラーニングによって飛躍的に進化を見せており、画像認識や音声認識は一部で人間を超えたとも言われている。こうした技術力を背景にAIが日々アップデートされる環境になると、その他のプレイヤーは為す術がない。