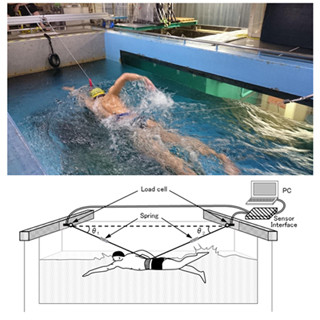東北大学電気通信研究所の栗木一郎准教授らの研究グループは2日、日本人に共通する19色名の存在を確認し、30年前の同様の研究と比較したところ、明確な増加が認められた。このことから、日本語における色概念の表現の進化が今なお続いていることが明らかになった。
今回の研究では、「青々とした緑」のような平安以前から継承されている表現に着目し、日本語表現において青と緑の区別がついていることを統計学的に立証するとともに、この日本語独特の言葉遣いの経緯についても解明した。同研究成果は東北大学、東京工業大学・オハイオ州立大学などの研究者による共同研究であり、視覚科学研究分野の学術誌「Journal of Vision」に掲載された。

|
今回の実験に使用されたカラーサンプル(有彩色320色+無彩色10色)。下段は今回の研究で抽出された日本語の色カテゴリー。緑と青の間に見られる水色の領域が、30年前の研究と異なり、98%の実験参加者が青/緑と明確に区別して「水(色)」と呼んだ色カテゴリー |
人間の視覚は100万もの微細な色の違いを見分ける事ができると言われているが、日常的に言葉として使われる色名は「赤」「緑」「青」「黄」など少数に限られる。今回の研究では、人間の最も基本的な視覚情報である色の情報がどのように脳内で形成され、個人差や言語差の影響を受けているかという様子について、計算的・統計的手法を用いて可視化できることが示された。
同研究では、日本語を母国語とする実験参加者57名が、日常的に色カテゴリー(赤、緑、青、黄、など)を呼ぶ色名の数について調べた。参加者に320の有彩色の色見本(+10色の無彩色=白、灰、黒)を1つずつ見せ、修飾語や複合語を用いない色名呼称を行った。つまり、「黄緑」や「薄紫」といった表現を除外した単一語の色名呼称をカウントしたことになる。
「水色」は新しい表現
k-平均クラスタリングという統計を用いた解析の結果、日本語話者に共通する19の色カテゴリーの存在を確認した。内訳としては、多くの近代的文化圏で用いられる11の基本色カテゴリー(赤、緑、青、黄、紫、ピンク、茶、オレンジ、白、灰、黒)に、8つの色カテゴリー(水(色)、肌(色)、抹茶、黄土、えんじ、山吹、クリーム)が加わったものとなった。
中でも、「水(色)」は98%の実験参加者が使用し、日本語の基本色カテゴリーの12番目の色名の強力な候補になりうると考えられる。30年前に実施された先行研究(Uchikawa & Boynton, 1987)では「水(色)」は基本色に含まれないと結論された。また、先行研究では「草(色)」が黄緑を指して頻繁に使われる色名として報告されたが、同研究では「抹茶」という回答が黄緑を指す代表的な色名として置き換えられたことが判明した。これらの結果は、言語における他の特徴と同様に、色名の語彙が時間とともに変化する様子を表している。
青と緑が分離して使われる経緯
一方で長く変化していない要素もあり、その1つが「青」と「緑」の混用だ。今回の共同研究では、平安以前の日本の和歌における青と緑の用法についても調査した。その結果、「あお」(正しくは「あを」)は明らかに青いものにも緑の物にも用いられ、「みどり」も同様であった。
現在でも、日本語では信号機や若葉、野菜などを指して「青」と呼ぶことはあるが、これ以外の場合では青と緑は明らかに区別して使われる。青と緑が混合した1つのカテゴリーから別々のカテゴリーに分離する過程は、世界中の言語が発達の途上で必ず経過するポイントと考えられている。
これらの結果から、今回の共同研究は、現代日本語の青と緑が異なる色カテゴリーであると示しただけでなく、青と緑にまたがる明度の高い領域に「水(色)」のカテゴリーが過去30年で加わったことを示した。
なお、同大学は、この研究成果が人と人あるいは人とAIの間において、より質の高い意思疎通を可能とする情報通信技術の実現に示唆を与えるものと期待できるとしている。