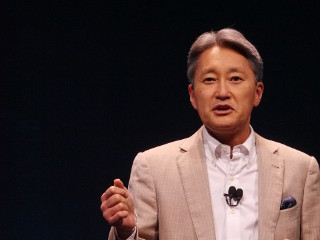テスラは年間50万台のEV生産を目指しているが、この生産台数を実現するには、現在、全世界で生産しているすべてのリチウムイオン電池を使ってしまうことになるという。ギガファクトリーは、こうしたテスラの旺盛な需要に対応できる生産規模を目指して建設されたもので、2018年には年間35GWhの電池を生産。年間50万台のEVを生産できるようになるという。テスラによると、これは、2013年に全世界で生産されたバッテリーの合計数を上まわる規模だという。
ちなみに、ギガファクトリーの敷地総面積は12平方km。敷地面積に「km」という単位がつくのは異例であり、その規模が壮大であることがわかる。敷地面積はフットボール場換算でおよそ107個分。「米テスラモーターズのイーロン・マスク会長兼CEOは、「経済学的な面から限界ともいえる規模を持つ工場。どんな種類の工場においても最大のものであり、建物としても最大。ハムスター500億匹入る大きな土地になる」と語る。ハムスター500億匹と言われても、まったく想像がつかないが、いずれにしろ、その規模はこれまでの工場の概念を大きく上回るものだ。
パナソニックの津賀社長は、「パナソニックは、ラインごとに順次設備投資をしていく予定であり、1つのラインが稼働すれば回収が始まる。設備償却は5年。1ラインごとで稼動率が上がれば、順調に投資回収ができる」とする。だが、河井代表取締役専務は、第3四半期決算会見の席上、「二次電池は、売り上げが相当伸びているが、ギガファクトリーの立ち上げ費用などの先行投資があり赤字である」と語る。
第3四半期において、二次電池事業は、売上高が前年同期比131億円増の1002億円となったが、調整後営業損益は18億円減の24億円の赤字、事業部損益は83億円増となったものの49億円の赤字と、赤字からは抜け出せていない。
河井代表取締役専務は、「具体的な需要が見えているので、できるだけ前倒しで進めている。北米の自動車関連事業の発展はかなり見込めると考えている。テスラとの事業そのものは赤字ではなく、さらに、2017年度は投資が圧縮でき、ボリュームが出てくる。今後は、利益に貢献できると考えている。二次電池を取り巻く環境は悪くはない」と、これからの成長に期待をかける。
ギガファクトリーへの投資は、かつてのプラズマディスプレイパネルを思い出させる大型投資とはいえるが、津賀社長は、「目的を明確にした電池が、ギガファクトリーの電池。単に汎用的な乾電池を量産しているわけではなく、テスラのクルマを量産するためのバッテリーを作る工場への投資である」と、その性質がまったく異なることを強調する。
言い方を変えれば、テスラと一心同体の大型投資にかけたともいえるが、この先行投資の成果は、EV時代の本格到来とともに、優位に働く可能性は高い。パナソニックは、EV時代に向けた勝負に出たわけで、その第一歩が本格的に踏み出された段階にあるともいえる。 津賀社長は、社長就任以降、パナソニックのBtoBシフトを打ち出してきた。そのパナソニックの成長に向けた「選択と集中」の取り組みは、BtoBを軸に、今後、より明確になっていきそうだ。