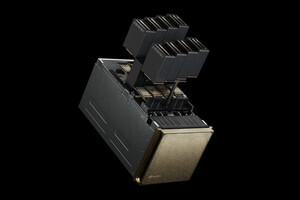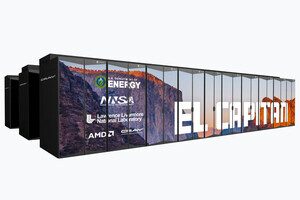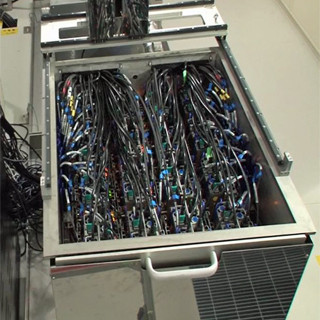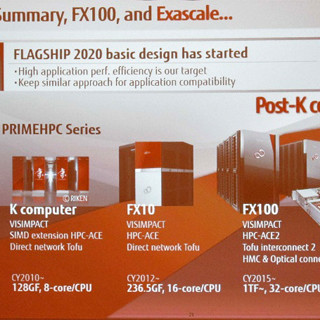3番目の発表は仁科加速器センターの大木洋氏の「物質優勢宇宙の謎解明のための核子構造精密計算」というものである。
何故、宇宙は物質だけで構成され、反物質が無いのかは大きな謎で、それを説明したのが小林・益川理論でノーベル賞を受賞した。しかし、この理論のメカニズムだけでは破れの大きさが足りず、破れを惹き起こす未知の現象を見つけるというさまざまな研究が行われている。これらの研究の結果を解釈するためには、QCDに基づく理論計算が重要であるという。同発表では、HOKUSAIスパコンを用いた格子化された時空のQCDのモンテカルロシミュレーションの研究を紹介し、また大木氏らが進めているCP対称性を破る核子形状因子研究の現状と、今後の展望について発表するというものである。
4番目の発表は、Kim表面界面科学研究室の三輪邦之氏の「表面吸着分子系の物性解析」と題する発表である。
固体表面と分子の間に働く相互作用やこれらの間の電荷・エネルギーの移動を調べることは、基礎科学的観点だけでなく、分子デバイスや不均一触媒の新規材料開発といった応用の観点からも重要である。Kim研究室では、走査トンネル顕微鏡を用いて固体表面に吸着した単一分子や分子膜の構造および電子状態を、サブナノメートルの高い空間分解能で調べている。これらナノ領域の表面系の原子構造や電子状態を理論的に調べる上では、量子力学の枠内で電子や原子核の微視的な振る舞いを解析することが肝要となる。この発表では、密度汎関数理論に基づく第一原理計算を用いて、表面吸着分子系の構造特性や電子特性を調べた結果を発表する。また、分子の光学特性や磁性、表面での電子・原子ダイナミクスの解明に向けた研究の展望について発表するというものである。
5番目の発表は、創発物性科学研究センターの白川知功氏の「物性物理における量子多体系計算手法とその応用」と題する発表である。
物質の量子状態の計算には色々な方法が考案されているが、運動項と作用項の両方を精度よく計算することは難しい。そこで白川氏らは、それぞれの計算手法を専門とする研究者を集め、1つの計算手法では不十分な点を補い合うことで、より統一的な理解を深めることを目指している。同発表では、こうした強相関量子多体系に対する計算手法の実際の応用例として、これまでのHOKUSAI利用課題を通して行ってきた白川氏らの研究について紹介された。特に、変分モンテカルロ法とクラスター埋め込み法を用いたイリジウム酸化物の研究、密度行列繰り込み群法の磁性不純物模型への適用方法と、それを用いたグラフェンにおける磁性不純物効果の研究などについて報告するというものである。