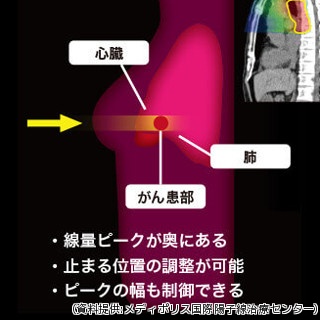超高齢社会に適応したローコスト手術の実現
1966年に公開された、アメリカのSF映画『ミクロの決死圏』はその後50年経った現在でもなお、名作の誉れが高い。映画では、脳に障害を起した要人を救うべく、ミクロサイズに縮小された科学者たちのグループが特殊潜航艇に乗り込み、頸動脈からの血液の流れに乗って脳に到達、治療を行う。
あくまで架空の話ではあるが、遠い未来にそんな医療が実現する可能性を否定することはできない。このロボサージャン手術もまた、発想の端緒は映画だったのだ。木原教授は、ソニーの3D映画の観賞用のヘッドマウントディスプレイの話を聞いたときに、構想していたロボサージャン手術への応用がひらめいて、共同開発を始めたという。
「映画で実現している3D画像のクオリティを、手術現場のひとりひとりに導入することができれば手術の進歩に役立つ、と思ったのです。イメージはロボコップ(1987年公開のアメリカ映画でサイボーグの警官が活躍する)、それが転じてロボサージャンになりました」(木原教授)
木原教授が、ロボサージャン手術の開発・洗練に尽力しているのには、訳がある。外科医としてずっと一線に立ち、今年3月まで東京医科歯科大学医学部附属病院の病院長を務めた立場から、「超高齢社会の到来」を肌で感じていたのだ。
日本の医療費は昨年、ついに40兆円を突破。最高額の更新は12年連続で、そのうちの3分の1が75歳以上の高齢者の医療費に当たる。高齢者人口の増加によって医療費が増えるのは致し方のない面はあるものの、このまま増え続ければ国の財政や健康保険のシステムに多大な影響を及ぼすことが各方面で指摘されている。
また、高齢化以上に影響を及ぼすのは、医療の高額化であるともいわれている。
「腹腔鏡手術、さらにダヴィンチ手術へと進むにつれて、高価な使い捨て器具が多くなり、手術コストは著しく上昇しました。またダヴィンチは大型の精密機器であるため、1台の購入費が数億円ほどかかり、年間の維持費も相当なものです。それらが結果的に、医療費の高騰に跳ね返るともいえます。日本は世界がうらやむ、国民皆保険という素晴らしいシステムに守られています。このシステムを破たんさせず、次世代に残していくためにも、"ハイクオリティ"で"ローコスト"の"みんなが受けられる医療"を目指したい。そのために、ダヴィンチほどコストがかからず、同等以上のクオリティを生み出す国産のロボット型手術を開発、推進しなければと思いました」と、木原教授は説明する。
20年近い年月をかけて、コイン創手術さらにロボサージャン手術へと進んできたが、ロボサージャン手術の要であるヘッドマウントディスプレイは2013年、医療機器として市販されるようになった。それに先立つこと数年前の2008年に「腹腔鏡下小切開手術」の名称でロボサージャン手術につながる手術が保健適用になったのも、新規保険収載の難しさからすると画期的なことだった。
対象となる疾患は、当初は前立腺がん、腎がん、腎盂・尿管がん、膀胱がん、副腎腫瘍などの泌尿器科系疾患だったが、東京医科歯科大学では、脳外科、脊椎脊髄外科、消化器外科などにも対象領域が広がっている。2015年には、アメリカのFDA(アメリカ食品医薬品局)でもヘッドマウントディスプレイの認可が降りるなど、欧米でもその実力が認められている。
「その昔、音楽は自宅かコンサートホールで聴くものだったでしょう。固定された音楽環境を変えたのが、音楽を外に持ち出したソニーのウォークマン。いまや誰もが、いつでもどこでも好きな時に好きな音楽を聴ける時代になりました。ロボサージャン手術もそれと似ていて、大型で固定された機器ではなく、小型でウェアラブルな性能の良い機器を使うことで、より多くの場所でより多くの患者さんに、患者さんにとっても術者にとっても"安全で快適な"手術を提供することが可能になると考えています」(木原教授)
術者のロボット化は、進んでいる。さらにこの先、木原教授には大きな夢がある。ロボサージャン手術を近い将来、人とAI(人工知能)がコラボレーションする手術にできれば、というものだ。まさに、「鉄腕アトムの世界」である。社会の願いである手術事故の完全防止へのアプローチである。
患者に寄り添った、誰もが受けられるハイクオリティの手術を――そんな情熱が、想像力と技術力の画期的な融合をもたらし、日本の医療の未来を拓いている。