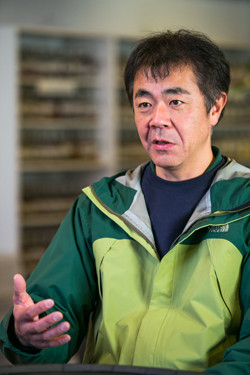「実はかつて一度、地ウイスキーブームはあったんですよ」と、ベンチャーウイスキー創業者で社長の肥土伊知郎(あくと・いちろう)さんは語る。「ただ、当時のブームは、大手さんのウイスキーよりも安く飲めるから、というのが理由でした。“一升瓶ウイスキー”なんて言葉もあったくらいなんです」
たしかに1980年代中頃、(当時私は高校生だったが)「マルス」や「チェリー」といったウイスキーの名前を聞いたことがあったのを思い出した。あれは、地ウイスキーだったのか……。
肥土さんの実家は、江戸時代の初め、寛永の頃から秩父で代々続いてきた酒造所である。1941(昭和16)年、同じ埼玉県の羽生に新たな本社工場を建て、日本酒以外に焼酎やワイン、リキュールなども造った。戦後すぐの1946(昭和21)年にはウイスキーづくりも始めている。
ウイスキー不遇の時代を乗り切る
さらに時が流れた1980年代には本格的なポットスチルを導入。スコットランド式のウイスキーづくりを続けたが、日本酒の設備投資の失敗や景気の影響もあり、肥土さんの父の代で傾いた。当時サントリーで働いていた肥土さんが実家に戻ってきたものの、結局、家業の造り酒屋は手放さなければならなくなった。
残ったのが、羽生の蒸溜所で造っていたウイスキーの原酒である。2000年代、ウイスキーは売れない時代だった。営業譲渡先の新しいオーナーも、大手でさえも、ウイスキーの引き取りには二の足を踏んだ。そのまま引き取り手がいなければ、貴重な原酒を廃棄しなければならない。肥土さんは必死になって探した。
とうとう見つけたのが、福島県郡山の笹の川酒造。同社は1980年代の“地ウイスキーブーム”のとき、「チェリーウイスキー」をヒットさせた酒造所である。同社の山口社長は「(原酒を)捨ててしまうのは業界の損失。時間というものは取り戻せないのだから」と羽生の原酒を預かり、その原酒を使って、肥土さんの企画によるシングルモルトウイスキー「イチローズモルト」が発売された。