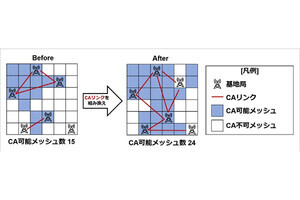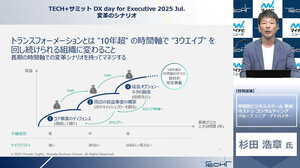日本大学芸術学部、通称「日藝(ニチゲイ)」の学生たちによるアートとメタバースの融合プロジェクト「はちゃメタ byニチゲイ」。2024年4月5日から18日にかけて、同プロジェクトの展示会「日藝生による江古田メタバース・イノベーション」が日本大学芸術学部江古田校舎A&Dギャラリーで開催された。
同展示会にはPCが複数台設置されており、学生たちが作り上げたメタバースの江古田を実際に体験できる。そのほか、アイデアイメージや資料、ポスターなどさまざまな展示物が公開され、来場者の注目を集めていた。
今回はメタバースの体験を中心にレポートするとともに、メタバースの制作に携わった学生たちの言葉を通して「はちゃメタ byニチゲイ」の意義をあらためて探っていく。
学生が作り上げた「メタバースの江古田」が日藝校舎で展示
東京・江古田の町にキャンパスを構えており、デザインや写真、文芸、音楽など芸術に関する8つの学科を有する日本大学芸術学部。そんな同校で前代未聞のプロジェクト「はちゃメタ byニチゲイ」がスタートしたのは、2023年12月のことだった。江古田の町の魅力を学生の視点で再発見し、それをメタバース上で構成するプロジェクトだ。
また、日本電子計算株式会社や株式会社Urth、株式会社NRC一級建築事務所、株式会社クニエといった企業が参画し、日本大学芸術学部の講師らと共に日藝生の活動をサポートした。「はちゃメタ byニチゲイ」はあくまでも校外プロジェクトという位置づけのため、参加した学生も特定のコースや学年に留まらない。それが化学反応となり、誰も予想できなかったユニークな作品ができ上がった。
同プロジェクトのポイントとなるのは、「江古田の町をそのまま再現する」のではなく、「学生たちの視点で再構成する」という点。そうして完成したメタバース空間の江古田は、たしかに現実の江古田の町並みをベースにしながらも、どこか現実とは違った要素が見え隠れしていた。
たとえば江古田駅だ。現実世界での江古田駅は西武池袋線の停車駅である。一方で、西武池袋線は地上を東西に向かって走るため、別の見方をすれば線路が江古田の町を南北に分断しているともいえる。この課題をどうにかして解決できないか。学生たちが知恵を絞った結果生まれたのが、「西武池袋線をモノレールにする」というアイデアだった。
「モノレールにすれば線路を高架化できるため、その下を人々が行き交えるようになり、町の分断が避けられます。線路を単に高架化したり、地下鉄化するアイデアも出ましたが、それだと面白くないねということでモノレールにしました」(高橋さん)
展示会場では、学生たちがプロジェクト中に作成した江古田の全体図や江古田駅の構造図、さらに線路をモノレール化したイメージイラストなども展示。モノレールが走り、その下に商店街が広がる光景は、現実と空想をミックスしたような不思議な雰囲気に満ちている。
「私は大学院生なので江古田には長く通っているのですが、モノレールのアイデアを聞いたときは、その発想があったか! と驚きました」(福田さん)
実際にメタバース空間に入り、モノレールになった江古田駅を眺めてみると、「もしかすると、こういう江古田もありえるのかもしれない」と思わされる絶妙なリアリティが感じられた。
「現実にはできないことができる」メタバースならではの表現
モノレールもそうだが、「現実にはできないことができる」のがメタバースの魅力だ。今回の作品でいえば、グラフィティアートもその一つだろう。メタバース内の北口商店街のシャッターにはところ狭しとグラフィティアートが施され、見慣れているはずの光景に違和感が付与されている。実はプロジェクト初期には、江古田の町をディストピアにするというアイデアがあったそうだが、その名残として採用されたのがグラフィティアートだったという。制作を担当した中田さんは、「メタバースに触れたのが初めてだったので、どんなプロセスでグラフィティを作ればいいかわからず大変でした」と当時を振り返った。
他に注目したいのが、日本大学芸術学部の校舎。普段から通っている場所ということで学生たちの思い入れも強く、ユニークなアイデアが数多く詰め込まれてリデザインされていた。
「日藝には8つの学科があり、よく使う校舎が異なるんです。そこで、各学科をイメージして校舎をデザインし直しました」(平井さん)
たとえば音楽学科が使用する音楽実習棟は音符や楽器をモチーフにしたデザインが、文芸学科や美術学科が使用する西棟は絵画や書籍をモチーフにしたデザインが採用されている。モチーフを過不足なく盛り込みながら、建物をデザインするのは大変な作業だったと平井さんは語る。
「校舎をリデザインしたことで結構奇抜な空間になったのですが、実際にメタバース内を歩いてみると町全体もグラフィティアートのおかげで色彩豊かになっていて、結果として統一感が出たんじゃないかなと思います」(平井さん)
産官学の連携で地域振興につなげていく
メタバース空間に江古田を再構築することで、江古田の魅力を再定義した「はちゃメタ byニチゲイ」。今回はデザイン学科の学生のみが参加したが、「次にやるなら他の学科も巻き込みたい」と木村さんは言う。
「他の学科の学生に今回の話をすると、参加したいという人がけっこう多いんです。せっかく日藝にはたくさんの学科があるので、いろいろな人が参加することで違う視点も入って面白いものが作れると思います」(木村さん)
また、本プロジェクトをサポートした日本電子計算の戸田氏は、「このプロジェクトや展示を日藝新入生へのガイダンスに使ってもらえたり、見てくれた人がSNSで共有してくれたり、企業のメタバース交流コミュニティで発表して好評を得たりと、各方面で反響がありました」と手応えについて語る。
「今回は産学で連携してプロジェクトを実施したわけですが、やはり産官学の連携が理想です。今後は自治体や地域の鉄道会社、航空会社などともコラボレーションして、町への興味や定住人口の増加などといった地域振興に結びつけていけたら理想的だと思っています」(戸田氏)
江古田の町と日藝の学生、そしてメタバース。3つの異なる要素がかけ合わさって、予想を超えた成果が得られた「はちゃメタ byニチゲイ」プロジェクト。今後は事業化も見据えて取り組んでいきたいと戸田氏は言う。メタバースが見せた新たな可能性がどのような形で紡がれていくのか。引き続き注目していきたい。
関連リンク
-
日本大学芸術学部
芸術総合学部としての特徴と伝統を保持するとともに、21世紀における芸術の持つ社会的先導性にかんがみ、学科の各々の専門教育をさらに充実・発展させ、同時に、学科の垣根を越えた総合的なカリキュラムを展開することで、芸術・文化全般にわたる広い視野を持った人材を養成しています。 -
株式会社クニエ
専門性の高い少数精鋭のコンサルタントが、先進的で高品質なコンサルティングを介し、変革に挑戦されるお客様のパートナーとして、解決へとリードする。QUNIE はそのような存在を目指しています。 -
日本電子計算株式会社
日本のITベンダーの先駆者として、これまで3,500社を超えるお客様のために、信頼性の高い情報システムの構築・運用を行ってきました。業界別に特化した事業部が、コンサルティングから企画・開発・導入・保守・BPOに至るまでの総合的なITサービスを、お客様のニーズに合わせて提供。メーカー系列等にこだわることなく、最適な製品/システム/サービスを提供します。
[PR]提供:日本電子計算