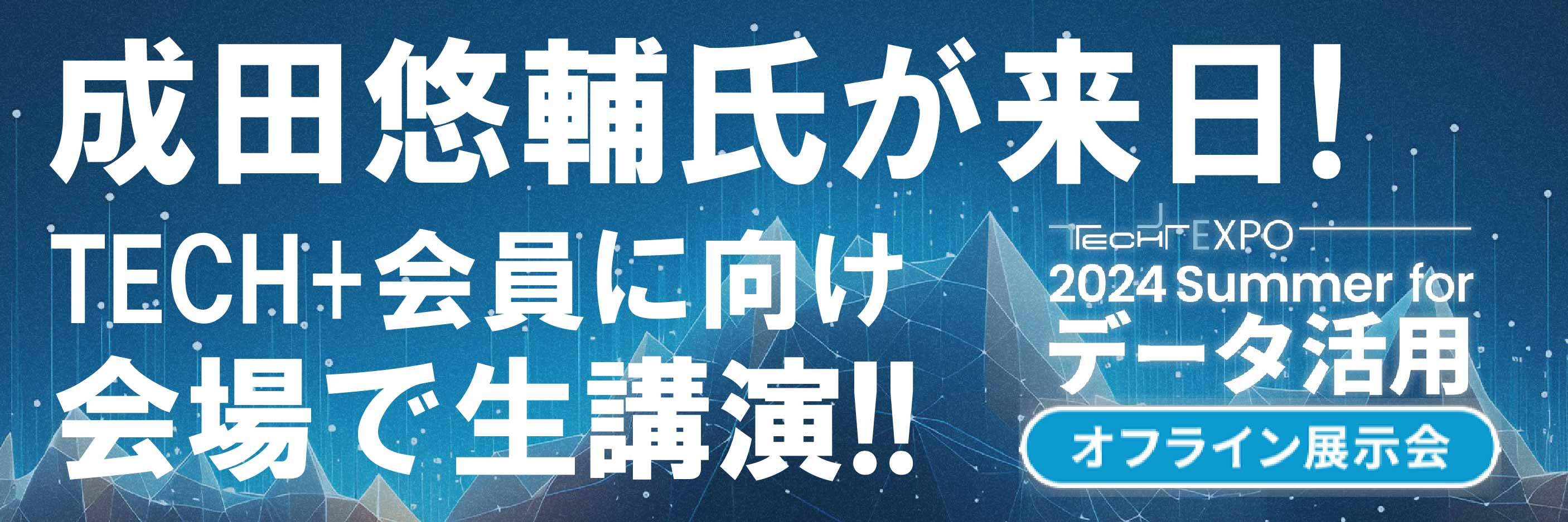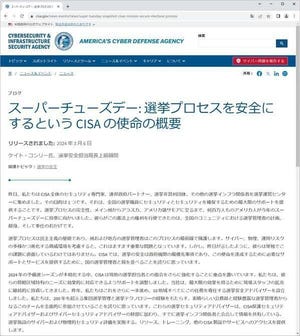現実に存在する町を自由な発想で再構築し、それをメタバース空間で表現したらどうなるのか――。
そんなプロジェクトが始動したのは2023年12月のことでした。参加したのは日本大学芸術学部、通称「日藝(にちげい)」の学生たち。「はちゃメタ byニチゲイ」と名付けられた同プロジェクトでは、日藝キャンパスの位置する東京・江古田の町をデザインし、メタバース上に構築するという試みが行われました。
完成したメタバース上の江古田は、現実の江古田をベースにしながらも学生たちの自由な発想が盛り込まれ、新たな気づきを与えてくれる興味深い作品に仕上がっています。
今回、同プロジェクトに参加した学生のうち、7名による座談会を実施。プロジェクトに参加した感想や作品に対する想い、制作の裏話を聞きました。
座談会メンバー
|
|
福田さん: |
|
伊藤さん: |
|
|
木村さん: |
|
中田(なかだ)さん: |
|
|
平井さん: |
|
高橋さん: |
|
|
桑原さん: |
なぜ江古田をメタバースで表現する「はちゃメタ byニチゲイ」に参加したのか
――まずは皆さんが今回の研究に参加しようと思った理由を教えてください。
|
|
木村さん:私が専攻しているグラフィックデザインの領域では、どうしても平面的な表現にとどまってしまいがちです。進級すると3Dについて学ぶ機会もありますが、今回のプロジェクトに携わることで今のうちからメタバースと3Dの表現にも触れられて楽しそうと思い参加しました。 |
|
|
平井さん:僕も木村さんと似た理由ですね。2年生のときにプロダクトデザインの授業を履修していたこともあって、2次元的なものを3次元的に表現するということに興味を持っていました。 |
|
|
伊藤さん:入学した頃に友だちと「もしかしたらメタバースがこれから流行るかも」みたいな話をしたことがあって、メタバースを勉強しておいたら就活を含めて将来役立つかなという下心満々で参加しました(笑)。 |
|
|
中田さん:僕はVRゴーグルを購入するくらいメタバースに興味を持っていましたが、作り方についてはなにも知りませんでした。そんなときに今回の話を聞いて、メタバースについて理解を深めるのにいい機会だと思い参加しました。それに、デジタルを使った地域振興にも興味があったので。 |
|
|
高橋さん:僕は1年間休学していたんですが、その間ずっとデザインから離れてしまうのも嫌だなと思っていました。そんなときに笠井先生から今回の研究は休学中でも参加できるというお話をいただきました。ガジェットや新しいものが好きというのも参加の決め手になりました。 |
|
|
桑原さん:もともとゲームを作りたくて、メタバースはゲームと親和性があるので興味があり、参加しました。 |
|
|
福田さん:笠井先生のゼミに所属していてお声がけいただいたのですが、最初は授業との兼ね合いで参加が難しかったため、今回の「日藝生向け特別verメタバース」展示の企画に携わることとなりました。 |
コンセプトは「江古田×日藝らしさ×違和感」
――「はちゃメタ byニチゲイ」プロジェクトのデザインコンセプトについて教えてください。|
|
中田さん:コンセプトとしては「江古田のイメージ×日藝デザイン学科らしさ」が基本軸にありました。僕らはデザイン学科の学生なので、そのコンセプトにどうすれば自分たちらしさを詰め込めるのかという視点で考えていきました。 |
|
|
平井さん:まずは江古田ってどんな町なんだろうというところから考えましたね。そのなかで、たとえば「昭和レトロ」とか「商店街の活気」といったキーワードが出てきて、それをヒントにコンセプト案をブレストしていきました。 |
|
|
伊藤さん:その過程で、江古田を世紀末感のあるディストピア世界にしようという案が出たり、コンセプトがおもしろい方向に向かったこともありましたね(笑)。 |
|
|
桑原さん:そうそう(笑)。最初は悪ノリで盛り上がることもありました。ただ、完全に荒廃させてしまったら江古田である必要もなくなってしまうので、最終的には江古田の良さを残す方向に落ち着いたんです。 |
|
|
高橋さん:戸田さんからは「商業作品ではないから自由に発想していいよ」と言っていただけたので、すごくやりやすかったです。 |
|
|
木村さん:あとは、「違和感」も大事にしましたね。リアルすぎずファンタジーに寄せることで生まれる違和感がトレンドっぽいなと思い、江古田ではあるけれど、現実にはないいろいろな要素を盛り込むことで、メタバースに入った人が違和感を持つようなデザインをあえて意識しました。 |
イメージをどこまでメタバースに落とし込むか、容量制限との戦い
――制作時の印象的なエピソードや苦労したこと、こだわったポイントなどについて教えてください。|
|
高橋さん:つくるものやデザインをあらかじめ決めてから制作するのではなく、まずやりたいようにやってみて、そこからおもしろいものを残したり、できないことは再考したりして自由度高く作り上げていきました。制作に使用したメタバース開発ソフト「V-air」はブラウザで動かせるので誰でも気軽にメタバース空間に入れますが、そのぶん容量制限があったりしてデザインを調整するのに苦労しました。メタバースに触れること自体が初めての学生も多かったですし、実際に体験することで直面する課題も多くありました。 |
|
|
桑原さん:たしかに容量制限は苦労したポイントでした。たとえば建物にしても一旦は細かい部分まで作り込んではみたものの、それだとメタバース内に置いただけでクラッシュしてしまうので、最終的にはシンプルな箱状にしました。やりたいこととできることのすり合わせが大変でしたね。 |
|
|
伊藤さん:そうですね。ただ、デザインしたものをメタバース上で3Dにしたときにどんな形になるのかを想像するのが難しいところでしたね。猫ポストも最初に作った平面デザインを3Dにしてもらったときに、もともと想像していたイメージとは少し印象が違っていてギャップを感じたんです。でも出来上がった3Dモデルを見ているうちに、こっちのデザインもかわいいなと気に入って、最終的にこれで行こうと決めました。 |
|
|
平井さん:僕は日藝の校舎のリデザインを担当したのですが、それぞれの校舎のイメージを表現するのが大変でしたね。日藝校舎は学部や学科ごとによく使う棟があるので、その要素を盛り込んだデザインにしたんです。たとえば、音楽実習棟なら音符記号を配置したり、写真学科が使う東棟ならカメラを配置したり。ただ、そうなると近い分野の学科を差別化するのが難しくて。たとえば放送学科と映画学科、デザイン学科と美術学科の違いをどう表現すればいいかは迷いました。 |
|
|
木村さん:でも、できあがってみると自然に馴染みましたよね。 |
|
|
福田さん:個人的にはギャラリー棟がストーブになっていて、その上にやかんがのっているのがすごく気になるんだけど(笑)、どんな流れでこうなったんでしたっけ。 |
|
|
平井さん:ギャラリー棟を作っているうちにだんだん形がストーブに見えてきて、いっそストーブにしたら面白いんじゃないかと思ったんです。そこに江古田のレトロさを取り入れて、ストーブでレトロといえばやかんだろうと発想しました。 |
江古田を“分断”する線路から生まれたモノレールというアイデア
――今回の研究を通して江古田の町のイメージや町に対する想いは変わりましたか。|
|
伊藤さん:制作を通して、江古田が持つレトロな魅力を再発見しました。池袋という最先端の町がすぐ近くにあるのに、少し外れるだけでこんなに親しみやすい町があることの面白さを実感しました。 |
|
|
中田さん:わかります! 親近感を覚える町ですよね。 |
|
|
高橋さん:それはたぶん、全員が共通して感じたことなんじゃないかな。 |
|
|
伊藤さん:逆に江古田の課題としては、知名度の高い日藝があるのにも関わらず急行電車が停まらないことへの不満なんかも出た覚えがあります。 |
|
|
福田さん:そうそう! 電車といえば、線路で町が分断されていることも課題として挙がりましたね。そこから、どうしたら町を分断せずに電車を通せるだろうと考えて、モノレールを作る発想に至ったのはすごく面白いと感じました。私はけっこう長く日藝に通っているのですが、その発想はなかったなと感心しました。 |
|
|
木村さん:電車が街を分断することから発想したのが、「荒廃」と「近未来」の2つのイメージで江古田エリアを区切ることです。荒廃している方にはシャッターにグラフィティアートが描きました。 |
|
|
桑原さん:実はもともと日藝と江古田の共同プロジェクトで、実際の江古田の町のあちこちに日藝生がアートを描くという取り組みがありました。それもグラフィティアートという発想のヒントになりました。 |
|
|
中田さん:グラフィティアートのデザインを担当したのですが、イメージを固めるために、実際にメタバースの江古田に入って町を歩きながら考えたりしました。場所も指定されているし、デザインしたものがきちんとはまるかどうかはやってみないとわからないこともあって。大変でしたが、結果としていい形に仕上がったと思います。 |
メタバースと現実の江古田、両方を歩くことで一つの「体験」として完成する
――今回の研究を通して学んだことや、今後やってみたいことなどを教えてください。|
|
木村さん:あらためて江古田という町について考える機会になったし、今回のプロジェクトを通してすごく創作意欲が湧いてきました。メタバースでのこうした活動は、またぜひやりたいと思いましたね。 |
|
|
桑原さん:現実との対比が面白いと思いました。メタバースの江古田を体験した後で、現実の江古田を歩いてみると、いろいろな発見や面白さがあるんですよ。一つの体験として、すごく完成されていると思いました。ぜひ機会があればメタバースと現実、両方の江古田を体験してほしいです。 |
関連リンク
-
日本大学芸術学部
芸術総合学部としての特徴と伝統を保持するとともに、21世紀における芸術の持つ社会的先導性にかんがみ、学科の各々の専門教育をさらに充実・発展させ、同時に、学科の垣根を越えた総合的なカリキュラムを展開することで、芸術・文化全般にわたる広い視野を持った人材を養成しています。 -
株式会社クニエ
専門性の高い少数精鋭のコンサルタントが、先進的で高品質なコンサルティングを介し、変革に挑戦されるお客様のパートナーとして、解決へとリードする。QUNIE はそのような存在を目指しています。 -
日本電子計算株式会社
日本のITベンダーの先駆者として、これまで3,500社を超えるお客様のために、信頼性の高い情報システムの構築・運用を行ってきました。業界別に特化した事業部が、コンサルティングから企画・開発・導入・保守・BPOに至るまでの総合的なITサービスを、お客様のニーズに合わせて提供。メーカー系列等にこだわることなく、最適な製品/システム/サービスを提供します。
[PR]提供:日本電子計算