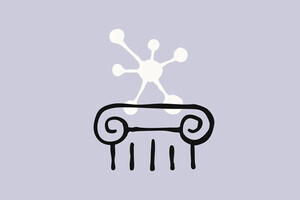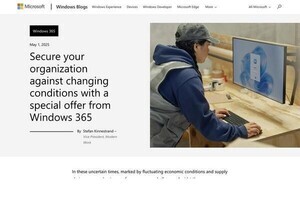YouTubeのdynabook公式チャンネルに公開された公式の紹介動画は140万回再生を超え、高評価は約3,000(2025年3月現在)。一人も取り残されることなく、同じようにパソコンを楽しんでほしい――そんな思いで開発されたアクセシビリティ向上ソフトウェア「せっていのとびら」が学校の先生や生徒から大きな反響を得、3月には総務省の「情報アクセシビリティ好事例2024」の一つとして選定された。
そんな「せっていのとびら」はどんな背景で開発され、教育現場でどのように活用されているのか。プロジェクト担当者たちにインタビューすると、「人に寄り添う、社会を支える、真のコンピューティング」というビジョンを持つDynabookの“矜持”が見えてきた。
総務省の「情報アクセシビリティ好事例2024」に選出された
「せっていのとびら」って?
Windows 11には、色の違いを認識しづらい、小さな文字が見えにくい、音声サポートが必要といった特性を持つ人に対応する「アクセシビリティ」という機能が用意されている。しかし、階層が深く見つけにくかったり、そもそも機能自体を知らないという人が多いのが課題だ。それを解決すべくDynabookが開発したのが「せっていのとびら」。Windows 11のアクセシビリティへのアクセスを容易にするソフトウェアだが、直感的でわかりやすい文字やアイコンで構成されており、障がい特性を持っている人だけでなく、自然にその便利さに気づかせる作りとなっているのが大きな特徴だ。
この取り組みは、情報アクセシビリティに優れたICT機器・サービスに与えられる総務省の「情報アクセシビリティ好事例2024」に選出された。学校教員へのインタビューや子ども目線で現場調査を行い、潜在的なニーズを掘り起こしている点、開発する製品をすべての人が使えるようにと意識した取組がなされている点などが評価された。特に1人だけが特別ではなく、誰もが自分に合わせて設定できるという点については、「すべての人がアクセシビリティという考えに触れる扉を開いている」と製品の価値が認められ、「GIGAスクール構想をさらに学校現場に定着・浸透させていく可能性を押し広げる、前例のない取り組みモデルを提供している。デジタル教科書との連動についても課題はあるが、希望を抱かせてくれる取組である」とコメントが寄せられている。
実際にYouTubeの解説動画がたくさん視聴されていることからも、多くの人が興味を持ち、使い方を確認しようとしているのが分かる。
「せっていのとびら」開発者インタビュー
情報アクセシビリティに配慮したアプリとして高い評価を得ている「せっていのとびら」だが、その開発がスタートしたきっかけとは。そして、開発する中でこだわったポイントとは。マイナビニュースでは、商品企画、デザイン、設計に関わったプロジェクトメンバーに詳しい話を聞いた。
(画像右)設計統括部 コンピューティング設計第一部 第二担当 主査 安藤秀哲氏
(画像中央)経営企画部ブランド・デザイン 事務主任 東谷俊哉氏
(画像左)国内マーケティング本部 副本部長 貞末文子氏
教育現場へのヒアリングで知った“子どもの悩み”をなんとしてでも解決したい
--------まずは皆さんが「せっていのとびら」にどのように関わったのか、自己紹介を兼ねて簡単に教えてください。
安藤氏:設計統括部の安藤です。私は商品企画から上がってきたコンセプトをどうすれば実現できるか考え、ぶれてはいけない部分をしっかり守って作るポジションでした。開発チームと、色や形が日本人の感覚と異なる部分を調整したりといった作業を担当しました。
東谷氏:経営企画部でブランド・デザインを担当している東谷です。安藤からのバトンを受け継ぎ、ユーザーが使いやすいデザインに落とし込んでいくのが私の役割でした。
貞末氏:国内マーケティングを担当している貞末です。子ども達がどのようにPCを使って学んでいるのかを探り、課題を見つけた時は商品企画や開発へ情報をインプットし、開発商品に対してお客様からフィードバックを頂くなど、営業部門と一緒にお客様のお話を伺っています。
--------「せっていのとびら」の開発のきっかけや背景について教えてください。
貞末氏:島根県益田市(※)での教育関係者の皆さまが集まる研究発表会に伺った際に、「色の判別が難しい生徒がいる、なんとかしてあげたい」と先生に相談されたことがきっかけです。「Windowsのアクセシビリティで設定を変更することで解決できませんか?」とお答えしたものの、そこにたどり着くまでの階層が深くて、使いづらい、発見しづらいという話になり、商品企画に相談したところから始まりました。
※島根県益田市は、2016年度からWindows PCによる1人1台端末の実証実験を東京学芸大学 森本 康彦 教授とDynabookの産学官連携で進めてきた
貞末氏:先生がおっしゃるには、「子どもたちは色が分からなかったり、文字が読みにくかったりしても、言い出せずに手を止めたまま黙って授業をうけてしまう」と。私としては、子どものときにつまずいたら、大人になるまでパソコンやタブレットを嫌いになってしまうと思ったので、なんとしてでも解決したいと思いました。
子どもたちの使いやすさを考え、視覚的に操作できるショートカットのソフトウェアを開発
安藤氏:これまで弊社でもソフトウェアを開発するにあたってアクセシビリティのケアはしてきたつもりですが、貞末のヒアリングで教育現場の本当のニーズが見えてきました。我々は、Windowsのどこでどんな設定ができて、というのは職業柄把握できているわけですが、一般のユーザーや子ども視点だと、深い階層にあるものを見つけるのは難しいんだなと改めて感じましたね。
貞末氏:最初は医学的な面まで追求しようとも考えましたが、ソフトウェアでサポートする難しさもあり、まずはあまり知られていなかったWindowsのアクセシビリティを使ってもらえるようにショートカットを作って、簡単にたどり着けるようにしようと。
東谷氏:スマホだとホーム画面にアプリや機能がアイコンとして表示されていて、ボタンを押す感覚ですぐに起動しますが、パソコンだと、ある程度階層を進まないとたどり着けない。子どもたちは、アイコンをタップしてアクセスするという感覚に慣れている。ボタンを並べたようなショートカット画面を作れば、使ってもらいやすくなるのではと感じました。
--------「せっていのとびら」はアクセシビリティに関する項目が分かりやすくまとまっています。このデザインに落ち着くまでには紆余曲折があったのでしょうか。
東谷氏:タブレットで画面が自動回転することは決まっていましたので、横表示でも縦表示でもデザインが崩れないよう気をつけました。統一したデザインにする為に、横の場合と縦の場合を両方同時に検討しながら、余白はこれぐらいがいいんじゃないかと地道な調整を繰り返しました。
東谷氏: もちろん、文字の色と背景の色のコントラストはアクセシビリティに配慮したものとなっています。また、グレートーンに変換した場合でもデザインが見やすいことは、視覚的なバリアフリーを考慮する上で重要な要素なのですが、今回カラフルながらその条件も満たす配色となっています。
貞末氏:そこは、東谷が本当に細かい部分まで確認してくれました。やっぱりダークモードも必要なんじゃないか、ボタンにポインターを乗せたときにはっきり分かるようにした方がいいんじゃないかと考え抜いて、どんどんと使いやすいものになっていきましたね。
東谷氏: 特徴的なのは、ボタンのステータス変化(操作に伴う色や大きさの変化)が一般的なアプリよりも明瞭なことです。マウスのカーソルをボタンに乗せると輪郭線が太くなったり、ボタンを押したときは若干小さくなったり、操作していることがしっかりと伝わることを大事にデザインしました。
安藤氏:アプリは全画面で立ち上がるようにしています。中途半端な大きさのウィンドウになってしまうと、触る場所が変わってしまうので。極力タッチが少なくなるように設計しました。
子どもたちが想像以上に使いこなしてくれた――先生からも「パソコンが身近になった」と喜びの声が
--------実際に導入した教育現場からの声を教えてください。
貞末氏:すごく喜んでいただきました。子ども達は障がい特性があるなしに関係なく、授業によって字の大きさを変えたり、音量を調整したりと、こちらが想像する以上に使いこなしてくれていて、本当にうれしかったです。また、Windowsのアクセシビリティをご存じでない先生方も多く、先生ご自身も、「せっていのとびらのおかげでパソコンが身近になりました」という話も聞かせていただきました。最初は「dynabook Kシリーズ」に合わせて開発しましたが、現在はdynabookのパソコンではインストールできるので、教育現場に限らず、多くの方々に活用いただいています。
安藤氏:普段は反応を図るものといえば売上台数の数値になっていて、現場の声が直接届くことはあまりないんです。今回は反響の大きさから喜んでいただけたことを知れて、うれしかったですね。
--------お話を伺って、正にDynabookのビジョンである「人に寄り添う、社会を支える、真のコンピューティング」、「ユーザーを起点に考えた新しい付加価値・サービス」を体現されていると感じました。今回のプロジェクトを通じて、改めて共感を覚えた点はありますか?
東谷氏: マラソンで、自分が人より遅れていると焦りますよね。でもパソコンを使った授業で置いていかれたと感じた瞬間って、生徒はもっと不安を感じると思うんです。そんな子どもの焦りやストレスを「せっていのとびら」で少しでも軽減できれば、この仕事には大きな意義があると感じています。
貞末氏:お客様に寄り添って考えることがDynabookの理念。普段諦めているところ、そういうものだからと仕方なく受け入れている潜在的な課題をどれだけ拾い、寄り添うことができるか。すべてには気づけなくても、日ごろから現場に足を運んで、お客様と会話をして、何を必要とされているのか、これからも耳を傾けていきたいです。
益田市の子どもたちが「せっていのとびら」を活用する様子を動画でもチェック
まとめ
「Windows アクセシビリティ」とWeb検索してみると、「ない」「どこ」といったワードがレコメンドされる。存在は知っていても、うまく見つけられない、活用できていないという人は少なくないはずだ。パソコンは、テキストやカーソルのサイズを自分に合ったものに変更するだけでも使い勝手が劇的に向上する。「せっていのとびら」は多くの人にとってパソコンを使いやすくしてくれる、まさに“とびら”となるアプリなのだ。
現在、dynabookのパソコンで使用できる「せっていのとびら」のダウンロードは無料。ぜひ一度とびらを開き、自分にとってのアクセシビリティを確認してみてほしい。