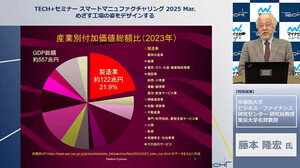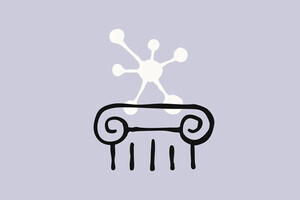2023年12月14日、米インテルはAI時代の到来を宣言し、“AI Everywhere”の戦略とともに、最新のインテル® Core™ Ultra プロセッサー(開発コード:Meteor Lake)を発表。NPU(ニューラル・プロセッシング・ユニット)を実装し、エッジ(PC)側でのAI処理をより効率的に行う「AI PC」の実現に寄与するこのプロセッサーは、インテルとして“40年に一度の大変革”と位置付けられている。
このAI PCは、今後のビジネスにおいてどういった影響を及ぼしていくのだろうか。
本稿では、以前にも「インテルが持つビジネスPCの運用管理における世界観」をテーマとした記事で共演した、法人向けPCブランドであるインテル® vPro® プラットフォームの拡販と、企業への導入支援を担当するインテルの佐近 清志 氏と、マイナビグループにおいてIT戦略、PC選定などを統括するマイナビの八角 雅明 氏のお二人で、再度対談を実施。
情報システム部門から見たAI PCに対する考えや期待、さらにAI PCの中核を担うCore Ultra、vPro、OpenVINOといったプロダクトで進化するビジネスPCの在り方について話を交わした。
対談者
・インテル株式会社
セールス&マーケティンググループ
ビジネスクライアント・テクニカル・セールススペシャリスト 佐近 清志 氏
・株式会社マイナビ
デジタルテクノロジー戦略本部 デジタルプラットフォーム統括本部
コーポレートIT統括部 統括部長 八角 雅明 氏
AI PC時代の到来を示すインテル® Core™ Ultra プロセッサーが、ビジネスにおけるAI活用の鍵を握る
――初めに、インテルが掲げる“AI Everywhere”に込められた思いをお聞かせください。
佐近:インテルとしては、今回発表したMeteor Lake を40年ぶりの大規模なアーキテクチャー刷新と捉えており、AI技術による大きな変革の波は、今後もその勢いを落とすことなく、あらゆる領域に行き渡っていくと考えています。そしてハードウェアベンダーである我々の責任としては、こうした波に乗るためのプロダクトを準備しなくてはならない。つまり、“AI Everywhere”とは、我々自身に向けたメッセージでもありますし、企業の皆様に対して「止まることのない、大きな波が来ますよ」と伝えるメッセージでもあると思っています。
――そのなかで、インテル® Core™ Ultra プロセッサーがリリースされ、AI PCの扉が開かれたような気がします。
佐近:そうですね、AI PC時代の到来を示す最初のプロダクトとして、Core Ultraという新たなブランドでリリースをさせていただきました。ですが、その特徴や強みについて理解されている企業担当者の方はまだ少ないと思っています。というのも、現在は「AI PCとは?」という定義のところから周知していくフェーズと捉えており、今後も、さまざまなOEMメーカーから新製品が出てくるなかで、“AI PCがもたらす価値”を知っていただけると、期待をしています。
従来のPCとAI PCの一番大きな違いは、AI処理に特化したプロセッサーであるNPUが載っているか否かです。とはいえ、以前のPCでもAI処理を行うことはできますので、「AIを動かすためにNPU搭載製品に買い換えてください」というような話ではありません。確かに、今後登場するプロセッサーはCore Ultraの様にNPUを搭載した製品が主流になっていくでしょう。ですが、インテルはハードウェアベンダーとして、AI時代に向けてNPU搭載のプロセッサーを提供しているわけで、それだけでは何のベネフィットにも繋がらないのです。
必要なのは、NPUを使って皆さんの作業効率や創作活動をより良くしていくことであり、つまりはアプリケーションが重要な役割を担います。インテルでは、AIアプリケーションのNPU対応を簡単に行えるインテル® OpenVINO™ ツールキットというソフトウェアを無償公開しており、現在100社以上のパートナーが新しいCore Ultraに最適化されたアプリケーションを開発しています。さらに300以上の新機能も用意しており、これらが2024年の年末までに出てきます。
こうした状況を踏まえて“AI Everywhere”というメッセージを打ち出したかたちです。
八角:PC選定を行う情報システム部門という立場で、AI PC、Core Ultra、NPUなどの話を聞いた際には、「これが業界のスタンダードになっていくんだろうな」という印象を強く受けました。ただ、佐近さんが話されたように、結局は対応するアプリケーションがどれだけ出てくるのかによって、Core UltraなどのNPUを搭載したPCの価値は変わってくる為、そこは注視しながら導入を検討すべきと思っています。
また、ここ半年か1年くらいの間に、さまざまなAI関連のセミナーに参加させていただくなかで、“AIをエッジ(PC)側で動かす”というキーワードを聞く機会が増えてきています。そのため今回、NPU搭載のCore Ultraが登場したことは、その実現に向けて大きな意味があると感じました。しかし、今すぐに社内でCore Ultra搭載のAI PCへ入れ替えができるかというと難しく、どれだけ魅力的なアプリケーションが出て、利用者や管理者にメリットを与えてくれるのかが判断ポイントになってくると考えています。
佐近:確かに、実際の業務にどのように影響するのか、何ができるようになるのかを皆さん気にされていますが、それはアプリケーションや機能によって決まります。つまり、それらを使用するうえで、どのようなハードウェアが必要であるかを判断するような形になると思います。
その文脈でいうと、Core Ultraはモバイル特化型のプロセッサーであり、PC側でAIを動かすという流れのなかで、モバイルユーザーがこれまでと同じスタイルのままAIを活用するために開発されました。通常、皆さんがパッと思いつくAIのサービス・機能の半分以上はクラウド上で処理されていますが、これをPC側でということになると、どんどん高まっていく高負荷なAI処理をCPUやGPUで行うため、消費電力が高くなってしまいます。
もちろんCPUやGPUでもAIを動作させることは可能ですが、モバイルノートPCの場合はACアダプターの常時接続が必要でしょう。さらに、負荷の高いAI処理をバックグラウンドで行っていれば、通常の作業も重くなり、モバイルの強みが失われてしまいます。
こうした処理をNPUが肩代わりすることで、快適な業務環境を確保したままAIの効果を享受できるようになるというのが、ハードウェアベンダーである我々からのメッセージとなります。
AI活用につきまとう多くの課題、安全性と利便性の妥協点はどこにあるのか?
――ビジネスにおけるAI活用では、セキュリティやプライバシーの観点から、データを管理することが大切になってきます。こうした観点から見たAI PCの導入メリット、デメリットについて話を伺えればと思います。
八角:弊社に限らず、AIの活用を検討されている企業に共通するものだと思いますが、攻めと守りの両面で課題があると感じています。
攻めの観点では、この用途で利用してよいのか、AIによりもたらされた情報は本当に正しいのか、といったAIアプリケーションや機能を積極的に活用していくためのガイドラインを策定する必要があると考えています。AIの使い方はそれこそ無限にあり、管理者としては従業員すべてのAI活用をコントロールするのは現実的ではありません。管理面も含めてクリアにすべき課題は数多くあるでしょう。
守りの観点では、やはりデータの管理が課題となります。入出力したデータがAI側に保存されてしまうのか、学習に使われてしまうのか、そういった部分を明確化しなければセキュリティは担保できません。ですがAI PCのエッジ側でAI処理を行うというコンセプトは、こうした課題を解決するための有効な一手になると思いました。
佐近:おっしゃるとおり、データがどう使われるのかは、AI活用を検討する企業にとって一番の懸念事項といえます。先ほど話した100社のパートナー企業も、「二次利用をしない」「企業内データのみで完結させる」など、コンプライアンスに配慮したソリューションを確立させようとしていますし、AI活用のガイドラインも作られていくでしょう。その意味では、データ周りの懸念は徐々に解消されていくと予想しています。
またAI活用が進むなかで、業務に携わっておられる皆様が、ぜひ使いたいと感じる機能やアプリケーションが登場してくれば、AI PCの導入に舵を切る企業も増えていくでしょう。今すぐというわけではありませんが、安全性と利便性の妥協点を探り、AIの活用を推進するフェーズは必ず来るはずです。その実現に向けてインテルでは、まずはアプリケーションの拡充を支援し、そのアプリケーションを高速かつ低消費電力で動かせるハードウェアの提供を続けていきたいと考えています。
実際、OSレベルでもAI PCへの対応は進んでおり、Windows 11に搭載されたWindows Studio エフェクトという機能は、すでにNPUに対応しています。そのほかにも画像生成や動画編集、さらにはセキュリティ対策ソフトにおいてもNPU対応製品が登場しました。なかでも特に、セキュリティについては非常に効果的なAI活用方法と考えています。
AIを使って巧妙化したサイバー攻撃に対処するのは一般的になってきていますが、その処理は重くなる一方で、このままでは安全性と引き換えに快適な業務が妨げられるようになってしまいます。その点をNPUで肩代わりできれば、負荷をかけずにエンドポイント側でセキュリティを担保できる。また、ビデオ会議などのコラボレーションに関しても、AI PCならばノイズキャンセリングや背景ぼかしなど、皆さんが欲しいと感じる機能を、消費電力を増やさずに低負荷で実現できます。
AIというと画像生成やビデオ編集などクリエイター向けの技術を考えられる方も多いと思いますが、その真価はセキュリティやコラボレーションなど一般的な領域でこそ発揮されるでしょう。
八角:確かにPCメーカーのデモンストレーションでは、画像生成などを例にAI処理の効果を解説するケースが多く、編集職やデザイン職向けのハイスペックモデルという印象が強かったです。ですが、佐近さんの話をお聞きして、セキュリティやコラボレーションなど、より一般的なPC利用の領域にも有効であることが理解できました。また、エッジ側のセキュリティ強化につながるのは、管理者から見ても非常に魅力的です。
複雑化していく運用管理のなかで、唯一無二の価値を提供し続けるインテル® vPro® プラットフォーム
――冒頭の話でもあったように、今後のボリュームゾーンの製品はインテル® Core™ UltrプロセッサーなどのNPUが実装されたAI PCになっていくと思います。IT管理者の立場からして、この変化をどのように捉えていますか。
八角:IT管理者側としては、一部のユーザーに限定してAI PCを導入することで、社内に複数モデルのPCが混在する環境となってしまい、調達面・管理面での負荷が高まってしまう点を危惧しています。
実際のところ弊社では、ビジネスPCを複数モデル運用管理しているのが現状となっていますが、本音を言えばPC調達の効率化はもちろん、セキュリティなども含めて、できるだけ統一した管理とサービス水準でコントロールしていきたいと考えています。そのため、単に機能やメリットだけで特定のユーザーに導入できるかというと、難しい部分も出てくるでしょう。そこも踏まえて導入を検討していく必要があると考えています。
佐近:八角さんのおっしゃる通り、多くのIT管理者が同じ考えだと思います。そういったIT管理者のニーズに対応するためにインテルが展開しているのが、パフォーマンスやハードウェア・ベースのセキュリティ、管理機能、安定性を実現する機能を備えたインテル® vPro® プラットフォームです。
異なる製品やモデルであっても、vPro対応であればハードウェア構成が同じになるので効率的かつ一元的管理が可能になります。このvProというのは、もともと弊社のIT部門が半導体工場のPCをリモートで管理したいという目的で開発を依頼した背景があり、その後、セキュリティ重視でアップデートを重ねてきました。
また、インテル® vPro® プラットフォームではある程度の高いスペックを要求するので、価格的には少しハイエンドに寄ってしまうという懸念点もありますが、管理の効率化、並びにセキュリティ強化というメリットも大きいです。こういった点が評価され、導入する企業や地方自治体も増えてきました。さらに、vPro対応のインテル® Core™ Ultra プロセッサーもローンチしており、インテル® Evo™ エディションも用意しています。
Evoエディションに準拠したノートPCは、明らかに軽くて薄くてスタイリッシュでパフォーマンスも高い。もちろんvProにも準拠しており、製品としての満足度が高いので従業員の方は喜ばれるのではないでしょうか。EvoデザインのAI PCを使って、その利便性・効率性を体験してしまうと、これまでのPCでは満足できなくなると思います。
やはり、従業員の皆さんのデイリー作業にどれだけインパクトを与えるかが大切で、我々がCore Ultraを40年に一度の大変革と呼ぶ理由もそこにあります。セキュリティやコラボレーションを皮切りに、今後も人々が驚くAIソリューションが多く出てくるはずで、我々自身もかなりワクワクです(笑)。
八角:今の話を聞いて、私も1人の利用者として、さらにIT管理者としても期待に胸が膨らみますね。セキュリティに関しては、エンドユーザーが意識することなく安全に業務を行えるような環境をAI PCで実現できる未来が見えました。あとはAIをエッジ側で動かすことが当たり前になったときに、社内でのアプリケーション開発、いわゆる内製化も進むのではないかと期待しています。そこでは、冒頭に出たインテル® OpenVINO™ ツールキットが重要な役割を担うということですね。
佐近:その通りです。インテル® OpenVINO™ ツールキットを使用することで、OpenVINOのシンプルなAPIによりエッジアプリケーションにAIを組み込むことが容易になります。NPUを優先的に使用したり、NPUと他のデバイスを複合的に活用してスループットを上げたりなど、柔軟なシステム構成をとることも可能になります。現在も頻繁にアップデートを重ねて、多様なラージランゲージモデルへの対応を進めており、AI PC向けのソリューション開発に欠かせないツールとして日々進化しています。
AI PCの登場により変化していく、これからの“ビジネスPCの在り方”を確認する
――最後に、ビジネスにおけるインテル® Core™ Ultra プロセッサーを搭載したAI PCの活用という文脈で、今後の展開についてメッセージをいただければと思います。
佐近:私はIT部門出身で、堅い使い方しか思い浮かばないのですが、AIを活用することで、社員がフィッシングに引っかかることがなくなる、ランサムウェアに悩まされることがなくなる、そうしたセキュアな世界観を実現できればと考えています。
八角:確かに、IT管理者としてセキュリティというのは、消えることの無い永遠のテーマではありますし、セキュリティに関するAI活用の話題が増えていることは実感していました。AI PCの活用が、今後のビジネスPCにおけるセキュリティの不安を少しでも払拭できるということですね。佐近さんがおっしゃるセキュアな世界がとても楽しみです。
佐近:近年では、マルウェアの作成にAIが利用されているケースも増えてきており、高度化したサイバー攻撃に対応するために、企業側でもAIを活用していくことになるはずです。vPro対応のCore Ultraならば、セキュリティ機能がさらに強化されており、年内にランサムウェアを検知できるTDT(インテル スレット・ディテクション・テクノロジー)もNPUに対応したアプリケーションが増える予定です。また、新たにOS下層を保護するインテル® シリコン・セキュリティー ・エンジンというシステムファームウェアの認証に使用されるオンチップ回路を搭載しておりますので、一般的なPCと比較して最上位のセキュリティレベルをvProは提供しています。
AI活用においては、八角さんが話されたように数々の懸念点が存在するのは確かですが、それでも“AI Everywhere”の未来が、徐々に見えてきていると感じています。ぜひインテル® Core™ Ultraプロセッサー搭載のAI PCに触れて、今後のビジネスPCの在るべき姿を体験してみてください。