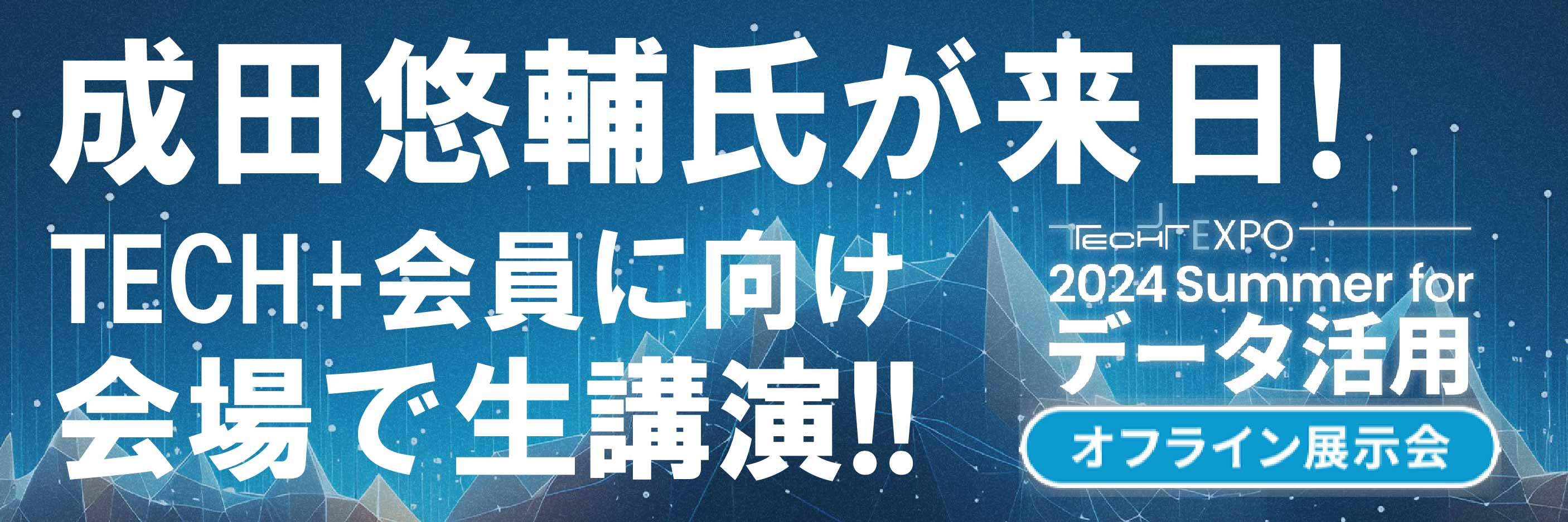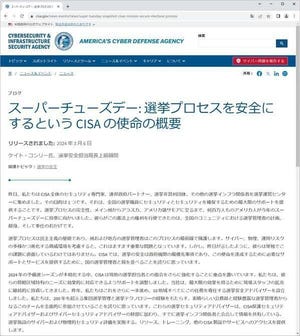DXの波が金融業界にも及ぶ中、プライバシー保護などの懸念から、顧客データを活用したサービス提供については、多くの企業が手探りで進めている。いったいどのような思想で、歩みを進めていくべきなのだろうか? Fintechの世界的権威であるキース・カーター氏に、海外と日本の取り組みについて話を聞いた。
【プロフィール】
KBC Global Partners
マネージングパートナー(最先端テクノロジー担当)
Keith Carter氏
コーネル大学でMBAを取得後、レンセラー工科大学で電気・コンピュータシステム工学の学士号を取得。アクセンチュア、エスティー・ローダーでの勤務やシンガポール国立大学の助教授などを経て、現職。またデジタル資産業界のグローバルコンソーシアムであるDEC Instituteの取締役も務める。これまでにNUS FinTech Societyや、生成AIの開発企業・JustAskProf.comなどを創設し、Fintechの世界的権威として広く知られている。講演実績、著書多数。
URL:https://www.keithbcarter.com/
銀行こそ、新たなテクノロジーを取り入れるべきである
―キース・カーターさんは、ビッグデータインテリジェンスとFinTechの専門家として、KBC Global Partnersで活躍されています。現在はどのようなプロジェクトを推進されているのでしょうか?
私は今、”Just Ask Prof”という生成AIを活用した教育サービスの開発を進めています。これは「親子」にフォーカスした教育プラットフォームであり、AIとの対話を通じて、子どもは科学・数学を、親は金融リテラシーを、それぞれ学ぶ事ができます。家族が一丸となって人生に向き合い、より豊かに過ごせる。そんなサービスを目指しています。
[PR]提供:Tealium Japan