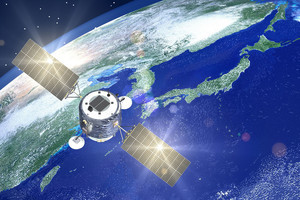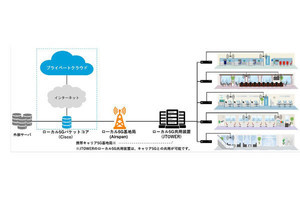かねてから「世界より遅れている」とされる日本の5G。2022年11月14日にエリクソンの日本法人であるエリクソン・ジャパンが実施した「エリクソンフォーラム2022」でも日本の5Gの遅れが指摘されていますが、現状どのような点が遅れているとエリクソンは見ており、その解決のためどういった取り組みを進めているのでしょうか。→過去の次世代移動通信システム「5G」とはの回はこちらを参照。
日本で遅れが目立つ5Gの高速体験
通信機器ベンダー大手、エリクソンの日本法人であるエリクソン・ジャパンは2022年11月15日、同社の最新技術やビジネスの取り組みなどを紹介するイベント「エリクソンフォーラム 2022」を開催しました。その中でエリクソン・ジャパンの代表取締役社長であるルカ・オルシニ氏が指摘したのが、日本の5Gの“遅れ”についてです。
4Gまで高度なネットワーク技術をいち早く導入してきた日本ですが、5Gではサービス開始が主要な国々より1年遅れてしまうなど、5G環境整備の遅れが多く指摘されています。ルカ氏は日本がモバイル通信の分野において、「この20年で初めて遅れを見せている」と話し、現在も遅れを取り戻せていない状況にあると話しています。
ではエリクソンの視点から、その遅れがどのような点にあると見ているのでしょうか。エリクソン・ジャパンの代表取締役社長 戦略事業担当である野崎哲氏は、日本ではエリアカバーの拡大に力を注ぐ一方、5Gのユーザー体験価値向上では大きく遅れを取っているといいます。
それは携帯電話事業者のミッドバンド、要はおおむね2.5GHzから6GHzまでの、いわゆる「サブ6」と呼ばれる帯域の活用の遅れだといいます。
5G向けのサブ6帯域として、主に3.7GHz帯と4.5GHz帯の2つが活用されていますが、野崎氏によるとそもそも日本では5Gの基地局比率が4G対比でまだ19%にとどまっているのに加え、その中でもサブ6の周波数帯を使った基地局は9%に過ぎないとのこと。
それゆえOpensignal社の調査でも5Gの捕捉率は7.3%にとどまり、通信速度も5Gで高いパフォーマンスを発揮する韓国や台湾だけでなく、中国にも及ばないとしています。そこには日本特有の事情も影響しています。
1つは、日本で割り当てられているサブ6の主要周波数帯である3.7GHz帯が、衛星通信と電波干渉を引き起こしてしまうため整備する場所や電波の出力に大きな制約があること。とりわけエリクソンの主要顧客となっているKDDIやソフトバンクは、衛星干渉の影響が少ない4.5GHz帯を割り当てられていないことから、衛星通信との干渉が大きく影響して3.7GHz帯での通信速度を容易に上げられない状況にあるといえます。
そしてもう1つ、大きな制約となっているのが「Massive MIMO」の導入の遅れです。Massive MIMOは多数のアンテナ素子を用いて人が多く集まる場所などでの高速化を実現する技術ですが、野崎氏はMassive MIMOに対応したアンテナの設置数が少ないことが、日本で通信速度が向上しない大きな要因の1つとしています。
ですがMassive MIMO対応アンテナは、多数のアンテナ素子を搭載している分大きくて重いという弱点があります。日本では地震など自然災害が多く、耐震性などの観点から重いアンテナを設置するのが難しいので、それがMassive MIMO対応アンテナの設置が進まない要因となっている訳です。
遅れを取り戻すには日本の環境に応じた施策が必要に
では、それら2つの課題に対し、エリクソンはどのような解決策を打ち出しているのでしょうか。まず衛星通信との干渉についてですが、ルカ氏は同社でも、出力の制御や電波を飛ばす方向を変えるなどさまざまな技術を導入して対応しているといいます。
しかし、最大の解決策は、やはり衛星通信側が携帯電話の電波に干渉しない環境が整うことのようです。実際ルカ氏は「2023年から(国内の衛星通信の)地球局が移設され、問題が少なくなると思う」と話しており、国内の衛星通信側の対応によって今後出力を大幅に上げられるとの見込みを示しています。
もう一方のMassive MIMOに関する問題については、エリクソンが新しいアンテナを開発して対処を進めているようです。それが「AIR 3268」というMassive MIMO対応アンテナで、その最大の特徴は軽さだといいます。
野崎氏によると、国内で5Gの整備を進めていた2018年時点でのMassive MIMO対応アンテナは60kgくらいと、1人では運べない重さであり携帯電話会社から「これでは使えない」と厳しく指摘されたとのこと。
そうしたことから、同社ではMassive MIMO対応アンテナの軽量化を進め、2021年には20kg、そして2022年に投入されたAIR 3268では12.5kgと、1人でも十分運べるまで重量を抑えたのだそうです。
その軽量化を実現するのに貢献したのが「Ericsson Silicon」というASIC(特定用途向けIC)とのこと。Massive MIMOは多数のアンテナを用いるため処理負荷が大きく、発熱も大きくなることが大型化の原因となっていたことから、Ericsson Siliconの導入による高速処理で発熱を抑えることによって、軽量化を実現できたようです。
このような施策から見えてくるのは、5Gの性能を発揮する上ではその国に応じた技術や取り組みが求められるということでしょう。エリクソン・ジャパンの関係者によると、日本ではアンテナの軽量化に対するニーズが非常に大きいですが、世界的に見るとそうしたニーズは実はあまりないのだそうです。
そうした細かなニーズに対応することが日本での5G性能向上に大きく影響するといえ、それが商機につながることからエリクソンも積極的に取り組んでいるのでしょう。
ただ、今後を考えるならば自然災害が多くミッドバンド・ローバンドで自由に使える電波の空きが少ないといった日本の地理的・電波的制約が、5Gの性能強化でマイナスに働きやすいともいえ、それが5G、そして6Gの整備で他国から一層遅れてしまう可能性があることが気がかりでもあります。