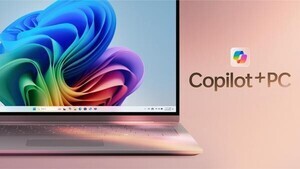クリエイティブツールの巨人、Adobeが年次イベント「Adobe MAX」で新機能やAI戦略を発表していた、まさにその時。Canvaが業界の話題を奪う発表を行いました。
2024年に傘下に収めたAffinityの3つのクリエイティブツール「Affinity Photo」(写真編集・加工)、「Affinity Designer」(デザイン)、「Affinity Publisher」(レイアウト)を統合し、「無料」でリリースするという爆弾を投下したのです。
6日間で100万ユーザーを獲得
この衝撃がどれほどのものだったかは、数字が雄弁に物語っています。PitaPixelによれば、Affinityは発表からわずか6日間で、100万人の新規ユーザーを獲得しました。これはクリエイティブソフトウェアでは前例のないスピードです。
参考として、同様に無料化戦略で成功した動画編集ソフト「DaVinci Resolve」は、主要機能の無償提供から100万ユーザーに到達するまでに9年を要しました。Affinityが1週間足らずで達成した数字は、いかにこの発表が注目を集めたかを物語っています。
もちろん、この発表は熱狂だけで受け止められているわけではありません。プロのデザイナーから学生までが無料で使える本格ツールに色めき立つ一方で「何か裏があるのでは」という冷静(あるいは冷ややか)な視線も少なくありません。
買い切り型の限界とCanvaによる買収
そもそもAffinityとはどのようなツールなのでしょうか。クリエイティブツールは比較的ニッチな分野なので、Affinityという名前を初めて聞いたという方もいるかと思います。
開発元のSerifは1987年に英国で設立され、当初はWindows向けのクリエイティブソフトウェアを開発していました。しかし、クラウド型・サブスクリプション型の波、そしてモダンなMacやiPadなど新デバイスの台頭に直面し、事業戦略をゼロから見直しました。
そして、2014年にMac向けに「Affinity Designer」をリリースし、続いて「Affinity Photo」、「Affinity Publisher」を投入。人気ソフトの多くがサブスクモデルに移行する中、それに抵抗を感じるクリエイターの「駆け込み寺」として、高性能な「買い切り型」ツールを提供し、独自の地位を築いてきました。
しかし、アプリ開発者の多くがサブスクモデルに移行するのには理由があります。継続的な収益を確保しやすく、資金繰りや開発投資の計画が立てやすくなります。対して、買い切り型は収益の波が激しく不安定で、さらにクラウドや共同作業機能との親和性が低いという課題があります。それらがAffinityの負担となっていました。
2024年にSerifは、一般向けのシンプルなオンラインデザインツールを展開していたCanvaによる買収に合意しました。Canvaにとって、プロフェッショナル向けの高精度な印刷物制作、DTP、複雑なレイアウト、本格的な写真レタッチなどの分野は弱点でした。
一方、Serifにとっては、Canvaの資金力とクラウド技術、AI機能を活用できることが魅力でした。両社の弱点を補完し合える関係から買収が実現しました。当時、多くの古参ユーザーが「ついにAffinityもサブスク化される」と覚悟しました。ところが、現実は真逆で、Canva傘下の新「Affinity」が無料で登場したのだから驚きです。
無料の裏にあるビジネスモデル
ただし、すべてが無料というわけではなく、Affinityには生成AI機能が搭載されておらず、「生成塗りつぶし」などAI機能を利用するにはCanvaのプレミアムサブスクリプションが必要です。つまり、CanvaはAffinityを無料の入口として提供し、AI機能を求めるユーザーには有料プランへの移行を促す戦略です。
この点について、意見は分かれています。「プロフェッショナルの世界でAI機能はもはや必須。結局、サブスクリプションが必要になる」という声があります。しかし、「AIは使わない」というクリエイターも存在し、Affinityほど高度なクリエイティブツールを無料で利用できる他の選択肢が見当たらないことを考えると、無償化のインパクトは大きいともいえます。
他にも、無償化に対して「いずれ広告が表示されるようになるのではないか」「ユーザーの制作物がAIのトレーニングに使われるのではないか」など、さまざまな声があがっています。Canvaはこうした懸念を否定していますが、持続的に使えるツールを求めるクリエイターの疑念は簡単には払拭されません。
最も不安視されているのは、ツールのアップデートや機能強化が停滞してしまう可能性です。買収によって、独自性のあったアプリがその輝きを失う例は枚挙にいとまがありません。最近のクリエイティブ業界で言えば、Appleに買収された「Pixelmator」がその例かもしれません。
買収前のPixelmatorは、Appleプラットフォームへの最適化を武器に、OSアップデートと同時に新機能を意欲的に取り入れ、月次で更新を重ねる「尖った」ツールでした。しかし、Apple傘下に入って以降、その更新は「バグ修正」程度に留まり、開発チームは事実上、Apple社内のプロジェクトに吸収されたように見えます。
Affinityも同じ道を歩むのではないか。Canvaの戦略上は「プロ向けツールの開発」よりも「CanvaのAIサブスクへの誘導」が優先され、Affinity本体の機能強化が停滞してしまうのではないか。この懸念が、100万人の熱狂の裏にある最大の不安となっています。
「買い切り」の信念が「無料」に行き着いた必然
そうした懸念はもっともですが、私はこの買収劇と無償化を、単なる企業戦略以上に感じています。
数年前、あるイベントでAffinityの開発チームに話を聞く機会がありました。Pixelematorがサブスクモデルを採用した時で、Affinityも導入する可能性を尋ねた私に、彼らはこう答えたのです。「Adobeのツールに投資するほどではないが高度なツールを求める層と、買い切り型を求める層は大きく重なっている。その層こそがAffinityの顧客だ。だから、買い切り型を可能な限り維持したい」と。
その信念が行き着いた先が、Canvaとの統合だったのではないでしょうか。Canvaでのフリーミアムモデルは、収益の不安定さやクラウド・AIとの相性という買い切り型の課題を克服しつつ、一般ユーザーの中でより高度なクリエイティブツールを必要とする人々のニーズを満たせるものになり得ます。
この無償化は「Adobe対抗」という文脈で語られがちですが、本質はそこではないと思われます。DaVinci Resolveが普及したからといって、Premiere Pro(現Premiere)が市場で弱体化したわけではありません。プロの現場は依然としてPremiereを使い続けています。むしろ、DaVinciの登場は、動画編集という市場そのものの裾野を広げました。
新しいAffinityの登場にも同様の効果が期待できます。FireflyのようなAIツールや、頻繁なアップデート、手厚いサポートやコミュニティを求めるクリエイターは、引き続きAdobe Creative Cloudを選ぶでしょう。一方で、手軽に高度なクリエイティブに挑戦したい人やまだAIツールを必要としない人にとって、Affinityは魅力的な選択肢となります。
そして何より、このCanvaの一手は、Adobeや、Apple傘下となってから停滞気味のPixelmatorをも刺激し、業界全体によい競争を生むはずです。
クリエイティブツールの民主化は、より多くの人々に表現の機会を与えます。同時に、AI機能をフックにしたフリーミアムモデルがアプリ市場において新たな収益モデルとして定着するかどうかが注目されます。Affinityの100万人ユーザー獲得は華々しいスタートでしたが、ユーザーの信頼を維持し続けられるかが、真の試金石となるでしょう。それは、今後のツールの進化にかかっています。