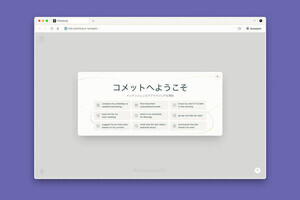9月の新学年から、カリフォルニア州の公立の中学・高校で早い時間の始業が禁じられた。中学校は8時以降、高校は8時半以降に始まる。
これは子供達の睡眠不足を防止するため。米国では親が子供を送り迎えしている家庭が多く、これまで親の勤務時間に合わせて早めの始業時間にしている学校が多かったが、スマートフォンを持つ青少年が夜更かしする傾向も相まって睡眠不足がひどくなっていた。しかし、8.5時間より少ない睡眠では身体的・精神的に健康が損なわれる。2014年の米小児学会の勧告から、カリフォルニア州では始業時間を8時35分以降にする試験導入を一部で行ったところ、遅くした高校で主要科目の成績や出席率が向上。今年から州全体での採用になった。
「いやいや、そこは早寝・早起きでしょ!」とツッコミたくなるが、習慣化は習慣化で別のことでも身につけさせられる。時間を守れる生徒でも睡眠を削る可能性が高くなるような早い時間に学校を始める必要はない。早すぎる始業時間で本来のパフォーマンスを発揮できずに失われる生産性は大きいというのが今どきの考え方なのだ。
それは子供だけではなく親の世代も一緒で、子供の誕生会などで集まる機会があると、最近はスマートフォンの新製品より睡眠やスマート寝具の話で盛り上がる。というのも、10数年前に仕事のパフォーマンスに適度な運動が結びつけて語られ始めたのと同じように、睡眠も必要であると見なされ始め、会社もしっかり睡眠をとるように指導するようになったからだ。技術系エリートの間で"徹夜"が名誉の象徴とされていたのは今は昔。そんなワークスタイルを披露しようものなら、今は「自己管理ができていないヤツ」と見なされる。
1日に7~8時間寝るだけでは不十分。ライフハックに積極的な人が積極的に睡眠の質の向上を追求し始めている。例えばここ最近勧める人が増えているのがEight Sleepのマットレス「Pod 3」(クイーンサイズ:3,395ドル)である。心拍や呼吸から睡眠の質とサイクルをトラッキングし、睡眠習慣に基づいて快眠できる体温になるようその人に適切な温度に調節する。ベッドに入ると適度にひんやりとした快適温度で、睡眠段階よって温度が調整され、深い眠りを持続できるという。最近増加している温度調節対応のマットレスの中で一番人気である。
スマートウォッチに比べると利用者数は少ないものの、睡眠にこだわる人の間ではスマートリング「Oura Ring」やヘルス/フィットネス・トラッカーの「Whoop」の利用が増えている。心拍数、皮膚温、動きなどのデータから、睡眠サイクルの各段階に費やされた時間が記録・分析される。
利用者からおすすめポイントとして挙げられることが多いのが、飲酒、ストレス、運動などが睡眠の質に与える影響の洞察だ。「寝酒」という言葉があるが、実際には少量でも飲酒によって睡眠の質が下がることが多く、自分もそうであることが分かって飲酒を控え始めた人が出てきている。でも、夜のお酒の時間が恋しい人達のために、「The Nightcap」(39ドル)のようなお酒のテイストと雰囲気で睡眠にプラスになるノンアルコール飲料も登場している。他にも身長、体重、好みの寝姿勢をもとに人間工学に基づいたオーダーメイドの枕を作る「Pluto Pillow」、昼食後の昼寝に使いやすいアイマスク「Manta Sleep Mask」(35ドル)など、様々な快眠グッズが注目を集めるようになった。
以前は睡眠が足りないと「ボーっとする」とか、仕事中に「眠くなる」という認識だったのが、最近は「最高のパフォーマンスを発揮するために睡眠をとる」である。「まるでアスリートみたい」とからかわれたりもするが、そうした考え方は着実に浸透し始めている。
先週ニューヨーク連邦準備銀行が公開した米労働省統計局American Time Use Survey (ATUS) データの分析によると、COVID-19禍の影響でオフィス出社が減少したことで、米国では1日に約6,000万時間の通勤時間が浮いた。その時間は主にレジャーと睡眠に使われている。
COVID-19禍が始まった頃は、慣れない在宅ワークでプライベートを犠牲にしてしまって、全般的に睡眠が不安定になっているという調査結果もあったが、しっかりと切り分けられるワーカーが増えたようだ。通勤時間がレジャーや睡眠に代わって労働に関わる時間は減少したものの、それらの効果による生産性の向上も確認されている。
18〜30歳の世代では、外食、社交、ワークアウトなどを優先する傾向が強く、在宅で睡眠時間が減っているケースも見られる。しかし、全体的には睡眠が増えており、睡眠の確保という点で在宅ワークはパフォーマンスを発揮できる環境を整えやすいといえる。もちろんオフィス出社には対面ならではのメリットがあるので、これだけでオフィスと在宅の優劣を決めることはできない。ただ、COVID-19禍の働き方の経験を経て、睡眠に時間を割り当てられる余裕が必要という認識が深まった。通勤するにしても、通勤にかかる不要な負担を減らす柔軟な仕組みを導入するなど、睡眠を損なわないライフスタイルを可能にする働き方という視点が今後強まりそうだ。