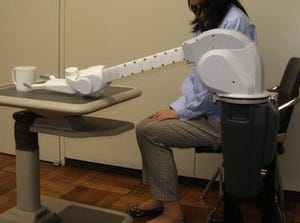つくば市で進められるセグウェイのシェアリング実証実験
2つ目が、前述したように2013年9月から行われている産総研~TXつくば駅のセグウェイのシェアリング実証実験だ。そして3つ目は2012年からスタートして現在も継続中の、Wingletを用いたNEDOのシェアリング実証実験「IT融合による新社会システムの開発・実証プロジェクト」となっている(実際に走行する実証試験は2013年9~10月に実施)。
セグウェイのシェアリング実証実験についてもう少し詳しく触れると、ルートは画像8の通りで現状は2点間で産総研の職員しか利用できない。歩行者・自転車専用道のペデストリアンデッキ(遊歩道)をほとんど通行する形で、途中に1カ所だけ横断歩道を渡るところがある全長約3.8kmだ。また充電ステーションは、先のレポートでもお届けしたが、産総研の建物内(画像9)と、TXつくば駅近くの交番の裏手(中央公園入り口)にある(画像10)。
シェアリング実証試験についてもう少し詳しく触れると、「産総研~TXつくば駅間の産総研職員による主に出張時のセグウェイ乗り捨て使用」である。現状、産総研~TXつくば駅間は、産総研の無料循環バスや一般の路線バスなどがあるわけだが、それらとの比較が1つというわけだ。どういう人が乗るとどういう速度で走るのか、どういう状況の時に使われるのか、収集すべき情報はいろいろとある。移動履歴や動画撮影、アンケートなどの手段によって情報は収集されており、それらの蓄積と解析も行われている。
セグウェイは2001年から販売が始まり、世界で年間1万台ずつ、これまで13万台ぐらい売れている。日本と英国を除く先進国で公道を走れるわけだが、個人で交通手段として利用しているという人は、それほど多いわけではない。世界的に見ても主に観光ツアーや警備の見回りが主な用途となっており(日本でも同じように観光名所や企業などで使われている)、セグウェイのシェアリングという使用例は実は世界的にもないのだ。そこで、今回の実証試験ではこれまでにないデータを収集できることから、貴重なものだとしている。
このように、今回の実証試験は、公道(遊歩道)走行を含む公共の場におけるモビリティロボットの新たな活用方法(シェアリング)に関するトライが意義の1つだが、情報インフラを活用した移動支援サービスのモデルケース提示ということも重要な意義だという。
実証試験は、2014年3月までは運用システムの安全性、信頼性検証のため、知能システム研究部門の常勤職員に限定して行われ、それ以降は産総研の全職員による利用となる方向だ。2014年4月以降の本格運用は特に期間を設けられていない。ただし、つくば市からの依頼で、市民への一般開放の要請も来ているということで、さらに翌年度の2015年4月以降にはそれを実現できるよう、一般市民が使用するためのさまざまな課題について解決していきたいとしている。
なお、現在は機能が変更されたり装備が追加されたりした4台が用いられている。追加装備としては、まずステアリングの中央にタブレット型コンピュータが状態表示モニタとして取り付けられ、セグウェイの予約時刻、位置・速度情報などが表示される仕組みだ(画像11)。また、前方向けにカメラが設置されており(画像12)、それはドライブレコーダとして走行中の前方の様子を記録している。
また特区の制限速度が時速10kmであることから、セグウェイは本来なら時速20kmまで出せるが、半分に抑えられるようソフトウェア的に変更済みだ。最高時速10kmでの片道の所要時間は、およそ25分となっている。この25分というのは、無料循環バスとどちらが早いかというと、待ち時間があったり、まっすぐ駅には向かわなかったりするので、あまり変わらないという。
ちなみに筆者も、オープンラボの取材にはTXつくば駅の近くから産総研への直行無料シャトルバスで訪問したのだが、走り出してからはおおよそ15分ぐらいだったと思うので待ち時間を入れたら、路線バスと比較してもセグウェイの方が早い可能性もあるというわけだ(路線バスは途中の停留所もある)。
あと、非常におかしなことになっているのが、特区の制限が緩和されているとはいってもそれでも制約はいろいろとあり、その1つがセグウェイで移動する際は産総研の職員がもう1人、保安要員として随行する必要があるということ。自転車で着いていくそうで、駅から帰ってくる時の利用でも、つくば駅に到着する時間に合わせて職員が駅まで行って、一緒に帰ってくるそうだ。セグウェイが走るのを自転車で追いかけるというのも、なにやら不思議な感じである(この話は、どこで話をしても受けるそうで、実際会場でも笑い声が起きていた)。そのほか安全に対する配慮としては、事前講習(インストラクター随想による走行ルートの試走を含む)、ヘルメットの着用なども義務づけられている形だ。
またこの実証試験を行うため、産総研では管理サーバを置いたシステムが開発された。その概要が画像13である。管理サーバが各ステーション(2カ所4ボックスずつ計8ボックス)とセグウェイ4台と通信する仕組みだ。ちなみに各セグウェイはGPSで位置情報を随時管理サーバにアップするので、何号機がどこら辺を走っているかといった動態管理がなされている。管理者はどこを走っているのかリアルタイムで見られるというわけだ(画像14)。もちろん、セグウェイの予約登録機能も実装済みである。
ちなみに、予約・貸し出し・返却の流れも紹介された。登録されているユーザがWeb画面上で予約をすると、予約コードとQRコードがまず発行(画像15)。次に予約時刻に充電ステーションの監理ポストで人称を行うことで、予約したセグウェイを充電ステーションのボックスから取り出せ、搭乗できるようになる。目的地側のステーションに近づくと、サーバがそれを認識してステーションに指示が送られるので、該当ボックスのイタズラを防止するためにかけられた扉のロックが外れ、そこに返却できるという仕組みだ。