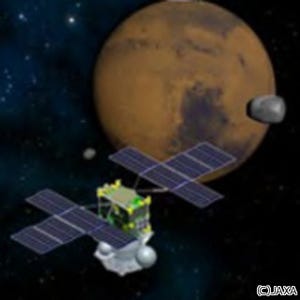宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所(ISAS)は2017年8月25日と26日に2日間にわたり、ISAS相模原キャンパスの施設公開イベント「相模原キャンパス特別公開2017」を開催した。毎年恒例のお祭にして、最先端の宇宙科学について、直接研究者とふれあいながら学べるこの催しは、今年も大勢の人々で賑わった。
今回は特別公開の展示や解説の中から、とくに気になったものを厳選し、3回に分けて紹介していきたい(第1回はこちら、第2回はこちら)。
第3回では、航空機のように何度も再使用できる「再使用観測ロケット」の最新情報と、ISASと民間企業が共同開発している小型ながら高性能なレーダー地球観測衛星について紹介したい。
ついに動き始めた日本の再使用ロケット
スペースXの「ファルコン9」ロケットや、ブルー・オリジンの「ニュー・グレン」ロケットに代表されるように、近年、ロケットを航空機のように何度も再使用し、1回あたりの打ち上げコストを少なくしようという取り組みが活発になっている。とくにスペースXは、すでに再使用打ち上げに2度成功し、また実際に約30%の低コスト化にも成功、顧客に提示する価格も10%引きにできているとされる。
このロケットの再使用化の波は世界中に波及し、この2社だけでなく、他の米国企業をはじめ、欧州や中国、インドなども開発を始めている。
一方で日本は、かつて再使用ロケットの開発では世界の第一線におり、2000年前後には小さな実験機「RVT」を開発し、実際に離着陸する実験も行っていた。しかしその後は足踏み状態となり、高度100kmの宇宙まで届くロケットや、人工衛星や人を打ち上げられるロケットへ発展することはなく、そうこうしている間にスペースXとブルー・オリジンに追い抜かれるという状況になった。
もちろん、研究・開発が完全に止まっていたわけではなく、エンジンを中心に地上で技術開発は続けられていた。2015年には宇宙まで届く再使用ロケットに使えるエンジンの試験が完了し、宇宙まで届く「再使用観測ロケット」を開発するめどが立ったことが発表された。
ISASは現在、衛星は打ち上げられないものの実験装置などを高度100km以上の宇宙空間に打ち上げられる観測ロケットを運用しているが、打ち上げごとに使い捨てている。そこで、この観測ロケットを再使用できれば、打ち上げコストが削減でき、実験の機会や頻度を増やすことができ、さらに将来の再使用ロケット開発にもつなげられるとが期待されている。
しかし、予算などの問題から、まだ実機は開発されていない。
今回の展示では、再使用観測ロケットそのものについてはまだ開発は動き出していないものの、その前段階となる再使用観測ロケットの"実験機"の開発についての発表が行われた。開発そのものは以前から明らかになっていたが、今回その実物大想像図が初めて公開された。
この実験機は、再使用観測ロケットよりも小さく、またロケットエンジンも再使用観測ロケットに4基積む予定のものを1基だけ積む。目標は高度数km~数十kmほどまで上昇して帰還する技術の実証にあり、すでに開発を始めており、来年度(2018年度)の打ち上げを予定しているとのことだった。
スペースXなどの他の再使用ロケットと比べた際の、ISASの再使用ロケットの技術的な強みは、「機体そのものが翼のように揚力を生み出せる形状をしているので、わずかながら滑空飛行できる」点だという。つまり帰還の際、着陸場所に向けて滑空飛行できるので、燃料を節約することができる。ただ、ファルコン9 ブロック5やニュー・グレンでも、胴体や小さな翼を使って滑空飛行することが考えられているため、「ちょっと苦しいですが……」という本音も聞かれた。
また、基幹ロケット(H3やその後継機など)の再使用化といった展開も、まだ実現の見通しはないという。
残念ながら、スペースXなどに比べるとまだ周回遅れの状況ではあるものの、少なくとも研究・開発が続いており、実験機の開発が進んでいることは明るいニュースではある。
|
|
|
|
|
再使用ロケットの実験機「RVT」。2003年に離着陸実験を行った |
開発中の再使用観測ロケットの実験機の実物大想像図 |
再使用観測ロケットの風洞模型(左)。機体そのものが翼のように揚力を生み出せる形状をしているので、わずかながら滑空飛行できる |
太陽電池とレーダーが一体化した小型レーダー衛星
大地震や豪雨、火山の噴火などの自然災害が発生したとき、被害状況を確認するため、地球観測衛星はすでに大きな活躍を果たしている。
しかし、人工衛星の軌道は決まっており、災害の発生直後に、すぐに被災地を撮影できるとは限らず、場合によっては1日以上待たねばならない場合もある。
その欠点を解消するため、「即応打ち上げ」というアイディアがある。災害などが発生した際にすぐさま衛星をロケットで打ち上げ、最適な軌道に投入し、迅速に観測を行うというもので、すでに米国や中国などで技術実証機が打ち上げられている。
この即応打ち上げを行う場合、開発や製造のしやすさや打ち上げやすさなどから、衛星は小型である必要がある。小型衛星にはあまり大きな観測装置が積めないので、衛星の性能が限られてしまうが、近年では電子部品の小型化が進み、望遠鏡とカメラで地表を撮影する光学センサを搭載する衛星については、100kgほどの大きさでも十分な性能をもつものが造れるようになった。
しかし、合成開口レーダーで地表を撮影するレーダー衛星は、大きなアンテナや大電力が必要なことなどから小型化が難しい。小型化できても性能が悪ければ役に立たない。一方で、光学センサは夜間や観測値の上空に雲がある場合には使えないため、レーダー衛星はこうした「即応打ち上げによる地球観測」という目的にとって必須でもあった。
この「小型ながら高性能、そしてすぐに打ち上げられるレーダー衛星」の実現という難題に、内閣府が進める「革新的研究開発推進プログラム」(ImPACT)のもとで、ISASと三菱重工、三菱電機、大学などが協力して挑んでいる。
この小型レーダー衛星の最大の特徴は、大きくてかさばるレーダーのアンテナを、太陽電池パドルと一体化させていることにある。多くの人工衛星がもつ太陽電池は、いくつかのパネルに分かれており、それらを折りたたんだ状態で打ち上げ、宇宙空間でぱたぱたと開いて展開するようになっている。これを利用し、小型レーダー衛星ではこの太陽電池のパネルの裏側にレーダー機器を搭載することで、機体のコンパクト化と軽量化を実現している。
ただ、単に太陽電池の裏にレーダーを貼り付ければよいというものではなく、さまざまな課題もあったという。たとえばレーダーのアンテナは、表面に突起があったり、展開した際にパネル同士のずれから歪みが生まれたりすると性能が落ちてしまう。そこでシンプルかつ高い精度が出せる展開方法が開発され、さらにパネル同士の隙間で発生するレーダーの電波の損失を小さくするための技術も開発された。
この小型レーダー衛星の質量は約130kgで、打ち上げ時(パドルを折りたたんだ状態)の寸法は1辺が約0.7mの立方体になる。レーダーに使うマイクロ波の周波数には、高い地上分解能を達成可能なXバンドを使い、分解能は高度600kmの軌道で3m、400kmで1mを目指す。
小型のレーダー衛星はイスラエルやドイツなどが得意としているが、100kg級で分解能1mという小ささと高性能さをもつ衛星はまだどこにもない。
また、衛星に使う部品にはITAR(米国の輸出規制)にひっかからないものを使っているので、事実上どこの国(中国など)のロケットでも打ち上げが可能な上に、さまざまな国へ衛星の輸出も可能となるという。
現時点では、2018年に実機の完成を予定しているという。具体的な打ち上げ予定などはまだないものの、将来的には即応打ち上げシステムとしての配備の他、十数機の衛星を打ち上げて軌道上に配備し(これをコンステレーションという)、つねに短い間隔で地表を観測し続けられるシステムの構築も目指しているという。これにより災害対応のほか、たとえば他国の港の動向を観測するなどし、経済状況や物流の動きを調べ、先物取引に利用するという応用も考えているという。
|
|
|
|
小型レーダー衛星の解説パネル |
小型レーダー衛星が目指すところと、他の同様の衛星との比較。小型のレーダー衛星はイスラエルやドイツなどが得意としているが、100kg級で分解能1mという小ささと高性能さをもつ衛星はまだどこにもない |
参考
・宇宙旅行に行きたいな再使用ロケット
・宇宙開発戦略本部 第15回会合 議事次第 : 宇宙政策 - 内閣府 ・でも曇でも地表が見れる小型レーダ衛星の開発
・革新的研究開発推進プログラム ImPACT: 研究開発プログラム: 白坂 成功PM
・オンデマンド即時観測が可能な小型合成開口レーダ衛星システム」
著者プロフィール
鳥嶋真也(とりしま・しんや)
宇宙開発評論家。宇宙作家クラブ会員。国内外の宇宙開発に関する取材、ニュースや論考の執筆、新聞やテレビ、ラジオでの解説などを行なっている。
著書に『イーロン・マスク』(共著、洋泉社)など。
Webサイトhttp://kosmograd.info/
Twitter: @Kosmograd_Info