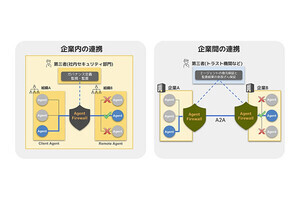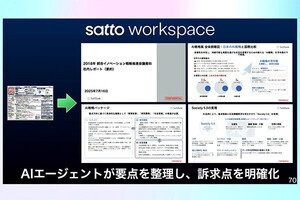ソフトバンクグループは、生成AIの活用に積極的な企業だ。これまで、さまざまな企業と提携を行っているが、米オープンAIと生成AIの共同出資会社を設立すると発表し、同社に約6兆円に上る出資を表明したことは記憶に新しい。
また、経済産業省および東京証券取引所、情報処理推進機構が選定する「デジタルトランスフォーメーション銘柄2025」(DX銘柄2025)において、DXグランプリに選定されている。
そこで、同社は社内業務にどのように生成AIを活用しているのか、IT統括 IT&アーキテクト本部 本部長 北澤勝也氏と、IT統括 IT&アーキテクト本部 IT CoE統括部 統括部長 澤田鉄平氏に聞いた。
IT統括 IT&アーキテクト本部は、会計などのバックオフィスのシステム、パソコンなどのOA機器のほか、全体的なシステム構成、アーキテクトを考えている部署だ。
生成AIを活用したCS業務の自動化
ソフトバンクの社内業務改革における生成AI活用で、最も大きなプロジェクトは、CS(カスタマーサポート)業務の自動化だという。これは、生成AIの活用により顧客の待ち時間の短縮と対応の均質化を図り、顧客満足度の向上を目指すものだ。
ソフトバンクのCSには1万以上の業務があり、このうち問い合わせ内容に対する案内や契約内容の照会、契約変更手続きなどの業務を中心に、生成AIを活用。LLM(Large Language Models:大規模言語モデル)が顧客の問い合わせ内容を判断して案内を行ったり、データソースから情報を収集したりして、最適な回答を行う。
「CSの自動化で生成AIを活用すれば、オペレーターが不要になります。人間より生成AIの方が賢いというところから始まったプロジェクトです。CSでは、案内、照会、変更、解約など、いろいろなことを行っていますが、生成AIで大幅に巻き取って、人件費を圧縮してきました」(北澤氏)
従来はLLMに顧客の要望を理解させ、その裏でワークフローを動かすフロー追従型を利用していた。しかし2024年2月から、顧客の問い合わせに合わせた形で自律したファンクションAPIを読み込むというLLM自律思考型を導入。
LLM自律思考型を採用することにより、従来は生成AIで対応できなかった意見(苦情/賞賛)、解約引き止め提案、トラブル時の解決策の提示、グループ内外への転送といったことも、生成AIで対応できるようになったという。
生成AIによるチャット対応にまつわる課題をどう解決したか?
ただ開発においては、音声の相槌、割り込み(ユーザーが発話中に生成AIを停止)の処理に苦労したという。
「お客様が『はい』と言った場合に、承諾の「『はい』なのか、相槌の『はい』なのか区別がつきません。テキストベースでやっているのでこの解釈が難しく、GPT-4o(OpenAI)でRealtimeAPIが対応できる予定だったので、一旦、音声による開発は中断し、チャット形式で回答品質の評価を試しました」(澤田氏)
当初、生成AIによるチャット対応で解決できた問い合わせは6割程度で、サービスインの条件に達しなかったという。原因は、顧客の意図解釈や要件の深掘りができないことにあった。
「オペレータを生成AIに置き換えるには、お客様が何を言いたいのかを理解することが必要です。お客様からの問い合わせは『携帯が使えない』から始まります。生成AIは、人のサポート、例えば検索したり、情報を集めたりすることにおいては有効ですが、人を生成AIに置き換えるという話になると、『携帯が使えない』と始まる問い合わせから用件を深掘りしないといけません。オペレーターであれば、お客様に寄り添い、質問を繰り返して正しい答えを返しますが、今の生成AIは一番優先順位が高いと思われる結果を回答します。そのため、質問内容によって、1位、2位、3位の順序が変わってしまいます。これを解決するには、人間の所作を体現する必要があります。一問一答を実現するためには、AIの前に人の振る舞いが再現できないと、オペレーターの代わりはできないということになりました」(澤田氏)
そこで、オペレーターが応対している音声ログをLLMに学習させ、オペレーターの状態遷移(この問い合わせが来たら、こう答える)を、すべてアクション化し、業務フローを内部で作って、問い合わせごとの対応をアクション化したという。
以前は、iPhoneのバージョンを聞き、可能性の高い解決策を提示していたが、新しいバージョンのLLM自律思考型では、iOSのバージョンを追加で質問したり、データの保証はできないといった免責事項を説明したりすることも可能になった。これにより、オペレーター業務を生成AIに置き換えられるようになったという。
「生成AIに人の所作を加えることによって、用件の深掘りが可能になりました。アンケートでは、多くのお客様がAIだと思わなかったと答えています。チャットの応答品質が上がってきているので、今後は、音声対応をプラスした形でオペレーターを減らしていきます」(澤田氏)
SmartAI-Chatで社員の生成AI活用をサポート
ソフトバンクでは、OpenAIのGPT以外にも、GoogleのGeminiといった生成AIを全社員が利用している。同社は、生成AIの業務活用タイプについて「助言型」「助手型」「変革型」の3つに分類できると考えているという。
助言型は、本人がやりたいことへのアドバイスをもらうという使い方で、助手型は、自分ができないことを生成AIにやってもらう。
「例えば、動画を作ることはこれまで他人にお願いしていましたが、生成AIで動画も作れるようになっているので、お願いすれば動画も作ってもらえます。変革型はAI使うことを前提に業務を変えようという取り組みで、前述したCSサポートが該当します」(北澤氏)
同社は、生成AI活用のロードマップを助言から助手、変革へと下から徐々に積み上げていく形で描いている。
そして、ソフトバンクは2023年5月、業務での生成AI活用を推進するため、全従業員約2万人を対象にソフトバンク版AIチャット「SmartAI-Chat」の提供を開始した。SmartAI-Chatは、セキュアな環境で構築された社内向けAIサービスで、文章の作成や翻訳などの既存業務の効率化や営業・マーケティング領域での企画・アイデアの立案など、あらゆる業務に応用することを目指している。
また、「ソフトバンクAI倫理ポリシー」に基づき、AI倫理およびガバナンスに特化した「AIガバナンス基本規程」を新たに制定。AIを用いたサービスの適正な開発や提供、管理、運用の方針を定めて、より安全・安心なAIの活用を推進している。
SmartAI-Chatの利用でパソコン交換時に追加要員が不要に
さらにSmartAI-Chatは、従業員のパソコンや社内業務に関する手続きや疑問に対応するといった社内向けITヘルプデスクの役割も担っている。
これは、社内向けITヘルプデスクのQ&Aデータ(質問数約3万6,000およびそれにひも付く回答)を連携させることで、自社に特化した生成AIの活用を実現したもの。
「社員全員が見られる情報を厳選してSmartAI-Chatに登録しました。これにより、例えばパソコン故障時の対処手順や会議室の予約方法などを即座に調べられます。人事情報は閲覧対象外ですが、各種人事手続きの進め方など、全社員が共通して必要とする情報は参照可能です。 SmartAI-Chatを活用すれば、全社員の困りごとを迅速に解決できる環境を提供しています。」(北澤氏)
同社では毎年一定数の社員用のパソコンの交換を実施するが、その時期は問い合わせが集中するため、従来はサポート要員を数名増員して対応していた。しかし、SmartAI-Chatを導入した昨年度は追加要員を確保することなく、既存体制で円滑に対応できたという。
こういった社員サポートの改善はどの企業においても課題になっているが、Q&Aのヒット率を高める上で工夫する点を聞いたところ、澤田氏は目的に沿ったデータのみを学習させる点を挙げた。
「CS自動化で説明したとおり、お客様が要望している回答を確実に提示しないといけません。世の中ではビッグデータやデータレイクなど、データが多いほうが優位と考えられていますが、データを全部入れてしまうと、一問一答において良い回答を得られないことがわかっています。ある程度、目的に沿ったデータをピックアップして入れることが必要で、ここには人の知恵が必要になります。ただ、これが非常に難しく、トライ&エラーで進めるしかないのが現状です」(澤田氏)
なお、現在も業務を生成AIに置き換える作業が進行中であり、各事業部から置き換えたい業務候補をピックアップしてもらっている。今後は、これらの業務における実現可能性や削減効果などを考慮しながら、優先順位を付けて実施していく予定だという。