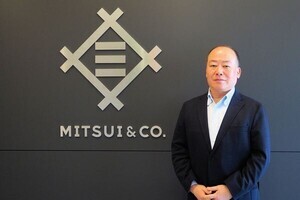KITZ(キッツ)は、総合バルブメーカーとして、一般家庭向けから、工場・プラント向けまで、さまざまなバルブの製造・販売を行う企業だ。バルブの種類は9万種も超えるという。
同社のIT部門(IT統括センター)は、予実管理からプロジェクト管理、戦略策定など部門全体を統括するIT戦略企画部と、営業、生産、設計・開発、経理、人事といった各業務システムの開発、保守、運用を行うビジネスシステム部、そして基盤となる技術のほか、パソコン、クラウド、ネットワークなどのインフラを管理するITインフラサービス部の3つに分かれており、総勢約50名の組織となっている。
新たな成長市場へのシフトに向けDXを推進
同社は、2020年からDX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組んでいるが、その背景には市場環境の変化があるという。
「われわれは、工業用バルブでは石油化学市場向けが強いのですが、石油関連もあと10年持つか、持たないかという市場だと思います。このまま何も変わらなければ、会社の業績が落ちていくことは目に見えているため、成長が期待できる市場、新規の市場をもっと伸ばしていこうとする段階に来ています」と語るのは、同社 執行理事 CIO/IT統括センター長の石島貴司氏だ。
こうした世の中の動きを受け、2022年からスタートした同社の中期経営計画のテーマは、「流れを変える」となっている。
「新たな成長市場にシフトしようとすれば、その市場のマーケティングをしっかり行って新製品を開発し、世の中に出していかなければなりません。お客様もこれまでとは異なる層になるので、顧客開拓もしなければなりません。納期や生産の仕方も変えないといけない点を考慮すると、新たな市場に出ることはそんなに簡単ではありません。会社の中のあらゆることを変えていかないと、競合に勝って成長できないと思っています。デジタルの力で現状を効果的かつ効率的に変えていくためにDXを始めたのが、2020年となります」(石島氏)
最初の取り組みはITツールの一新
同社がDXを進める上で最初に取り組んだのが、普段、社員が使っているITツールの一新だ。
「DXを始めるにあたって、まず、やらなければならなかったのは、徹底的な効率化と会社の空気を変えることでした。そのためにITツールを一新し、表に出ていなかった情報を出し、従業員に情報武装させることを通じて、会社の風土を変えてきました」(石島氏)
この取り組みは、あまりに大きな変化のため、最初は疑問の声もあったが、コロナ禍により、変化を受け入れざるを得なくなったという。
「デジタル上でいろいろなことを変えていったところに、新型コロナウイルスの感染が拡大したので、新たなITツールを使わざるを得なくなりました。これらツールにより会社の中の風土も急激に変わりました。従業員が自分たちで工夫すれば、どんなに難しい状況も乗り越えられるという経験をしたことにより自信が付き、変わらなければいけないことを痛感したと思います」(石島氏)
DXを通して業務効率化を実現
DXと会社の変革を進めていくにあたり、経営層からは変革をするための工数を捻出するよう、業務効率化の指示があった。同社は2021年にコンサルティングを受け、全部門の工数の可視化を行ったが、その結果、どの部門も8割程度がルーチンワークだったことがわかったという。
「2割程度の工数しか改善に使えていないので、業務を効率化して、ルーチンワークをできるだけ減らし、新しいチャレンジや変革に工数を使えるように取り組みました」(石島氏)
具体的には、徹底的にペーパーレスを図って作業スピードを上げ、データが蓄積されるようにした。そして、そのデータを分析し、データドリブンで仕事を進めていくように変わることを期待したという。
「ペーパーレス化は目標の半分ほど終わっていて、スタッフ部門についてはペーパーレス化が完了しています。残りの半分は製造現場です。製造現場ではトヨタと同じかんばん方式を採用していますが、いまだに紙かんばんを使っていたり、組み立てをするための指図情報を紙で行っていたりします。今、これらのデジタル化に取り組んでいます。検査も、結果を紙に書いて後で転記していましたが、デジタル化してiPadで直接入力するように変えました。あと2年ほどで、ほぼ紙はなくなると思います」(石島氏)
ペーパーレス以外にも、業務効率化に向けRPAを活用した自動化も行った。教育とサポートのスキームを作って、開発者を全社で増やし、現在、300人以上の業務ユーザー開発者がいるという。
また、DXを推進する部隊として、社長直下に各組織から代表者を集め、社員の約2割が参画するDXタスクフォースチームを構築し、さらに、ビジネストランスフォーメーション(BX)推進部を設置。この部署で、DX全体を取りまとめる役割を担うと同時に、生産、設計開発、営業、人事、経営といった組織ごとのワーキンググループを構成した。
各ワーキンググループでは、現在の課題と2030年にどうあるべきかという未来の姿を議論しており、その計画に基づいてシステム化が行われている。