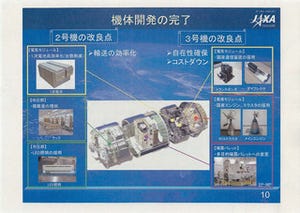宇宙航空研究開発機構(JAXA)は2020年8月20日、宇宙ステーション補給機「こうのとり」の最終号機となる9号機を、計画どおり大気圏に再突入させた。機体は燃え尽き、任務を終了。2009年から始まった、国際宇宙ステーション(ISS)への補給物資の輸送ミッションをすべて完遂した。
「こうのとり」は日本が苦難の末初めて開発した、有人宇宙施設に飛行・接近する宇宙機であり、信頼と実績を少しずつ積み重ねつつ、ISSの運用・利用に欠かすことができない重要な役割を担ってきた。
また、小型回収カプセルの搭載や無線LAN伝送など、今後の有人宇宙活動の発展につながる新たな技術実証も実施。そしていま、新型の補給機「HTV-X」の開発が進んでいる。
本連載では、「こうのとり」開発の経緯から、9号機までのミッションの歩み、そしてHTV-Xの概要と展望について、4回に分けて取り上げる。
宇宙ステーション補給機「こうのとり」とは?
「こうのとり」は、国際宇宙ステーション(ISS)に補給物資を運ぶために開発された、無人の補給機である。「こうのとり」は愛称で、正式には「HTV (H-II Transfer Vehicle)」と呼ばれる。
機体は全長約9.8m、直径約4.4mの円筒形をしており、その形状や、また機体を覆う断熱材が金色に輝いていることもあって、よく缶ビールなどにも例えられる。機体は3つの区画に分かれており、前方から、補給物資を搭載する「補給キャリア」、機体の制御を行う「電気モジュール」、そして軌道や姿勢の制御を行うためのエンジン(スラスター)を積んだ「推進モジュール」の順に並んでいる。
また補給キャリアは、搭載する物資の種別によって、ISSの船内で使用する物資を運ぶための「与圧部」と、船外で使用する物資を運ぶための「非与圧部」の2区画によって構成されている。最大で6tもの補給物資を載せることができ、機体も合わせた打ち上げ時の質量は約16.5tにもなる。
「こうのとり」が開発された目的は、大きく2つある。ひとつは、ISSを運用するための、日本の分担義務の遂行である。ISS計画を進めるにあたって定められた「国際宇宙基地協力協定」においては、日本人宇宙飛行士がNASAの宇宙船でISSに向かう際などの経費は、実費ではなく、補給物資を輸送することで、すなわちバーター(物々交換)で支払うことになっている。
もうひとつは、日本の宇宙開発技術の発展である。「こうのとり」によって軌道間輸送手段を確立するとともに、有人宇宙機の実現も視野に入れた、将来の宇宙開発の展開に必要な技術を蓄積するという意味合いがあった。
「こうのとり」を打ち上げる「H-IIB」ロケットの開発、打ち上げによるロケット技術の成熟化も、そのひとつに含まれる。また、「こうのとり」開発当時は日本のロケットの需要が少なかったことから、"宇宙の定期便"であるHTVを打ち上げることで、需要を作り出し、ロケット技術や産業を維持する、いわゆるアンカーテナンシーとしての役割もあった。
NASAからの叱咤と苦難
のちに「こうのとり」と呼ばれることになるHTVは、1995年から概念設計が始まり、1997年に開発に着手した。日本にとって、有人の宇宙ステーションに接近、結合する宇宙機の開発は初めてのことであり、最初は無人の人工衛星と同じ基準で設計していたこともあって、NASAからは「宇宙飛行士の命を何だと考えているんだ」、「HTVが来ないことがISSの安全」、「米国の物品は載せられない」などと言われたこともあったという。
なかでも物議を醸したのは、ISSにランデヴーし、結合する方法である。前述のように、日本は有人機を造った実績がなかったが、他国からドッキング・システムを購入するのは高価で現実的ではなかったため、自主開発することを決定する。
その結果、「ランデヴー・キャプチャー方式」と呼ばれる仕組みが生み出された。まず、高度と距離を合わせながらISSに近づいたのち、ISSの下約10mの位置で、静止するかのように並んで飛行。そこをISSの宇宙飛行士が操作するロボット・アームで捕まえ、ドッキング・ポートに結合する。他国の宇宙船や補給船は、自律的にISSに近づいたあと、そのまま突っ込むようにしてドッキングする方法が主流であり、このような方法は日本独自のものだった。
ランデヴー・キャプチャー方式が生み出された背景には、「スペース・フライヤー(SFU)」の存在があった。SFUは日本が1995年に打ち上げた宇宙機で、宇宙実験を行ったのち、スペース・シャトルに乗った若田光一宇宙飛行士が操るロボット・アームで捕まえて回収された。日本にとって、有人機と無人機を結びつける、ほぼ唯一の実績ある方法であった。
また1998年には、技術試験衛星VII型「きく7号(おりひめ・ひこぼし)」による、無人のランデヴー・ドッキング試験にも成功。これにより実証された技術もHTVへと活用された。
開発初期からHTVにかかわる、HTV技術センター長の植松洋彦氏は、8月21日の記者会見において、「ランデヴー・キャプチャー方式は、よく言えば斬新、悪く言えば突拍子もないものだった」と当時を振り返った。有人分野において、米国からの信用はない状態だったこともあり、NASAを説得し、納得させるのに非常に苦労したという。
-

「こうのとり」をISSに結合する方法として採用されている「ランデヴー・キャプチャー方式」。ランデヴーしてISSに対して静止した「こうのとり」を、ロボット・アームで捕まえる。写真は2019年、8号機を分離したところ (C) NASA
そのいっぽうで、保守的な設計を採用した部分もある。かつてHTVプロジェクトチームのサブマネージャーを務め、現在JAXA有人宇宙技術部門長を務める佐々木宏氏は、太陽電池を例に挙げた。
HTVの太陽電池は、他の衛星や宇宙船でよく見られる、翼や、あるいはカヌーのオールのような形をした展開式の太陽電池パドルではなく、機体の表面に貼り付ける形式が取られている。
太陽電池パドルの場合、根本を回転させ、太陽のある方向を向くように角度を変えることで、大きな発電量(効率)を得ることができる。いっぽう、貼り付ける形式の場合、どこかの太陽電池には太陽光が当たるものの、機体の影になって当たらない場所も生まれるため、発電量(効率)は落ちてしまう。
佐々木氏によると、HTVが貼り付ける形式を採用したのには、HTVの開発初期にあたる1996年に、地球観測プラットフォーム技術衛星「みどり」で、太陽電池パドルの根本の配線が切れたと推定されるトラブルが発生したことが理由だという。
万が一太陽電池が壊れ、電力が作り出せなくなると、ただ補給機を失うだけでなく、物資が届かなくなることで、ISSで生活する宇宙飛行士の命に関わる事態にもなりかねない。そこで、効率が落ちることは承知のうえで、表面に太陽電池を貼り付け、パドルの展開に起因するトラブルが起こるリスクをなくしたのだった。
(次回に続く)
参考文献
・JAXA | 宇宙ステーション補給機「こうのとり」9号機(HTV9)の大気圏への再突入完了について
・宇宙ステーション補給機「こうのとり」9号機(HTV9)ミッションプレスキット
・宇宙ステーション補給機「こうのとり」9 号機(HTV9)ミッションプレスキット 別冊 「こうのとり」のあゆみ
・平成21年度宇宙環境利用の展望 - 第7章宇宙ステーション補給機(HTV)技術実証機の飛行結果
・宇宙ステーション補給機技術実証機(HTV1)プロジェクトに係る事後評価について平成22年10月18日(A改訂)平成22年9月21日宇宙航空研究開発機構有人宇宙環境利用ミッション本部HTVプロジェクトマネージャ虎野吉彦