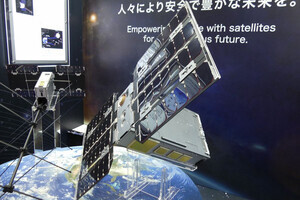ソフトバンクは2025年6月26日、「空飛ぶ基地局」とも呼ばれるHAPS(High Altitude Platform Station、成層圏通信プラットフォーム)によるプレ商用サービスを、2026年に開始することを明らかにしました。ですがHAPSとして使用する期待は、従来ソフトバンクが開発を進めてきた太陽光を用いて飛行するHTA(Heavier Than Air)型ではなく、ヘリウムガスによる浮力を用いたLTA(Lighter Than Air)型を採用しています。一体なぜでしょうか。→過去の「ネットワーク進化論 - モバイルとブロードバンドでビジネス変革」の回はこちらを参照。
HTA型からLTA型に切り替えて事業化
KDDIの「au Starlink Direct」の提供開始によって、低軌道衛星とスマートフォンの直接通信が注目を集めている2025年ですが、もう1つ、上空から通信エリアをカバーする取り組みとして進められているのがHAPSです。
HAPSは「空飛ぶ基地局」とも呼ばれ、成層圏を長期間飛行して地上のスマートフォンなどと直接通信するもの。低軌道衛星は高度約2000km以下の軌道を周回していますが、HAPSは高度約20kmと、それよりはるかに低い場所を飛行することから、端末との距離がより近い分、低軌道衛星より遅延も少なく一層の高速大容量通信も可能とされています。
ただ一方で、高度が低い分1基でカバーできるエリアが小さいのに加え、飛行させる必要があることから、既に実績のある衛星と比べ実現が難しいとされてきました。ですがここ最近、そのHAPSのサービス提供に向けた動きが相次いでいるようで、大きな動きを見せた1社がソフトバンクです。
実際、ソフトバンクは2025年6月26日にHAPSによるプレ商用サービスを2026年に開始すると発表しています。ソフトバンクは早い時期からHAPSの事業化に取り組んでいる先駆的存在の1つであり、これまでは飛行機タイプで太陽光を用いて長期間飛行するHTA型のHAPSに関する研究開発に力を入れてきました。
しかし、今回商用サービスに用いるHAPSはHTA型ではなく、ヘリウムガスによる浮力を用いて成層圏を飛行する、LTA型の機体。しかも、それを開発したのはソフトバンクではなく米国のSceyeという企業であり、ソフトバンクは同社に出資することを発表。その上で同社のLTA型HAPSによる日本国内でのサービス展開に係る独占権を取得し、サービスを実現するとされています。
実はソフトバンクもともと、2029年の商用サービスを目指すとしており、そこに照準を合わせてHTA型のHAPSに関する要素技術開発を進めてきました。それがなぜ、LTA型のHAPSを用い、3年も前倒しして2026年のプレ商用サービスを打ち出すに至ったのでしょうか。
NTTドコモも2026年にサービス予定、企業間競争が激化
そこには複数の要因が働いていると考えられますが、1つ目の要因は、LTA型HAPS機体の方が早期サービスを実現しやすいことのようです。
HTA型は飛行速度が速く目的地により素早く到達しやすいメリットがある一方、LTA型は浮力で上空により素早く到達でき、なおかつ積載量が大きいことから、大きな基地局設備などを搭載する上で優位性があります。それゆえソフトバンクではHTA型の開発に注力しながらも、LTA型での展開も検討していたそうです。
ただ、LTA型の機体は進化が想定より早く進み、HTA型と比べ3年早く実用化の目途が立ったことから、そちらを採用するに至ったとのこと。加えてLTA型は飛行機タイプではないので、HTA型とは違い航空機の型式認証が必要なく、国土交通省と協議して新しい制度での運用が可能になったことも、早期のサービス実現には大きく影響しているようです。
そしてもう1つ、より大きな要因となるのが競合の動向です。HAPSの開発に力を入れている国内通信企業はソフトバンクだけではありません。
実はNTTドコモもHAPSの事業化に力を入れており、同社はAirbus Defence & Space子会社でHAPSの機体開発を手掛けるAALTOと2024年に資本業務提携を締結。AALTOのHTA型HAPSを用い、2026年に日本国内でHAPSによるプレ商用サービスを提供する予定であることを明らかにしています。
しかし、これが実現した場合、ソフトバンクからしてみればHAPSの事業化で、競合に3年も大きく先を越されることになります。それだけにソフトバンクも、まだ事業化に時間がかかるHTA型から、LTA型による早期の商用サービス実現へと大きく舵を切り、競合に対抗する必要があったのではないかと考えられます。
もっとも、現状のHAPSはまだ日本全国を自在に飛行できる訳ではありません。とりわけHTA型は太陽光をエネルギーとする関係で緯度の制約があり、北に行くほど飛行時間が短くなってしまうことから、NTTドコモが提供するという2026年のプレ商用サービス時点では、島しょ部など日本の南のエリアの一部での提供に限られると見られています。
LTA型はヘリウムガスを用いることから北側飛行にそこまで制約は厳しくないようですが、それでもやはり一定の制約はあるようです。それゆえ2026年時点では常時特定のエリアをカバーするのではなく、で空からエリアカバーできることを生かした、災害対策用のソリューションとしての展開を考えているようです。
双方ともにさまざまな課題を抱えてはいますが、企業間の競争によってHAPSのサービス実現時期が近付いていることは確かでしょう。地上の影響は受けない多様な通信手段が提供されることは、山岳地帯や島しょ部が多く、自然災害も多い日本においては大きなメリットとなるだけに、今後の展開が大いに期待されるところです。