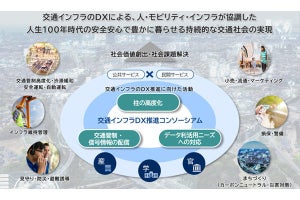米国のファンドであるDigital Bridgeに買収されたインフラシェアリング大手のJTOWER。買収された同社の現状と今後の戦略とはどのようなものなのでしょうか。2025年6月6日に実施された戦略発表会から確認してみましょう。→過去の「ネットワーク進化論 - モバイルとブロードバンドでビジネス変革」の回はこちらを参照。
買収でJTOWERは長期的視野での投資が可能に
複数の携帯電話会社が設備を共用してネットワークを整備する「インフラシェアリング」。国内でその大手となっているのがJTOWERです。
JTOWERの現在の事業は、主に大規模ビルや商業施設などの屋内に向けたインフラシェアリング設備の整備・運用です。しかし、通信規格が4Gから5Gへと移り、設置する基地局の数が大幅に増えていることに加え、政府主導による携帯電話料金引き下げの影響を強く受けて携帯各社が業績を悪化させ、インフラ整備にかける投資を減らしインフラシェアリングを活用する傾向が強まっています。
そこでJTOWERは屋外のインフラシェアリングにも力を入れるようになり、NTTドコモやNTT東日本・西日本などから合計で7232本の通信鉄塔を取得。自社でも130本の鉄塔を新設しており、2024年10月にはNTTドコモから取得した鉄塔によるインフラシェアリング運用を開始。屋外インフラシェアリング事業を本格化させつつあるようです。
そうした中にあって大きな出来事となったのが2024年8月、米国の投資会社であるDigital BridgeがJTOWERを買収すると発表したこと。NTTグループから通信鉄塔を譲り受ける契約して間もない時期の買収だけに、経済安全保障などの側面からも疑問視する声があったのは確かですが、それでも同社が買収を受け入れました。
今後大きな需要が見込める屋外インフラシェアリングの事業強化を図るうえでは、長期的かつ大規模な投資が必要だったからでしょう。Digital Bridgeはデジタルインフラに多くの投資をしている企業で、JTOWERのようなインフラシェアリングを手掛ける「タワーカンパニー」と呼ばれる企業などに対して実績があります。
一方、JTOWERはDigital Bridgeに買収される以前は上場企業で、先行投資が響いてここ最近は赤字決算が続いていたことから、株価が低迷。市場の理解が得られない状況では資金調達も難しく、長期的視野での戦略が立てづらい状況にありました。
そこでDigital BridgeがJTOWERを買収し、非上場化したことで、JTOWERは短期的な業績が問われなくなり、長期的視野での戦略が立てやすくなったといえます。それに加えて同社からの長期的な投資と、これまでのタワーカンパニーへの投資で得た豊富な知見を得られることが、JTOWERにとって大きなメリットに働くと見ているようです。
屋内外の設備老朽化に商機
実際、JTOWERはDigital Bridgeから資金を得て、今後5年間で総額1000億円の投資機会を見込むとしています。その具体的な取り組みの1つとなるのが、現在の主力事業である屋内のインフラシェアリングの導入施設を拡大することです。
国内では4Gの時代まで、エリアや通信品質が競争上大きな要素となっていたことから、屋内のネットワーク対策も各社が独自に進めていました。しかし、現在ではそれら設備が古くなり入れ替えが必要となりつつある一方、携帯各社はインフラ投資を削減しているため、インフラシェアリングでそれら設備を巻き取ってほしいという声が増えているのだそうです。
JTOWERではそうしたニーズに対応し、設備入れ替え時にインフラシェアリング設備の導入を進め、事業拡大につなげたいようです。
2つ目は、新しい装置やサービスを開発してシェアリングできる領域を増やすこと。具体的には、携帯各社の新しい技術や設備に対応する開発体制も強化し競争力強化を図る考えのようです。
例えばここ最近、携帯各社は基地局などの無線設備をオープン化する「オープンRAN」への対応を進めていますが、JTOWERではそうしたオープンRANに対応した5Gの共有無線機を開発したことを発表。
これによって携帯各社は、従来のインフラシェアリング設備では設置が必要だった無線機(RU)の設置が必要なくなり、建物のスペースや消費電力を削減できるとしています。
-

2025年6月6日に発表したオープンRAN対応の5G共用無線機。携帯4社の5Gのサブ6に対応した、オープンRAN対応の設備となり、無線機も共用できることから整備にかける手間やコストだけでなく、設備側の場所と消費電力も削減できるという
3つ目は、とりわけ地方を中心とした屋外の鉄塔設備の老朽化に対応することです。既に多くの鉄塔が建設してから10~20年の歳月が経過し老朽化が進む一方、今後携帯各社のコスト削減に加え、人手不足などによって今後鉄塔の維持管理が難しくなると見られています。それゆえJTOWERでは、将来的な鉄塔の統廃合も含め、鉄塔の維持管理を担い持続可能なインフラ運用に向けた体制を強化するとのことです。
そしてJTOWERでは、屋内のインフラシェアアリングで今後5年間のうちに、現在3倍規模となる累計2000件の導入実績を目指すほか、屋外のインフラシェアリングでは中長期的に鉄塔が現在の8万本規模から6万本規模に統廃合が進むと見て、その半数となる3万本の運用ができる体制を目指しています。
-

JTOWERでは屋内のインフラシェアリングを今後5年で現在の3倍規模にするとともに、屋外のインフラシェアリングでは将来的に鉄塔が6万本に減少すると見て、その半数を運用できる体制を整えることを目標にしている
資金面での課題をクリアして屋内だけでなく、屋外のインフラシェアリングの事業化を推し進める体制が整ったJTOWER。
しかし、屋外インフラシェアリングでは、屋内では比較的影響が少なかった自然災害への対策など、これまでにはない取り組みが求められることもまた確か。そうした課題をいかにクリアして携帯電話会社などから信頼を獲得し、目標達成に結びつけられるかが今後大きく問われる所ではないでしょうか。