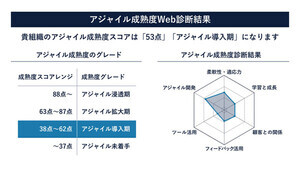お菓子のマシュマロが名前に入るのでどこかふざけた感じがするかもしれませんが、「マシュマロ・チャレンジ」はチームビルディングや仕事の進め方について学ぶ良い機会を提供します。実際に、大手企業でも取り入れられています。YouTubeを見ると、Googleで実施されている様子もあります。
筆者は何度もマシュマロ・チャレンジの経験があり、企業向けのファシリテーションもしています。いつも、大笑いが起きます。今回はマシュマロ・チャレンジのやり方や、少しネタバラシ的にその学びについて解説したいと思います。
マシュマロ・チャレンジをやってみよう
マシュマロ・チャレンジは名前のとおり、マシュマロを使ったチーム戦のリアルなゲームです。ルールは簡単で、4名ほどが1チームになりマシュマロのタワーを作ります。制限時間内に最も高いタワーを作ったチームが勝利です。ですので、最低でも3チームは欲しいです。
日本マシュマロ・チャレンジ協会によると、準備するものは以下の道具です。
●乾燥パスタ:20本(1.7mm推奨)
●マスキング(紙)テープ:90センチメートル
●ひも:90センチメートル
●マシュマロ:1つ(予備にもう1つ)
●はさみ:1つ
そして、高さを測るメジャーと、時間を計るストップウォッチが必要です。1位のチームに何か"おかし"な賞品をプレゼントするのも良いでしょう。写真を撮る人をお願いしておき、記録に残すのも良いと思います。笑顔の写真がいっぱい撮れます。
マシュマロ・チャレンジ詳しいルールは、自立可能なタワーを18分で立てるというものです。18分経過した時点でタワーの高さを計測をしますが、計測の間もタワーは自立している必要があります。
タワーのてっぺんにはマシュマロを置きます。マシュマロは切ってはだめですが、パスタを突き刺すことはできます。足場はテープで固定できません。パスタやテープやひもは、切ることも折ることもできます。これだけです。
スタートの前に「世界記録は99センチメートルだ」と言って、競争心をあおっておきます。さて、ゲーム・スタートです。
18分間のタワーを立てる作業が終わったら計測をして、各チームの成績を発表します。その後で、学んだことをチーム内で話してもらい、順番に共有してもらいます。
【ネタバレ注意】マシュマロ・チャレンジで勝利するチームの特徴は?
みなさんは、マシュマロ・チャレンジで勝つチームの特性は、どのようなものだと考えますか?
きちっと作業プランを立てるチーム
アーキテクチャを考えて作業を始めるチーム
適当に始めるチーム
チームをリードする人の性格が、その特性によく反映されます。実は、マシュマロ・チャレンジで勝利するチームの大半は、適当に早く作業を始めるチームなのです。とりあえず作業を開始して、試行錯誤を繰り返していくことが、勝利への鍵になります。そうです、まさにアジャイルアプローチです。
多くの参加者にとって、マシュマロ・チャレンジは初めての経験です。正解がないまま、あれやこれやと考えても机上の空論になってしまいます。そのうちに時間がなくなってきて、焦るのです。小さいものでもよいので早い時間にタワーを立てておけば、安心感も生まれますし、そこからの発展も簡単です。デザイン思考的に、最初の小さな成功を早い段階で作るのです。失敗を恐れず、チャレンジする姿勢が大事です。
忘れてはいけない大事なことは、もちろん、作業分担です。4名がどのように作業を分担するかを決めて、コミュニケーションを密に進めていけば、時間が限られる中での作業効率が上がります。コラボレーションが大事だということです。
ルールを再度読んでいただきたいのですが、勝つのは全チームの中で一番高いタワーを立てることであり、世界記録を作ることではありません。ですから、他のチームの様子を見て、それよりも高いタワーを立てれば、わずか10センチメートルのタワーでも勝てるかもしれません。作業に夢中になり環境を見ない=競合を無視するのです。これも実ビジネスでありがちですよね。
このマシュマロ・チャレンジは、限られた素材=資源から結果を出す必要があり、チーム全体の創造力も要求されます。あなたも、マシュマロ・チャレンジをやってみようと思いましたね?
筆者は、最後に関連する2冊の書籍を紹介して、フォロー学習を促進するようにしています。
『根性論や意志力に頼らない 行動科学が教える 目標達成のルール』(ディスカヴァー・トゥエンティワン 著者:オウェイン・サービスら)