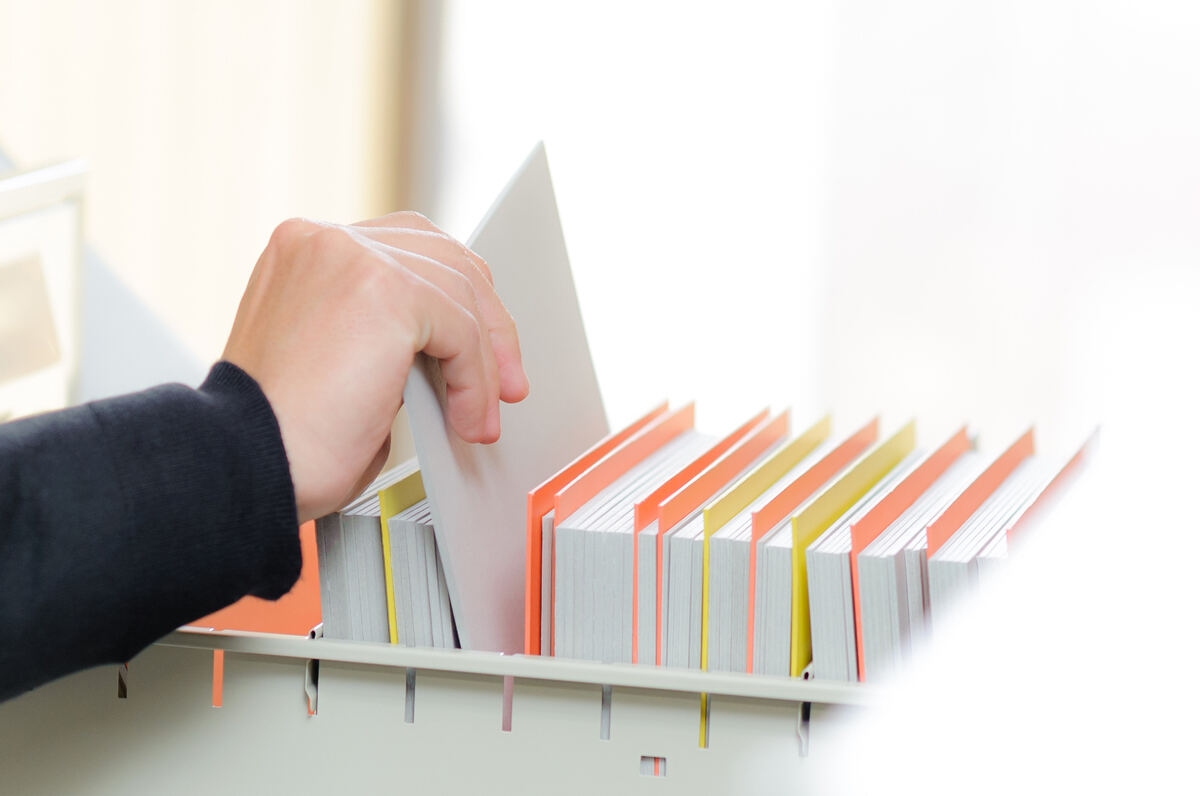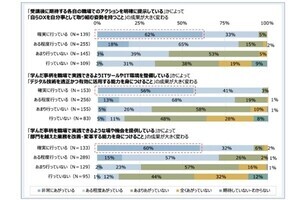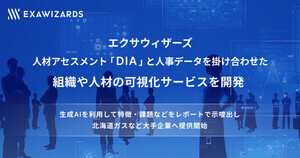リーダシップの有名な手法である「シチュエーショナルリーダシップ」では、人がパフォーマンスを出す要素としてスキルとモチベーションがあるとされます。筆者は、このスキルは大きな定義で、さらにスキルと知識に因数分解できると考えています。今回は、このうちの知識、英語でいう"Knowledge"について解説します。
「知識」は引き出してこそ
筆者がなぜスキルと知識に分けているかというと、そこには違いがあるからです。また、違いを明確にした方がそれぞれを向上できるからです。知識とは、特定の物事や分野、情報について「知っている・理解している・引き出せる」状態のことを指す際に用いる言葉です。一方でスキルは、知識として知っていることに加えて、行動に移せる状態を意味します。こう書くと、違いがお分かりいただけますよね?ここで、筆者が知識として定義している部分で「引き出せる」状態というのも大変重要なことです。単に知っている状態では、知識の無駄な蓄積でしかないからです。
筆者はかなりの知識オタクです。趣味ではギターが大好きで、いまだに『ヤングギター』や『ギターマガジン』を毎月購入して、知識を深めています(ヤングではないですが)。こんな筆者の頭の中にある知識のイメージは、「引き出し」です。知ることによって引き出しに大切なコトを保存します。そして、状況に応じて、必要な知識を引き出しから出して、利用します。最近ではありがたいことに、「ロジックの人」と言ってもらえる機会が多いのですが、これは筆者の引き出しに特定の方法論の知識が保管されていて、必要なときに使っているからだと認識しています。
そもそも、英語"knowledge"の語源はなんでしょうか?調べてみると、「古英語の『cnawan』(知る)と『cnawlecce』(知識)に由来する。これらの言葉は、さらに古いゲルマン語の『knew-』(知る)という語根から派生している。時代を経て、現代英語で「knowledge」という形になった』とのことです。知るという「Know」の語源からの派生のようですね。
筆者が以前SAS Instituteで働いていたときのブランドの標語が「Power To Know」でした。「知る力」なんて、なんといいこと言うと思っていました。アナリティクスをうまく表現しています。でも今は、知るだけではだめで、利用につながる必要があると思います。
知識を得るための2つの行動
みなさんの仕事で、必要な知識って何がありますか?ベンダーの社員であれば、製品の知識、お客様の業界知識、お客様の企業の知識、パートナーの知識、ビジネス遂行に必要な知識など、多様な知識があると考えます。以前も記載しましたが、グローバルベンダーではロールごとにイネーブルメントチームや担当があり、ビジネスに必要な知識を伝授してくれます。
知識を得るためには、2つの行動が必要です。1つは学習すること、もう1つが経験することです。簡単ですね。情報が簡単に入手できる今、知識のソースは豊富にあります。溢れているくらいです。学習する手段もYouTubeやUdemyなど豊富にあります。
ただ、厄介なのは知識を引き出しに入れ込む作業です。学習しても経験しても、知識は引き出しには簡単には保管されません。なぜなら、人間は興味がないコトは無視するからです。興味のあることは覚えていますが、興味のないことはなかったことにします。このため、筆者はテーマを持って知識を習得しています。
例えば、「今回のテーマは知識の付け方」と決めて、そのテーマに応じた知識の獲得を目指します。そうすることで、興味を強く持った状態で引き出しに知識を入れ込むことができます。その際、筆者は自分の弱点にフォーカスしています。知らないことが弱点につながっていると考えており、知ればそれを克服する可能性があるからです。
忘却曲線に負けない学習を
もう1つ大事なことは「反復学習」です。ドイツの心理学者のヘルマン・エビングハウスの有名な忘却曲線があります。
「忘却曲線は、学習した情報が指数関数的に失われることを示している。最も急激な記憶減少は最初の20分で起こり、最初の1時間を通しての減衰も著しいものがある。 この曲線は約1日後になだらかとなる。」(Wikipediaより引用)
この忘却曲線の理論によると、学んだ20分後には忘却が急速に進行して、42%しか覚えていないそうです。そして、1日経過すると26%しか覚えていないそうです。おー怖っ。しかし、学習した後24時間以内に10分間の復習をすると記憶率は100%に戻り、次回の復習は1週間以内にたった5分すれば記憶がよみがえるそうです。小学生や中学生のころに「復習せよ」と言われた、その大切さが今わかりますね。
筆者は基本的にテーマに応じた書籍や記事を短期間に集中して読みます。そうすることで、知識が引き出しに残りますし、なにより共通の事項が大切なことだとわかるのです。それを引き出しに入れます。また、筆者は翻訳を中心に海外の書籍を読みます。それの何が良いかというと、色々な参照があり、それを辿っていくことで新しい関連知識を習得できるからです。その結果、読まなければいかない書籍が筆者の机に積み上げられています。
知識の引き出し方については、明確な手法を筆者はまだ定義できていません。ただ、何か課題があった場合に、どのような対応ができるかを必死に考えて、引き出しに入っている知識を課題に当てにいきます。筆者は毎日できるだけ8キロメートルほど散歩をするので、そのときに頭の中で組み合わせて考えることが多いです。この引き出すという行為について知識が得られたら、別の機会に共有したいと思います。