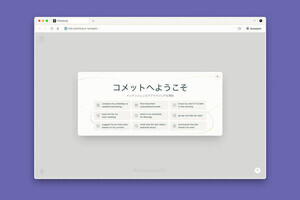最近、AIブラウザ競争がいきなりヒートアップしている。6月にGensparkが「Genspark AIブラウザ」、7月にPerplexityが「Comet」をリリース。最初からAIエージェントを組み込み、ブラウザをユーザーのアシスタントとする試みです。→過去の「柳谷智宣のAIトレンドインサイト」の回はこちらを参照。
そして10月22日、OpenAIが「Atlas」をリリース。多くの人が、AIエージェントブラウザに触り、その可能性に驚いたものです。Microsoftの「Actions in Edge」もGoogleの「Gemini in Chrome」も遅ればせながら参戦。すでに第三次ブラウザ戦争が始まっている様相です。
第三次ブラウザ戦争の主役はAI
既存のブラウザにAIのチャット欄を追加する程度では、そこまで便利にはならなかったのですが、AIエージェントがユーザーの指示でタスクを遂行してくれるのは次世代の体験となりました。Webブラウジングの発明以来となる根本的な変化かもしれません。
現在、ブラウザシェアのトップはGoogle Chromeですが、この状況になるまでには熾烈な戦いがありました。1990年代半ば、インターネット黎明期には、当時最先端だった「ネットスケープ・ナビゲーター」と、OSの巨人マイクロソフトが送り込んだ「インターネット・エクスプローラー(IE)」がぶつかり合いました。
マイクロソフトはWindows OSにIEを「無料でおまけ」として最初から組み込むバンドル戦略により、IEの勝利に終わりました。これが第一次ブラウザ戦争と呼ばれています。
第二次ブラウザ戦争は2000年代半ばから始まりました。第一次で勝利したIEは、長らく王様でしたが、進化を怠り、動作が重くセキュリティも甘くなっていました。Web標準も無視しがちで、開発者を悩ませていたのです。そこに「Firefox」が安全性とカスタマイズ性を掲げて挑戦。Appleも「Safari」でMacユーザーを固めました。
しかし、この戦いの決定打を放ったのはGoogleの「Chrome」でした。2008年に登場したChromeは、圧倒的な速さとシンプルなデザイン、タブの安定性、そしてGoogle検索との強力な連携を武器に、爆発的にシェアを伸ばしました。結果、IEは王座から転落し、ChromeがPCでもスマホでも新たなスタンダードとなりました。
そして現在、第三次ブラウザ戦争が勃発しています。今回の主役はもちろんAI。圧倒的シェアを持つChromeに対し、各社が新しいステージでの戦いを挑む形です。
これまでの戦いが「いかに速く、正確にWebページを表示するか」の技術競争だったのに対し、第三次は「いかにAIを使って、ネット体験を賢く、便利にするか」という、新しいステージでの戦いとなっています。
第三次ブラウザ戦争に参戦しているすべてのブラウザがChromiumを基盤にしており、追加で実装する独自のAI技術で差別化しようとしているのです。
ブラウザは単なる「閲覧ソフト」から、賢い「AIアシスタント」へと進化しようとしています。この戦いの結果が、私たち未来のインターネットの使い方や、情報の探し方を根本から変えることになるでしょう。そして、そこには利権、つまりはお金がつきまとうので熾烈な戦いになっているのです。
AIエージェント搭載ブラウザ5強、激突。「次」の標準はどれだ?
AIブラウザの最前線を走るのは、既存の枠組みを破壊しようとするスタンドアロン型のチャレンジャーたち。その筆頭が、PerplexityとOpenAIです。彼らは、ブラウザにAIを後から追加するのではなく、AI体験をゼロから構築することを選びました。
PerplexityのCometは、ユーザーの問いに対し、SonarやR1といった自社開発モデルに加え、GPTやClaudeといったAIを状況に応じて動的に使い分けます。Perplexityらしく、引用により信頼性を担保しているのも特徴です。
Cometは、単なる要約にとどまらず、@タブ機能で複数タブを横断比較したり、「バックグラウンドアシスタント」が非同期でタスクを処理したりと、まさにエージェントとして機能します。リリース当初は有料プラン向けでしたが、2025年10月に無料で提供されることになり、注目を集めました。
一方、OpenAI Atlasは「ブラウザとチャットする」という、ChatGPT中心の体験を提供。常駐する「Ask ChatGPT」サイドバーが閲覧中のページ文脈を理解し、要約や文章作成を支援してくれます。
無料プランでも利用できますが、有料プラン(ChatGPT Plusなど)で利用可能な「エージェントモード」がすごく便利です。ChatGPTがブラウザを直接操作し、例えばレシピを検索してそのままECサイトで材料をカートに入れるといった、複数ステップのタスクを自律的に実行できるのです。
例えば「週末のカレーパーティのための食材をイオンネットスーパーのカートに入れて。4人分です」と入力すると、カレーパーティに必要なメニューを考え、商品を検索し、指示通りにカートに入れてくれました。
結果、Cometはカレーとサラダ、付け合わせで14点3702円分の商品を追加してくれました。Atlasは11点3303円だが、カレーの材料のみを追加。今回は「パーティ」という文脈を理解してくれたCometの方が優秀な結果となりました。
牙城を守るGoogleとMicrosoft
AIネイティブ勢の猛攻に対し、Webの世界を長らく支配してきた巨大企業も黙ってはいません。GoogleとMicrosoftは、それぞれが持つ圧倒的な市場シェアとエコシステムを武器に、AI機能を既存ブラウザに統合することで牙城を守ろうとしています。
Googleの「Gemini in Chrome」は新しいブラウザを作るのではなく、既存の体験にGeminiを深く組み込みました。Chrome内で起動するGeminiは、現在開いているタブだけでなく他のタブの内容を理解し、タブを切り替えることなく情報の比較や要約を行います。
最大の強みは、やはりGoogle Workspaceとの深い連携。ユーザーの許可があれば、Gmailの要約やカレンダーへの予定追加をブラウザから直接実行できるのです。全機能の利用には、月額19.99ドルのGoogle One AI Proプランなどのサブスクリプションが必要になっており、AI機能が既存エコシステムへのロックインをさらに強化する構造となっています。
対するMicrosoftは、Edgeブラウザを「ダイナミックで知的なコンパニオン」へと進化させる戦略を採っています。特にWindowsやMicrosoft 365ユーザーの生産性向上に焦点を当てています。
現在、プレビュー段階の「Actions in Edge」は、AIがユーザーに代わってメールの購読解除やレストラン予約といった複数ステップのタスクを実行する機能です。また「Journeys」機能は、過去のブラウジングセッションをタスクごとに自動でグループ化し、中断した作業の再開を容易にします。
独自の地位を築くGenspark
市場の競争がスタンドアロン型対統合型という構図で進む中、異なるアプローチで独自の地位を築こうとする挑戦者がいます。Gensparkは、オープンソースのAIモデルをローカルで実行できる世界初のAIブラウザとしてGenspark AIブラウザを投入しました。
GPT-OSSやGemmaといったオープンソースLLM(大規模言語モデル)を169種類ラインナップし、ユーザー自身のPC上で直接実行できるようにしました。機密データが外部のクラウドサーバーに送信されることなく処理を完結できるため、高速レスポンスと高いプライバシー保護を実現しています。
AIが自律的にWebを閲覧する「オートパイロットモード」や、Eコマースサイトでリアルタイムの価格比較を行う実用的なエージェント機能も搭載。ブラウザ本体とオンデバイスAI機能は無料で利用できますが、クラウド処理が必要な高度なAI機能はクレジット制の有料プランが必要となります。
Gensparkのスタンスは、AIエージェントとユーザーとの信頼関係の在り方に対して、市場に根本的な問いを投げかけています。GoogleやMicrosoft、OpenAIが採用するのは「許可に基づく信頼」です。ユーザーは企業のプライバシーポリシーを信頼し、データ利用を許可することでAIの支援を得ます。
対照的に、Gensparkが提示するのは「設計によるプライバシー」であり、「われわれはあなたのデータを見ることができないので、信頼する必要すらない」というアーキテクチャに基づいた信頼モデルです。現在の生成AIサービスはクラウドが中心ですが、今後はローカルでの動作も併用されるようになるのは間違いないでしょう。
もう1つの「検証可能な信頼」を推進するのがPerplexity Cometです。AIの回答に必ず出典を明記することで、ユーザー自身が情報の真偽を検証できる透明性を担保しています。この「信頼」を巡る思想的な対立は、機能競争と並行して、今後のブラウザ選択におけるひとつの判断基準となっていくでしょう。
激戦区・日本市場の動向 - 黒船か、既存の牙城か
これらのグローバルな戦いは、日本市場においてどのような様相を呈しているのでしょうか。各社の日本での提供状況は大きく異なっています。Perplexity CometとOpenAI Atlas(macOS版)は、すでに日本で一般提供を開始しており、日本語にも完全対応しています。驚きの体験に多くの人が情報を発信し、徐々にユーザー数を増やしています。
一方、Gemini in Chromeは米国から段階的に展開中で、日本の全ユーザーがその恩恵を受けるにはまだ時間がかかる見込み。Microsoft Edgeの先進機能であるCopilot ActionsとJourneysも、現在は米国限定のプレビュー段階に留まっています。Gensparkは一般提供されているものの、日本語サポートの度合いは選択するオープンソースモデルの能力に依存する状況です。
筆者としては、ChatGPTの高いブランド認知度と高性能なエージェント機能により、鳴り物入りでお目見えしたAtlasが有利に見えますが、圧倒的なブラウザシェアを持つChromeとEdgeの影響力も見逃せません。
法人が利用するGoogle WorkspaceやMicrosoft 365の強固な地盤も追い風になるでしょう。一方、日本市場はデータプライバシーに対する意識が比較的高いので、Gensparkのオンデバイス処理やPerplexityの透明性の高い引用アプローチも大きなビジネスチャンスとなり得ます。既存の巨人が守りを固めるか、それともAIネイティブ勢がローカライズ戦略で切り崩すか。日本市場の動向から目が離せません。
この状況は単なるブラウザの機能競争ではありません。Webとの対話を通じて、デジタルライフ全体を管理する窓口の主導権争いなのです。第三次ブラウザ戦争の戦線は3つあり、まだまだ趨勢は読めません。
第一に、より複雑なワークフローを自動化できるかを競う「エージェント能力の軍拡競争」。当然、皆は賢いAIを使いたいからです。
第二に「許可に基づく信頼」と「検証可能な信頼」のどちらがユーザーの心を掴むかを巡る「信頼性を巡る思想闘争」。特にビジネスシーンでは慎重な判断が求められます。
最後に、ユーザーを自社サービスに囲い込む「エコシステム戦争」です。ユーザーとしては、ぜひ公平で透明性の高い競争になり、オープンで便利な未来が来ることを期待したいところです。