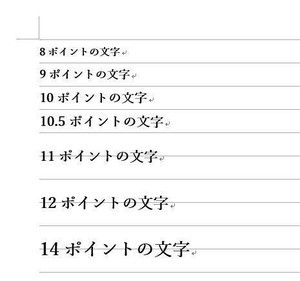Wordには、各段落を「箇条書き」や「段落番号」として表記するための書式が用意されているが、この書式をどうも好きになれないという人もいるだろう。そこで今回は「ぶら下げ」を使って箇条書きや段落番号のように表現する方法を紹介していこう。また、「ぶら下げ」と「タブ」を組み合わせた応用例も紹介する。
「箇条書き」の書式が必要になる場面
文章や単語などをリスト化して示すときは「箇条書き」という書式を利用するのが一般的だ。この書式の指定手順は、段落を選択して「箇条書き」コマンドから好きな行頭文字を選択するだけ。すると、それらの段落を「箇条書き」として示せるようになる。
以下の図は、行頭文字に「◆」を選択した場合の例だ。この方法で文書に「箇条書き」を記している人もいるだろう。
また、似たような機能として「段落番号」という書式も用意されている。こちらは、各段落の先頭に「1、2、3、……」などの番号を付けて手順を示す場合などに活用できる。
いずれもWordの基本的な書式といえるが、その結果は少し微妙なものになってしまう。というのも、行頭文字(または番号)と本文の間隔が広くなりすぎる傾向があるからだ。
よって、これらの書式を使わずに“通常の文字”のまま箇条書きを記している人もいるだろう。たとえば、各段落の先頭に「・」の記号を自分で入力して、箇条書きのような見た目に仕上げることも可能だ。
このように、箇条書きの文章を“通常の文字”として記しても何ら問題はない。さらに「インデント」を指定して、左側に余白を設けるのも効果的な手法といえる。以下の図は、箇条書きの部分に「2字のインデント」を指定した例だ。
ただし、この手法が使えるのは「各段落が1行に収まるとき」に限定されてしまうことに注意しなければならない。文章が2行以上になると、文章の先頭が揃わないといった不具合が発生してしまう。
一方、「箇条書き」の書式を指定した場合は、2行以上の文章も問題なく先頭を揃えて配置される。そういう意味では「箇条書き」は便利な書式といえるかもしれない。
でも、「やっぱり行頭文字と本文の間隔が広すぎる……」と感じる人もいるはずだ。そこで「ぶら下げ」という書式を使って箇条書きを表現する方法も覚えておくとよい。その手順を詳しく解説していこう。
「ぶら下げ」を使った文字の配置
まずは、箇条書きにする段落の先頭に「・」や「●」、「■」などの記号を入力する。続いて、これらの段落をまとめて選択し、「段落」グループの右下にある「小さな四角形」をクリックする。
「段落」ダイアログが表示されるので、最初の行に「ぶら下げ」を指定し、幅に「1字」を指定する。
「OK」ボタンをクリックすると、各段落の2行目以降に「1文字分の余白」が設けられるのを確認できる。つまり、各段落の1行目が左側へ1文字分だけ飛び出した形で配置されることになる。この飛び出した部分を「行頭文字として機能させる」と考えればよい。
なお、上記の例では、文章が1行に収まっている段落にも「ぶら下げ」の書式を指定したが、これは文字数が増えて2行になったときの対策となる。あらかじめ「ぶら下げ」の書式を指定しておけば、何らかの理由により文章が2行に増えても、不具合なく文字を配置できるようになる。
このように「ぶら下げ」の書式を活用すると、段落が2行以上になっても文字の先頭を揃えて配置できる。さらに「インデント」を指定してもよい。以下の図は、先ほどの例に「2字のインデント」を追加した例となる。
このように1字の「ぶら下げ」を指定することにより、箇条書きのような見た目を実現する方法もある。Wordに用意されている「箇条書き」の書式が好きになれない人は、この方法で箇条書きを記していくとよいだろう。
「ぶら下げ」と「タブ」を使った応用例
続いては、段落番号のような配置を実現する方法を考えてみよう。今回の例では「(1)、(2)、(3)、……」という形で各段落の先頭に番号を付けることにした。それぞれの段落が1行に収まる場合は、普通に文字を入力していくだけで作業完了となる。ただし、以下の図の(4)のように2行以上の段落が含まれる場合は、文字の先頭を揃える調整作業が必要になる。
これを先ほどと同じ手順で解決してみよう。段落をまとめて選択し、3字の「ぶら下げ」を指定する。
すると、各段落の2行目以降に「3文字分の余白」が設けられ、以下の図のような配置になる。今回の例では、1、2、3、……の数字を半角で入力しているため、(4)の文字幅は全角3文字分にならない。よって、少しズレた形で2行目以降が配置されてしまう。
このようなズレを解消したいときは、番号と本文の間に「タブ」を入力してやるとよい。「タブ」の入力は、その位置にカーソルを移動して「Tab」キーを押すと実行できる。
すると、タブ以降の文字が「ぶら下げ」で指定した位置(3字の位置)から開始されるようになる。このように「ぶら下げ」と「タブ」を組み合わることで、各文章の先頭を揃えて配置する方法もある。便利に活用できるので、ぜひ覚えておくとよいだろう。
「ぶら下げ」の幅に“小数点以下の文字数”を指定することもできる。先ほど示した例は少し間隔が広すぎるので、文章を開始する位置を微調整してみよう。もういちど「段落」ダイアログを開き、「ぶら下げ」の幅を2.6字に変更する。
すると、タブ以降の文字が2.6字の位置から開始されるようになり、番号と本文の間隔を狭められる。
少し頭が混乱しているかもしれないので、いちど整理しておこう。
◆「ぶら下げ」の指定
各段落の2行目以降が「字数」で指定した位置から開始されるようになる。小数点以下を含む「字数」を指定することも可能。
◆さらに「タブ」を入力
タブ以降の文字が「ぶら下げ」で指定した位置から開始されるようになる。
こういった仕組みの組み合わせで、文章の先頭を揃えつつ、1行目だけを左に飛び出させて配置できる。ただし、「ぶら下げ」の字数が十分でなかった場合は、配置に不具合が生じてしまう。以下の図は、「ぶら下げ」の字数を2.5字に変更した例だ。
この場合、各段落の2行目以降は2.5字の位置から開始される。同様に、1行目の「タブ以降の文字」も2.5字の位置から開始されるはずが、実際にはそうなっていない。
これは(1)や(2)などの文字幅が2.5字分よりも大きいことが原因だ。このままでは文字が重なって配置されてしまうため、十分な字数が確保されていない場合は、既定のタブ位置(初期値は4字間隔)から「タブ以降の文字」が開始される仕組みになっている。つまり、1行目の「タブ以降の文字」は4字の位置から開始されることになる。
もしも上図のような不具合が発生したときは、「ぶら下げ」の字数を少しだけ大きくしてやると、文章の先頭を揃えて配置できるようになる。「ぶら下げ」と「タブ」を組み合わせて活用するテクニックとして覚えておくと役に立つだろう。