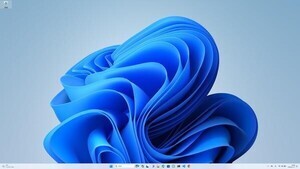これまで3回にわたって拡張機能「VisiOS」の使い方を紹介してきたが、これ以外にも覚えておくと便利な機能がいくつかある。今回はVisiOSの最終回として、ファイルやフォルダーの検索、サイドパネルの活用、2D Paint、パスワード保護、VisiOSの設定画面について紹介しよう。
今回、紹介する内容は以下の通り。
- デスクトップに保存したファイルやフォルダーを検索する方法
- VisiOSをサイドパネルとして表示する方法
- 「2D Paint」を使ってデスクトップに手書きする方法
- デスクトップやフォルダーをパスワードで保護する方法
- VisiOSの設定画面
こういった機能の使い方も覚えておくと、より快適にVisiOSを利用できるようになる。すでにVisiOSを利用している方も一読しておくとよいだろう。
ファイルやフォルダーの検索
VisiOSには、ファイルやフォルダーの検索機能が用意されている。検索機能を利用するときは、画面右下にある「+」アイコンをクリックして「虫眼鏡」を選択すればよい。
すると、以下の図に示したようなウィンドウが表示される。ここに適当なキーワードを入力すると、その検索結果がウィンドウの下部に一覧表示される。あとは表示された検索結果をクリックしてファイルやフォルダーを開くだけ。これで保存場所を忘れてしまったファイル(フォルダー)を簡単に見つけ出せるようになる。
この検索機能にはオプションも備えられている。9枚あるデスクトップのうち「どのデスクトップを検索対象にするか?」、また「リンク先のURLも検索対象に含めるか?」を指定して検索することも可能だ。さらに、AND(かつ)やOR(または)、XOR(指定したキーワードを含まない)の検索を行える「高度な検索」も用意されている。
フォルダー内だけを対象に検索することも可能だ。この場合は「フォルダー」を開いて、ウィンドウ右上にある「虫眼鏡」のアイコンをクリックすればよい。
続いて、適当なキーワードを入力すると、そのキーワードを含むファイルだけがハイライト表示される。
なお、ハイライト表示を解除したいときは、ウィンドウ右上に入力した検索キーワードを削除してあげればよい。これで元のフォルダー表示に戻すことができる。
参考までに、ファイルの表示方法を変更するときの操作手順も紹介しておこう。「虫眼鏡」の右隣にあるアイコンをクリックすると、フォルダー内のファイルをリスト表示することが可能となる。このあたりも「本物のOSっぽい仕様」といえるだろう。
リンクはファイル名が長くなりがちなので、この表示方法のほうが目的のファイル(リンク)を探しやすくなるかもしれない。ちなみに、元のアイコン表示に戻したいときは、同じアイコンを再度クリックしていけばよい。
上記に示した例は、いずれも検索機能が必要になるほどの状況にはなっていないが、ファイルの数が増えてきたときには重宝する機能となるだろう。
サイドパネルの活用
普通にWebページを閲覧しているときに、VisiOSを「サイドパネル」として表示する機能も用意されている。サイドパネルを開くときは、「VisiOS」のアイコンを右クリックして「サイトパネルを開く」を選択すればよい。
すると、VisiOSがサイドパネルとして表示され、デスクトップに保存したファイルに手軽にアクセスできるようになる。「Webページ」と「サイドパネル」を区切る境界線を左右にドラッグして、各領域のサイズを調整することも可能だ。
サイドパネルに慣れている方は、この表示方法で「VisiOSのデスクトップ」を活用していく方法もある。
デスクトップに手書き文字を描画「2D Paint」
続いては、デスクトップに「手書き文字」を描画できる機能を紹介していこう。この機能を利用するときは、デスクトップの右下にある「+」アイコンをクリックして「2D Paint」を選択する。
すると「色」や「太さ」を指定するパネルが表示されるので、ここでペンの書式を指定する。あとはマウスをドラッグして好きな文字(または絵)を描くだけ。これでデスクトップ上に「手書き文字」を残すことができる。
デスクトップに描画した「手書き文字」を削除したいときは、「ゴミ箱」のアイコンをクリックすればよい。そのほか、直前の描画を取り消す「Undo」、個々の線をクリックで削除できる「消しゴム」も用意されている。
なお、第38回の連載で紹介したように、VisiOSには「テキスト」や「リスト」をデスクトップに配置できる機能も用意されている。このため、「2D Paint」を利用する機会は滅多にないかもしれない。よって、この機能は参考程度に覚えておけば十分だ。
デスクトップやフォルダーのパスワード保護
機密事項やプライベートな情報をVisiOSで管理できるように「パスワード保護」の機能も用意されている。
まずは、デスクトップ全体をパスワードでロックする方法から紹介していこう。デスクトップの余白部分を右クリックし、「設定」を選択する。
VisiOSの設定画面が表示されるので「ログインとパスワード」の項目を開き、ログイン用のパスワードを指定する。その後、「×」をクリックして設定画面を閉じる。
以上でパスワードの設定は完了。次回以降は、VisiOSを起動したときに「パスワードの入力」を求める画面が表示されるようになる。もちろん、正しいパスワードを入力しない限り、デスクトップは使用できなくなる。
そのほか、フォルダーにパスワードを設定して保護する方法も用意されている。こちらを利用するときは、「フォルダー」を右クリックして「パスワードロック/ロック解除」を選択する。
以下の図のような画面が表示されるので、フォルダーを開くためのパスワードを指定し、「保存」ボタンをクリックする。
以上でフォルダーのパスワード保護は完了となる。パスワードを指定したフォルダーは、右上に「鍵」のアイコンが表示されるようになる。もちろん、これ以降は正しいパスワードを入力しない限り、フォルダーを開けなくなる。
念のため、指定したパスワードを解除するときの操作手順も紹介しておこう。デスクトップに指定したパスワード保護を解除するときは、VisiOSの設定画面を開き、「ログインとパスワード」の項目でパスワードを空欄に再設定してあげればよい。
フォルダーに指定したパスワード保護を解除するときは、「フォルダー」を右クリックして「パスワードロック/ロック解除」を選択する。すると、現在のパスワードを訪ねる画面が表示されるので、正しいパスワードを入力する。その後、パスワードを空欄に再設定すると、パスワード保護を解除できる。
VisiOSの設定画面とエクスポート
最後に、VisiOSの設定画面とエクスポートについて補足しておこう。先ほども紹介したように、デスクトップの余白部分を右クリックして「設定」を選択すると、VisiOSの設定画面を開くことができる。
この画面にある「バックアップとリセット」は、現在のデスクトップ状況のバックアップファイルを作成したい場合に利用できる。「バックアップとリセット」の項目を開き、「バックアップを作成」ボタンをクリックする
続いて、バックアップする内容(デスクトップ、設定)を指定し、「バックアップをダウンロード」ボタンをクリックする。
すると、JSON形式のファイルが「ダウンロード」フォルダーに保存される。デスクトップをバックアップ時の状態に戻したいときは、「バックアップとリセット」→「バックアップからロード」を選択して、このJSON形式のファイルを指定してあげればよい。
VisiOSの設定画面にある「デスクトップ切り替え時のスプラッシュ」についても補足しておこう。この項目を選択すると、各デスクトップに説明文を追加できるようになる。
ここで指定した説明文は、デスクトップを切り替えた際に、以下の図のような形で表示される。必須の機能ではないが、用途別にデスクトップを使い分けるときの補助機能として活用できるだろう。
そのほか、VisiOSで作成した「ドキュメント」をパソコンにファイルとして保存する機能も用意されている。この機能を利用するときは、「ドキュメント」のファイルを右クリックして「エクスポート」を選択する。
すると、「ダウンロード」フォルダーにHTML形式のファイルが保存される。このHTMLファイルをダブルクリックして開くと、文書の内容をブラウザに表示できる。
HTML形式のファイルになるため、そのままWordなどの文書作成アプリに読み込むことはできないが、コピー&ペーストして文書を再利用することは可能となる。こちらも参考程度に覚えておくと役に立つだろう。
ということで、計4回にわたって「VisiOS」の使い方を紹介してきた。ブラウザ内に仮想OSを構築することで、さまざまな用途に活用できることを実感できたと思う。ブックマークの管理をはじめ、タスクやメモの管理、文書の作成など、気になる方はいちど試してみるとよいだろう。