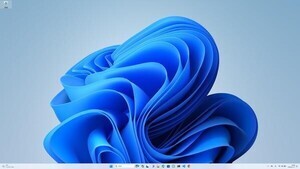Webページを資料として活用する際に、メモや補足情報などを付加しておきたいたい場合もあるだろう。こういった場合に活用できるのが「Note Anywhere」だ。この拡張機能を使うと、Webページに付箋(ふせん)形式のメモを貼り付けられるようになる。ユニークな拡張機能なので、気になる方はいちど試してみるとよい。
Note Anywhereの追加手順
今回、紹介するのは、Webページに付箋を貼り付けられる拡張機能「Note Anywhere」だ。Webページにメモや補足情報などを残せるツールとして活用できるだろう。
それではNote Anywhereの追加手順を紹介していこう。拡張機能の追加手順はいつもと同じ。Note Anywhereの紹介ページを開き、右上にある「Chromeに追加」をクリックする。続いて、「拡張機能を追加」ボタンをクリックするとインストールが完了する。
拡張機能を追加できたらNote Anywhereをツールバーに固定しておこう。「拡張機能」のアイコンをクリックし、Note Anywhereのピンをオンにする。これで準備は完了。さっそく、Note Anywhereの詳しい使い方を紹介していこう。
Note Anywhereの基本的な使い方
まずは、Note Anywhereの基本的な使い方から紹介していこう。Webページに付箋を貼り付けるときはNote Anywhereのアイコンをクリックし、「Add Note」を選択すればよい。
すると、Webページの中央に付箋が配置されるので、この中に補足情報や注意点などのメモを自由に入力していく。
貼り付けた付箋の位置やサイズを変更することも可能だ。付箋の位置を移動するときは「タイトルバー」、付箋のサイズを変更するときは「右下のハンドル」をドラッグすればよい。
ただし、「最低限の高さ」が定められているようで、文字の行数に合わせて付箋を小さくすることはできない。このため、文字の下に無駄な余白が生じてしまうケースもある。このあたりは今後の改善を期待したいところだ。
もちろん、同様の操作を繰り返して、2枚以上の付箋を貼り付けることも可能である。
それぞれの付箋を色で分類する機能も用意されている。付箋の色を変更するときは、上図に示した「…」をクリックし、一覧から色を選択すればよい。
そのほか、「…」のメニューには「Pin」や「Delete」といった項目も用意されている。「PIN」をクリックすると、通常は画面と一緒にスクロールされていく付箋がウィンドウに固定され、常に表示されるようになる。「Delete」は付箋を削除するときに利用する項目となる。
もちろん、各Webページに貼り付けた付箋は、以降に同じWebページを開いたときに自動表示される仕組みになっている。このため、Webページを見返した際に、付箋としてメモした内容を再確認することが可能となる。
覚えておくと便利な機能
続いては、Note Anywhereをもっと便利に活用するための各種機能を紹介しておこう。
Webページに貼り付けた付箋には、「文字」だけでなく、「画像」を埋め込むことも可能となっている。画像を埋め込むときは、その画像を付箋内にドラッグ&ドロップすればよい。この操作は「別のWebページ」に掲載されている画像にも対応している。ただし、パソコンに保存されている画像ファイルには対応していない。挿入できるのは“Webに掲載されている画像のみ”となる。
別のWebページに掲載されている「文字情報」や「画像」などを参考資料として貼り付けておけば、いちいち別のWebページを開かなくても付箋で情報を補完できるようになる。これがNote Anywhereの便利な使い方といえるだろう。
付箋だらけで、肝心のWebページが見づらくなってしまった場合は、付箋をアイコン表示に切り替えることも可能だ。この場合はNote Anywhereをクリックしてメニューを開き、「Iconize」を選択する。
すると、すべての付箋がアイコンで表示されるようになる。アイコンの上にマウスを重ねると、その付箋が表示され、内容を確認できるようになる。
ただし、付箋の外へマウスを移動しても付箋は表示されたままで、アイコン表示には戻ってくれない。このあたりは、予想とは異なる動作になっていた。
そのほか、すべての付箋を一時的に非表示にする機能も用意されている。こちらはNote Anywhereのメニューにある「Hide Notes」を選択すると実行できる。もういちどNote Anywhereのメニューを開いて「Show Notes」をクリックすると、すべての付箋を再表示できる。
Note Anywhereのオプション
最後に、Note Anywhereのオプションについて紹介しておこう。オプション画面を開くときは、Note Anywhereのアイコンを右クリックして「オプション」を選択すればよい。
すると、以下の図のような画面が表示される。最初は「Summary」の項目が選択されているはずだ。ここには「付箋を貼り付けたWebページ」が一覧表示されている。それぞれのURLはリンクとして機能するため、この画面をブックマークとしても活用することもできる。ただし、URLだけの表示になるため、少しわかりづらいのが難点といえる。
「Setting」の項目は、デフォルトで表示される付箋の書式を変更する際に利用する。ここで「規定の付箋」の色やフォントなどをカスタマイズすることも可能だ。
「Sync」の項目を選択すると、「My Atoms」へのサインインを促す画面が表示される。ここで「Sign in & Sync」をクリックしてアカウント登録すると、付箋の内容を別のパソコンと同期できるようになる。こちらは、複数のパソコンで付箋を共有したい場合に活用するとよいだろう。
もちろん、アカウント登録は必須ではないので、単独(1台のパソコン)でNote Anywhereを使用するときは、この項目を無視しても構わない。
以上がNote Anywhereの概要となる。「Webページに付箋を貼り付けられる」というユニークな機能に興味を持った方は、いちど試してみるとよい。