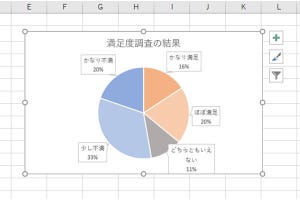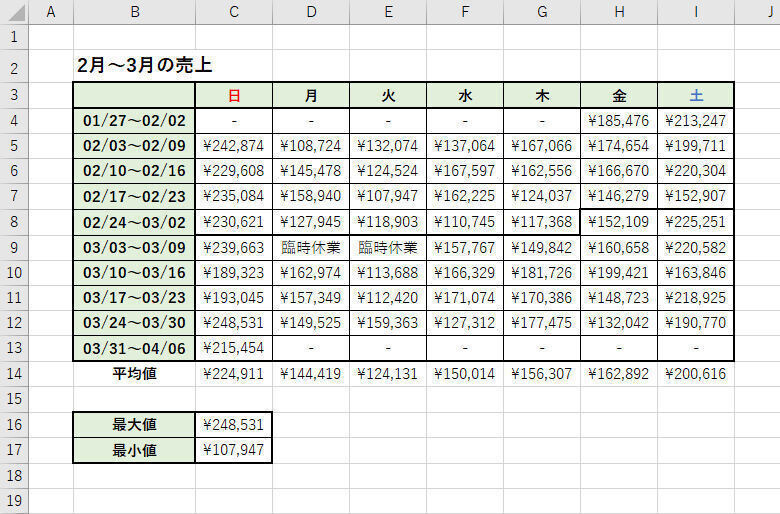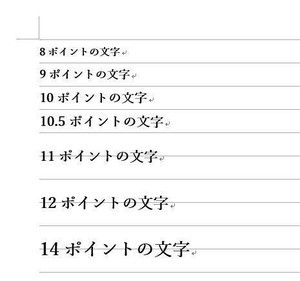前回の連載では「関数PMT」や「関数NPER」を使ってローンの計算を行う方法を紹介した。これを逆に考えて、積立投資したときの将来の金額などをExcel関数でシミュレーションすることも可能だ。つみたてNISAやiDeCoはもちろん、FIRE(早期リタイア)を目指すときの指針としても活用できるだろう。気になる方は試してみるとよい。
積立投資のシミュレーションにも使えるExcel関数
前回の連載で紹介した「関数PMT」や「関数NPER」などを使って積立投資のシミュレーションを行うことも可能だ。今回は、ここ数年、話題になっているFIRE(早期リタイア)を目指す場合を例に、積立投資のシミュレーションをExcelで行う方法を紹介していこう。
FIREの具体的な例として、「1億円の資産を利回り4%で運用していけば、毎年400万円の利益を得られる。この400万円で生活していけば仕事から解放される」という話がよく紹介されている。
ただし、そのためには、まず1億円の資産を用意しなければならない。その手段は「積立投資で資産を雪だるま式に増やしていく」となっているケースが多いが、実際問題として、どれくらい積立投資すれば1億円を達成できるのだろうか? Excelでシミュレーションしてみよう。
将来の資産額をシミュレーションする
まずは「関数FV」を使って「将来の資産がいくらになるか?」をシミュレーションする方法を紹介していこう。
この計算を行うには、「想定利回り」、「積立期間」、「毎月の積立金額」といった3つの条件を指定する必要がある。それぞれの値を手軽に変更できるように、以下のような表を作成する。
今回は、「想定利回り」を4%と予想して、毎月7万円を20年間、積立投資していく場合を考えてみよう。それぞれの数値を表に入力する。なお、「想定利回り」のセルには「パーセンテージ」の表示形式を指定している。このため、4.00%の場合、実際に入力されている値は0.04という数値になる。
これらの数値を参照しながら関数FVを入力していこう。関数FVの書式は、以下のようになっている。
◆関数FVの書式
=FV(利率, 支払回数, 定期支払額, [現在価値], [支払期日])
第1引数には、「毎年、何%くらいの利益を得られそうか?」という予想値を指定する。これを一言でいうと「想定利回り」となる。第2引数には「積立する回数」、第3引数には「毎月の積立金額」を指定する。
第4引数(現在価値)には「最初の資産額」を指定する。積立投資の場合、この値は0(ゼロ)になる。なお、0の場合は、この引数の記述を省略しても構わない。
第5引数(支払期日)は「いつ積立を行うか?」を数値の0(各期の期末)または1(各期の期首)で指定する。この引数も省略することが可能であり、省略した場合は0(各期の期末)が指定されたとみなされる。
前回の連載でも紹介したように、複利計算を行う関数を使用するときは、それぞれの単位を「月」に統一しておくのが基本だ。第1引数から順番に解説しておこう。
一般的に「想定利回り」は年単位で考えるケースが多い。これを月単位に換算するには、12で割り算しておく必要がある。
続いて、第2引数に「積立する回数」を指定する。今回の例では「期間」(C4セル)を年で指定しているので、これに12を掛け算して月単位の数値にする。
第3引数は「毎月の積立金額」をそのまま参照すればよい。一般的な積立投資の場合、第4引数と第5引数の指定は省略することが可能だ。
「Enter」キーを押して関数FVを実行すると、「将来の資産」として以下のような数値が表示された。
この例のようにマイナスの数値が表示された場合は、第3引数(定期支払額)をマイナスの数値に変換して指定するとよい。
これで「将来の資産」をプラスの数値として表示できるようになる。
この結果を見ると、想定利回り4%で毎月7万円ずつ20年間の積立投資を行うと、約2567万円にまで資産を増やせることがわかる。実際に投資した金額は(7万円)×(20年間:240回)=1680万円なので、それなりに資産を増やせることになる。ただし、1億円には程遠い。つまり、この程度の積立投資では「FIREを実現できない」ということになる。
せっかく色々な条件でシミュレーションできるのだから、別の条件も試してみよう。まずは、思っていたほど投資が上手くいかず、利回りが2%しか得られなかった場合だ。この場合における「将来の資産」は約2064万円になり、さらにFIREの実現が遠のくことになる。
「想定利回り」を4.0%に戻して、「毎月の積立金額」を10万円に増やした例も見てみよう。この場合、「将来の資産」は約3668万円にまで増えるが、それでも1億円の半分にも満たない。
このように関数FVを使うと、条件を色々と変更しながら「将来の資産」を予測することが可能となる。
目標達成に必要な「毎月の積立金額」をシミュレーションする
今度は考え方を変えて、「1億円の資産を形成するには、毎月いくらの積立投資が必要か?」をシミレーションしてみよう。この場合に必要となる条件は、「想定利回り」、「積立期間」、「目標金額」の3つだ。
「毎月の積立金額」を計算するときは、前回の連載でも紹介した「関数PMT」を使用する。
◆関数PMTの書式
=PMT(利率, 期間, 現在価値, [将来価値], [支払期日])
数値を「月単位」に統一して指定することに注意しながら、それぞれの引数を指定していこう。第3引数(現在価値)には0(ゼロ)、第4引数(将来価値)には「目標金額」を指定する。
この場合も、計算結果がマイナスの数値で表示される。
第4引数をマイナスの数値に変換して指定する方法もあるが、(将来価値)をマイナスにするのは少し変な気もするので、別の方法で対策してみよう。マイナスを数値をそのままプラスにするときは、絶対値を返す「関数ABS」で囲んであげればよい。
これで「毎月の積立金額」をプラスの数値で表示できる。
この結果をみると、想定利回り4%、20年間の積立投資で資産を1億円にするには「毎月、約27万円の投資が必要になる」ということがわかる。
とはいえ、これは相当に厳しいシナリオになるはずだ。生活費を確保しつつ、さらに毎月27万円の投資を20年間も継続していく。これを実践できる方は少ないだろう。「なるべく節約して・・・」で実現できるレベルではない。
ということで、今度はもっと積極的に運用して「想定利回り」を8%に増やした例を見てみよう。
この場合「毎月の積立金額」は約17万円にまで減少するが、それでも大きな金額であることに変わりはない。それ以前の問題として、利回り8%を20年継続する、というのが相当に難しい課題になるかもしれない。
少し妥協して「目標金額」を5000万円に減らしてサイドFIREを目指す例も紹介しておこう。こちらは「想定利回り」を4%として計算している。
この場合「毎月の積立金額」は約13.6万にまで減少する。これで「少し現実味を帯びてきた・・・」と言いたいところだが、冷静に考えると、生活費のほかに毎月13.6万円の投資資金を捻出するのは、やはり大変な話と言わざるを得ない。
目標達成に必要な年数をシミュレーションする
今度は、もっと別の考え方でシミレーションする方法を紹介しておこう。たとえば、「想定利回り4%で毎月7万円ずつ積立投資した場合に、どれくらいの期間で1億円に到達するか?」を計算してみよう。
この場合に必要となる条件は、「想定利回り」、「毎月の積立金額」、「目標金額」の3つになる。
複利計算の期間を求めるときは「関数NPER」を使用する。こちらも、前回の連載で紹介した関数となる。
◆関数NPERの書式 =NPER(利率, 定期支払額, 現在価値, [将来価値], [支払期日])
単位を「月」に統一して関数NPERの引数を指定していくと、以下の図のようになる。なお、計算結果をプラスの数値で表示するように、第2引数(定期支払額)はマイナスの数値に変換して指定している。
この計算結果は、526.255・・・という数値になった。つまり、約526ヶ月にわたって積立投資を継続すれば1億円に到達する、という訳だ。
約526ヶ月という数値は理解しにくいので、「△年△ヶ月」という形に換算してみよう。前回の連載でも紹介したように、△年の部分は「=INT(C7/12)」、△ヶ月の部分は「=MOD(C7,12)」で算出できる。すると、43年と10.3ヶ月という結果が得られた。大雑把に見て約44年だ。
つまり、想定利回り4%で毎月7万円ずつ積立投資していくと「約44年後に1億円に到達する」という計算になる。これで無事にFIREを実現できることになるが、はたして本当にそうだろうか?
仮に現在の年齢が25歳だとすると、44年後には69歳になっているはずだ。これでは、とても早期リタイアとはいえない。やはりFIREは実現できなかったことになるが、1億円もの資産があれば「老後は安泰」と考えられるだろう。
このように関数NPERを使うと、積立投資で目標を達成するまでの期間を求めることが可能となる。
今回の連載は、FIREすることの難しさ(1億円を貯めることの難しさ)を伝えるような話になってしまったが、本当に伝えたかったのは「Excelでも積立投資のシミレーションを行える」ということだ。
FIREのように実現が困難な事例ではなく、子供の学費を積立投資で備える場合、つみたてNISAやiDeCoのシミュレーションを行う場合などであれば、もっと現実的な結果を得られるだろう。
前回の連載で紹介したローンと違って「利回り」を想定値でしか指定できないため、正確な将来値を予測するのは不可能であるが、何の指針もなく、やみくもに投資するよりは計画性が高くなるはずだ。気になる方は、色々と条件を変えながら実際に計算してみるとよい。