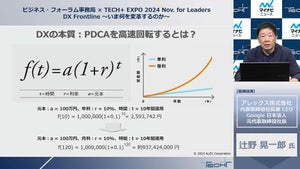前回は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みが進まない理由として3つの落とし穴を取り上げました。今回は、「現行踏襲」というキーワードに焦点を当て、それがDX推進においてどのような問題やリスクをもたらすかについて解説します。
変革を阻む「既存の業務プロセス」依存のリスク
DX推進における「現行踏襲」とは、新しいビジョンや目標に基づいて業務やシステムを再設計するのではなく、既存のシステムやプロセスをそのままデジタル化するアプローチを指します。
この現行踏襲がDXの文脈において問題視されるのは、既存の業務フローをそのままデジタルツールに置き換えるだけでは局所的な効果にとどまり、DXの本質的な目的である「ビジネスモデルの変革」を達成することが困難だからです。
では、なぜ企業は現行踏襲の選択をしてしまいがちなのでしょうか。ここにはいくつかの要因があります。
1つは、「失敗を避けたいという心理」です。現行の業務やシステムが正常に稼働している場合、失敗のリスクを背負ってまで、それをあえて変更することに多くの人は抵抗を感じます。しかし、「変えなければリスクを負わずに済む」という前提は今や必ずしも成り立ちません。急速に進化する現在のテクノロジー環境では、現状維持はむしろ他社に後れを取るリスク要因となり始めています。
もう1つ、現行踏襲を助長する要因として挙げられるのは「システムのブラックボックス化」です。業務の自動化や効率化を進めて長い年月が経過すると、多くの利用者は「なぜそのような仕組みになっているのか」という背景や、業務間の関係性を深く意識しなくても業務が回るようになります。一方で、誰も業務システム間の関係性をひも解くことができないという、いわゆるブラックボックス状態になります。
そのためにシステムを再構築する段階において、個別の業務を最適化することは可能でも、全体を俯瞰して見直しを行うことが企業にとって重い負担となり、変革に二の足を踏んでしまうのです。
例えば、既存の業務やシステムの抜本的な見直しを行う場合、システム開発当初に正確な仕様書が存在していたとしても、年月の経過に伴う業務やシステムの改修が反映されず、最新システム仕様や業務仕様が分からないということも珍しくありません。
仕様書本体の修正に負荷がかかることから、企業によっては改版部分のみを別ドキュメントの改造仕様書として作成することもありますが、これを繰り返したことで仕様書の数が膨大となり、誰も全体像を正確に把握できなくなってしまったというケースもあります。その結果、変更作業が複雑化し、既存のプロセスを踏襲する方が「簡単」だという判断に至ってしまうのです。
現行踏襲は「維持」ではなく「悪手」でしかない
現行踏襲は、一見するとリスクの少ない安全な選択肢のように思えますが、実際には企業に大きな負担とリスクをもたらします。
まず、最新テクノロジーと既存のレガシーシステムとの間でギャップが広がることによって、それを埋めるためのコストが増加します。このギャップを解消するためにはレガシーシステムの維持費用だけでなく、レガシーな技術と最新技術の双方に精通した専門人材が必要です。しかし、人材獲得競争が激化しているため、そうした人材の確保はそう容易ではありません。
さらに、レガシーシステムの維持自体が高コスト化しています。例えば、メインフレームなどのハードウェアが製造終了を迎えたり、既存ソフトウェアのライセンス料が値上がりしたりするケースが増えているのです。また、サポート終了(EOL)に伴うセキュリティリスクも無視できません。
こうした負担やリスクがある中で、現行踏襲を選択することは、単なる「維持」ではなく、「悪手」でしかありません。変化を拒むことは責任放棄といっても過言ではないでしょう。特に、業界全体が新しいビジネスモデルにシフトしていく中で、従来の方法に固執することは、長期的に見た場合、競争力低下につながります。現行踏襲は単なる技術的な問題にとどまらず、企業文化や意思決定プロセスの硬直化をもたらし、企業経営の根本的な問題に関わるものと言えます。
現行踏襲から脱却するための実行可能なアプローチとは
現行踏襲の落とし穴を回避するためには、どうすればよいでしょうか。
対策の一つとして、既存の業務プロセスやシステム仕様を徹底的に整理して解析し、全体像を明らかにすることが求められますが、この方法は膨大なリソースと時間を必要とするため、現実的には難しい場合が多いでしょう。
そこで、実現可能性の高いアプローチとして、現在のテクノロジーの潮流に合わせて業務プロセスそのものを見直し、再構築するということが挙げられます。
もちろんこれも理想論であり、すべてを一気に変えることは困難です。ただし、計画を立てて段階的に進めることは可能です。例えば、クラウド移行であれば、いきなり既存のアーキテクチャを完全に置き換えるのではなく、初期段階では業務間をつなぐインタフェースのAPI化だけを行い、他の部分については次のフェーズで取り組むといった進め方があります。こうしたアプローチは、変革を進める際の負担を軽減し、成功率を高めることにもつながります。
変革により「自分の価値が下がる」という現場担当の懸念も
ここで、実際に「現行踏襲の落とし穴」に陥ったあるサービス企業の事例を紹介しましょう。
同社は迅速な新規サービス展開を行うにあたり、アジャイル開発やマイクロサービスなどの最新技術を採用しました。アジャイル開発は、市場や顧客からの迅速なフィードバックに基づいて計画を柔軟に見直し、改善を繰り返すことで、高いアジリティを実現します。マイクロサービスは、システムを疎結合化させることで、1つの機能変更が全体に与える影響を最小限に抑えることができ、こちらもビジネス変化に迅速に対応し、新しいサービスを素早く展開するうえで重要な技術です。
これらの手法をうまく組み合わせることで、ITシステムの進化だけでなく、企業文化やベンダーとの関係においても柔軟な体制を構築することが可能です。
しかし、現場担当からは「これまでのやり方に慣れている」「なぜ変えなければならないのか」といった声が多く上がり、変革への抵抗が顕著に現れました。この背景には、新しい技術やプロセスへの理解不足や、変化そのものに対する恐れもあります。また、現行業務にノウハウを持つ人材が「従来のやり方の変化によって既存のノウハウが陳腐化し、自分の価値が下がってしまう」という不安を抱いていることも挙げられます。
「人」に響く戦略をビジョンに組み込む
上記の事例では、トップが変革の必要性を明確に伝えるとともに、先述したように段階的なアプローチを取ることが重要になります。例えば、全社的な変革を一度に進めるのではなく、部分的に新しい技術を導入し、その成功事例を積み上げていくことで、現場の信頼を得るといったやり方が解決の糸口となるでしょう。
さらに、この事例では、リスキリングの推進が重要な役割を果たします。現代のビジネス市場の特徴は急速な環境変化であるため、この変化に適応できないことは、個人の市場価値を低下させるリスクを伴います。特に、これまでの経験やノウハウを磨き上げてきた人々にとっては、変化に対応するためのキャリアチェンジが必要となる場面が増加しているのです。
そのため、企業がスムーズなキャリアチェンジを支援する施策としてリスキリングを進めるとともに、その取り組み姿勢や成長度を評価に反映することで、従業員の不安や抵抗感を軽減します。このような取り組みを通じて、従業員の変化への対応力を高める環境を整えていきます。
最終的に、変革を実現するのは「人」であり、その人々に響く戦略を描くことが、組織の成功には不可欠です。これをビジョンに組み込み、明確に伝えることで、個人と組織の成長を両立させる道が開かれていくでしょう。
以上、今回はDX推進における現行踏襲の落とし穴とその要因について説明してきました。急速な変化が求められる現代のビジネスにおいて、現行踏襲は「現状維持」ではなくむしろ「後退」であり、企業が持続的な成長を遂げるためには、デジタルによるビジネスモデル変革は避けられません。
次回は、DXの進捗を阻害する2つ目の要因である「情報投資の意思決定プロセスの落とし穴」について詳しく解説します。
著者:篠田 尚宏
Ridgelinez株式会社 Director/Technology Group
著者:藤井 崇志
Ridgelinez株式会社 Senior Manager/Technology Group