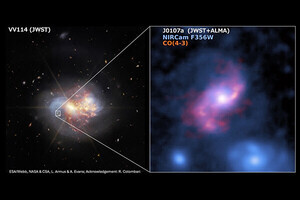国立天文台、九州大学(九大)、台湾・中央研究院天文及天文物理研究所(ASIAA)、工学院大学、足利大学の5者は、アルマ望遠鏡の公開観測データにスパースモデリングを応用した新たな画像復元法を適用し、これまでの解析では捉えきれなかった若い星をとりまく原始惑星系円盤の構造とその進化を明らかにしたと、6月24日に共同発表した。
-

従来の画像復元法とスパースモデリングを応用した新手法で得られた、へびつかい座の星形成領域に分布する原始惑星系円盤の画像。各パネル左下の楕円マークは解像度を示し、小さいほど高い解像度を意味する。右下の白線は30天文単位を表す目盛り。左列から右列へ、同じ列では上から下へ向かって、中心星の年齢は高くなっている
(C)ALMA(ESO/NAOJ/NRAO), A. Shoshi et al.
(出所:アルマ望遠鏡日本語Webサイト)
同成果は、九大大学院理学府/ASIAAの所司歩夢大学院生、九大大学院 理学研究院の町田正博教授、ASIAAの山口正行博士後研究員、同・平野尚美研究員、国立天文台/総合研究大学院大学の川邊良平名誉教授、工学院大 教育推進機構 基礎・教養科の武藤恭之教授、足利大 工学部 創生工学科 システム情報分野 の塚越崇准教授らの国際共同研究チームによるもの。詳細は、日本天文学会が刊行する学術誌「Publications of the Astronomical Society of Japan」に掲載された。
原始惑星系円盤とは、若い星の周囲に広がる低温の分子ガスと固体微粒子(塵)で構成される円盤のことだ。この円盤内に惑星が存在する場合、その重力で物質が集積したり押し出され、円環状や螺旋状などの特徴的な構造が形成される。このような特徴的な構造の観測には、アルマ望遠鏡による高解像度の電波観測が不可欠だ。
これまでのアルマ望遠鏡を用いた大規模な原始惑星系円盤観測プロジェクト「DSHARP」と「eDisk」は、高解像度観測により円盤に含まれる塵の分布の詳細を明らかにした。DSHARPでは、星形成開始から100万年以上経過した20個の若い星を取り巻く原始惑星系円盤に、特徴的な構造が普遍的に存在することが確認された。
一方、eDiskが調べた星形成開始から1〜10万年程度の降着段階、つまり星と円盤への質量降着が活発な段階にある19個の若い星を取り巻く円盤では、明確な構造はほぼ観測されなかった。これは、星の年齢によって原始惑星系円盤の特徴が異なることが示唆されている。
-

今回の研究で得られた天体とeDiskで観測された天体の、ボロメトリック温度とダスト円盤半径の散布図。紫色、赤色、黄色のマーカーは特徴的な構造を持つ円盤、またはその候補天体を示す。ボロメトリック温度650Kは中心星が誕生してから100万年程度経過した円盤を表し、それよりも早い段階から特徴的な構造が現れたことが示唆されている
(C)A. Shoshi et al.
(出所:アルマ望遠鏡日本語Webサイト)
星の年齢(進化度合い)には、その周囲の全波長における天体が放つ光の明るさから求められる見かけの温度「ポロメトリック温度」が用いられる。温度が高いほど進化が進んでおり、例えば絶対温度650K(約377度)では、中心星は形成から約100万年が経過した状態と考えられている。
原始惑星系円盤において、惑星の誕生を示唆する構造がいつ現れるのかを特定するには、これまで未調査だった10〜100万年の中間年齢にある幅広い原始惑星系円盤の観測が必要だった。しかし、高解像度観測が可能な天体は距離や観測時間に制限があり、十分な統計的調査が困難だ。
そこで研究チームは今回、超解像度画像復元法のスパースモデリングに注目。同じ観測データから、従来よりも高解像度の復元を試みることにした。
電波干渉計の画像作成では、データ欠損を補うため、ある仮定に基づき画像復元を行う。今回の手法では、従来法より適切にそれを行うことで、同じデータからでも高解像度の画像作成を可能とした。画像作成には、日本の研究チームが開発した公開ソフトウェア「PRIISM」が使用された。既存のアルマ望遠鏡の公開データのうち、太陽系近傍(約460光年)にあるへびつかい座の星形成領域に分布する78個の原始惑星系円盤に対し、この新たな画像復元法が適用された。
解析の結果、半数以上の円盤で従来比3倍以上の高解像度化に成功。これは、DSHARPやeDiskで得られた画像と同等の高解像度だ。また、画像作成された天体の総数は、両プロジェクトのおよそ4倍に達し、サンプル数を大幅に増加させた。今回得られた78個の円盤画像中、27個の円盤で円環状や螺旋状の構造が発見され、そのうち15個は今回の研究で初めて特徴的な構造の存在が判明したものである。
研究チームは、今回得られたデータとeDiskのデータを組み合わせ、統計解析を実施。その結果、星が誕生してから数十万年の時期、半径30天文単位以上の円盤で特徴的な構造が出現し始めることが確認された。つまり惑星は、中心星周囲に分子ガスや塵が豊富に残る、従来の常識よりも非常に若い段階ですでに形成されていたのである。これは、若い星と共に成長することを意味する。
今回の研究成果は、新たな画像復元法により高解像度と多数のサンプルの両立を可能にし、これまでのeDiskとDSHARPの間を埋めるものとなった。今回はへびつかい座の円盤のみが対象とされたが、今後、他の星形成領域と比較することで、この傾向が普遍的なものかどうかが解明される可能性があるとしている。