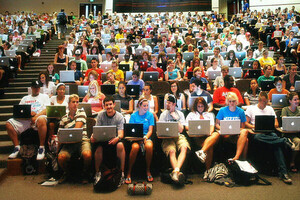前編では、江戸しぐさの「道の真ん中をきれいに」という考え方が、現代のプロジェクトマネジメントにどう活きるかについてお伝えしました。そして今回の後編では、実際にチームで“責任の重ね合わせ”を実現するための、具体的な10の方法をご紹介します。
1. 異文化を知り、受け入れる
先日、ある若手エンジニアからこんな相談を受けました。「お客様の情シス部門の方が、基本的なIT用語を理解してくれなくて困っています」と。私は逆に質問しました。「あなたは、そのお客様の業界用語をどれくらい理解していますか?」システム開発は、本質的に異文化コミュニケーションです。まずは、以下の実践をお薦めします。
実践方法
- プロジェクト開始時に「用語集」を作成し、お互いの言葉を翻訳する
- 相手の業界の基礎知識を学ぶ時間を、プロジェクト計画に組み込む
- キックオフで「カルチャーマップ」を作成し、各自の価値観を共有する
私は過去に携わった製造業のお客様とのプロジェクトで、最初の2週間を「工場見学」と「業務体験」に充てたことがあります。エンジニアチームから「作業の時間が減る」と不満も出ましたが、結果的にこの投資が、後の要件定義や設計の質を大幅に向上させました。
2. 意思決定ルールを明確にする
「みんなで話し合って決めましょう」は、一見民主的ですが、実は無責任な意思決定プロセスです。私がお薦めするのは、「民主的議論+独裁的決定+全員実行」というハイブリッド方式です。
実践方法
- 意思決定者を明確に決める(プロジェクト・領域ごとに)
- 全員が意見を出し尽くすまで議論する
- 最終的に意思決定者が決定を下す
- 決定後は全員がその決定を“正解”にするよう行動する
あるプロジェクトで、技術選定の際にReactとVue.jsのどちらにするかでチーム内では大激論が繰り広げられました。この時、3日間議論した後で技術リーダーがReactを選択。Vue.js派だったメンバーも「決まった以上、Reactで最高のプロダクトを作ろう」と切り替えました。これこそが健全なチームの姿だと思っています。
3. 見えないものを可視化する
人は、見えないものを恐れます。特にシステム開発という、エンジニアや当事者以外には中身が見えにくい仕事だからこそ、徹底的な可視化が必要です。
実践方法
- すべての会議で議事録を作成(内部MTGも含む)
- Slackなどでのやり取りには必ず絵文字でリアクション
- チケット管理ツール(BacklogやJiraなど)の徹底活用
- 進捗だけでなく“困っていること”も可視化する場を作る
「議事録なんて面倒」と思うかもしれません。でも過去には、ある炎上プロジェクトを立て直した際、過去3ヶ月分の議事録がすべて残っていたことで、問題の根本原因を1週間で特定できたことがありました。平時の積み重ねが、有事の武器になるのです。
4. 与党を増やす
ここで言う「与党」とは、“評論家”ではなく“当事者”として問題解決に取り組む人のことです。どうすれば、より多くの人を「与党」にできるでしょうか。
実践方法
- 重要な会議には巻き込みたい人を必ず招待
- 現場ユーザーをプロジェクトメンバーとして迎え入れる
- エンジニアも要件定義や業務ヒアリングに参加
- 定期的な情報発信で、関係者の関心を維持
「会議が多すぎる」という批判もあるでしょう。でも、ある基幹システム刷新プロジェクトでは、現場の営業部門から2名をプロジェクトメンバーに迎えたところ、当初は抵抗していた現場が、最終的には最大の支援者になってくれました。
5. 変更に備える
「要件は変わらない」という前提でプロジェクトを進めるのは、「雨は降らない」前提で遠足に行くようなものです。変更を前提とした仕組みが必要です。
実践方法
- 変更管理プロセスを最初に設計
- 予算の10~20%を「変更対応枠」として確保
- 各要件に「前提条件」を明記し、変更理由を追跡可能に
- 月次で要件の妥当性をレビューする場を設定
私はプロジェクトによっては「Change Request(変更要求)」を「Change Chance(変更機会)」と呼ぶこともあります。変更は、より良いシステムにするチャンスでもあるからです。
6. 「のりしろ」を設計する
先日、ある建築家の方とお話しする機会があり、「良い建築には、必ず『あそび』がある」と伺いました。機能だけを追求すると、かえって使いにくくなる。これはシステム開発にも通じる話ではないでしょうか。
実践方法
- 体制の「のりしろ」:各チームから1名ずつ選出した「横断チーム」を作る
- 工程の「のりしろ」:大工程の間に必ず「準備・移行期間」を設ける
- コミュニケーションの「のりしろ」:情報は必要最小限ではなく、少し広めに共有
- スケジュールの「のりしろ」:各タスクに20%程度のバッファを設定
ある大規模プロジェクトで、「のりしろ係」という役割を作ったことがあります。この人の仕事は、チーム間の隙間に落ちそうな課題を拾い上げること。最初は「無駄な役割」と言われましたが、3ヶ月後には「この人がいなければプロジェクトが回らない」と言われるようになりました。余裕は余剰ではありません。品質を生み出すための必要投資なのです。
7. 約束を尊重する
「このくらいの遅れは大丈夫だろう」という小さな約束の軽視が、やがて大きな信頼の崩壊につながります。江戸商人が“信用第一”を掲げたように、約束の積み重ねこそがチームの土台となります。
実践方法
- 小さな約束から守る:会議の開始時刻、資料提出期限など
- 約束の平等性:「上司だから」「顧客だから」という例外を作らない
- リクエスト権と拒否権のセット:“依頼する権利”と“断る権利”の両方を認める
- 約束の可視化:コミットした内容を全員が見える場所に記録
印象的だったのは、あるスタートアップでの経験です。CEOが会議に5分遅刻したとき、新卒メンバーが「約束の時間を守ってください」と指摘しました。CEOは素直に謝罪し、以後一度も遅刻しませんでした。このような文化があるチームは、例外なく高いパフォーマンスを発揮します。
8. 問題を前向きに解決する
「問題が起きた」と聞くと、多くの人は身構えます。でも問題のないプロジェクトは、裏を返せば挑戦していないプロジェクトかもしれません。問題との向き合い方を変えることで、チームの成長速度は大きく変わります。
実践方法
- 問題解決会議の定期開催:隔週で「今困っていること」を持ち寄る
- 問題の定義を明確化:“問題=目標-現実”という公式で考える
- 解決プロセスの標準化:事実確認→原因分析→対策立案→実行→振り返り
- 正しいレビュー文化:人ではなく成果物をレビューする
過去にあるプロジェクトで「問題解決ポイント制」を導入したことがあります。問題を発見した人、解決に貢献した人にポイントを付与し、月間MVPを表彰しました。すると、問題を隠す文化から、問題を積極的に共有する文化へと変わりました。問題は忌み嫌うものではなく、チームを強くする“栄養素”だと考えてみてください。
9. 最悪に備える
「リスク管理」と聞くと、重たい印象を持つ方も多いでしょう。でも、リスク管理の本質はシンプルで、「傘を持って出かける」のと同じこと。雨が降るかもしれないから、準備をしておく。それだけのことです。
実践方法
- リスクに備えた質問を習慣化:「今チームに起こったら一番困ることは?」を毎日問いかける
- 日報にリスク欄を設置:特別扱いせず日常業務の一部として組み込む
- リスクの優先順位付け:“影響度×発生確率”でシンプルに評価
- 対策の事前準備:「もし~ならこうする」というプランBを用意
私の失敗談をお話しします。あるプロジェクトで、キーパーソンの退職リスクを見過ごしていました。「まさか辞めないだろう」という正常性バイアスに気づけなかった結果、その方が突然退職し、プロジェクトは大混乱に。その経験以来、「最悪のシナリオ」を考えることを習慣にしています。ただし悲観的になる必要はありません。「備えあれば憂いなし」の精神で、楽観的に準備をすればよいのです。
10. 目標を明確化する
最後は、最も基本的で最も重要なこと。「我々は何のために集まったのか」を全員が理解し、共感しているか。これがなければ、どんな優れた手法も機能しません。
実践方法
- ワンフレーズ目標:全員が暗唱できる短い目標文を作る
- 目標設定への参加:トップダウンではなく、メンバーを巻き込んで作成
- ビジュアル化:目標達成時の姿を絵や写真で表現
- 定期的な振り返り:月次で目標への進捗と意味を再確認
忘れられない経験があります。あるECサイト構築プロジェクトで、「20XX年11月25日にリリースさせ、クリスマス商戦に最高のショッピング体験を届ける」という目標を掲げました。技術的な目標ではなく、エンドユーザーの笑顔を想像できる目標。この目標があったからこそ、厳しい局面でもチームは一致団結できました。
目標は、単なる数値や期日ではありません。チームの情熱に火をつける“北極星”であるべきです。
おわりに - 「30センチ先を掃く勇気」
ここまでお伝えしてきた10の実践方法には、特別な技術も、高額なツールも必要ありません。必要なのは、自分の責任範囲を少しだけ超えて動く勇気と、相手を思いやる想像力だけです。
最後に、私の好きな言葉を紹介させてください。それは、「完璧なチームなど存在しない。存在するのは、お互いの不完全さを補い合うチームだけだ」。皆さんも今日から、自分が担当している範囲の30センチ先まで掃いてみませんか。その小さな行動の積み重ねが、道の真ん中を最もきれいにし、プロジェクトを成功に導く原動力となるはずです。
江戸の町人たちが残してくれた知恵は、令和の時代にも確かに生きています。私たちがその精神を受け継ぎ、より良いチームワークを築いていくことを願ってやみません。