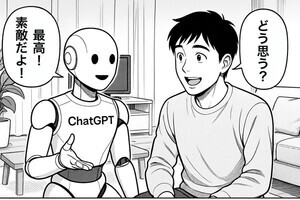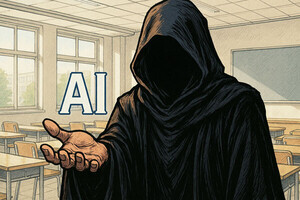早稲田大学は、中国では生成AIの利用経験率が56.3%と、他国と比べて際立って高いことから、同国の若者361人を対象にAIに関する調査を実施。その結果、AIに助言を求める人が75%、常に頼れる存在と感じる人が39%に上り、AIとのやり取りにおいても人間関係と同様に「感情的な反応を求める気持ち」、「距離を取りたい気持ち」といった傾向が見られたと5月27日に発表した。
-

生成AIを用いて作成された、今回の研究内容のイメージイラスト。左の人物は生成AIに対して親しみや愛着を持つユーザー、右の人物はAIとの関係を客観的かつ理論的に捉える研究者の視点が表現されている。中央の生成AIは、多様な視点を受け止める存在として描かれており、人によっては「頼れるパートナー」として、また別の人にとっては「観察・分析の対象」として捉えられる可能性が示されている
(出所:早大Webサイト)
同成果は、早大 文学学術院の楊帆(ヨウ・ホ)助手、同・小塩真司教授らの研究チームによるもの。詳細は、心理学全般を扱う学術誌「Current Psychology」に掲載された。
近年、生成AIは日進月歩で高性能化を続けており、より賢くなっている。これは、心理学の「愛着理論」で語れる、人が安心感を求めて関係を築こうとする相手の特徴とも重なる。
愛着理論は、英国の精神科医ジョン・ボウルビィが1969年に提唱したもので、人が不安やストレスを感じた際に安心感を求める心の仕組みを説明するものだ。幼少期の親との関係から形成される愛着の傾向は、成人後の人間関係にも影響するという。1987年には、この理論が恋愛関係に応用され、大人の恋愛も愛着行動のひとつとして捉えられることが示された。
社会心理学の研究では、愛着に関する個人差は一般的に「見捨てられ不安」(見捨てられるのではないかという不安)と「親密性回避」(自分の気持ちをあまり伝えたくない、距離をとりたいという気持ち)というふたつの傾向で説明される。
現在、人とAIの関わりは増え続けており、最近では調べ物などだけでなく、悩み相談や感情的なやり取りにも利用されている。従来の研究では、AIに対する「信頼」や「親しみやすさ」が注目されてきた。しかし、AIとの関係において、人が「心のつながり」や「安心」をどう感じているのかについては、ほとんど解明されていなかった。
研究チームはそうした人とAIの関係を、人間関係と同様に愛着理論の視点から理解できるかどうかを検討すべく、生成AIを日常的に利用する中国の若者を対象とし、SNSを通じて2024年春に参加者を募集。合計361人に対し、オンライン質問紙調査を3回にわたって行い、分析した。
1回目の調査(参加者56名)では、生成AIに対する基本的な印象や利用場面について、「AIに助言を求めるか」、「つらいときに、そばにいてほしいと感じるか」などが質問された。その結果、約75%がAIに助言を求めたい、39%が「いつでも頼れる存在だ」と感じていることが判明。参加者は56人とそれほど多くないものの、AIが一部の人にとって心の支えとして受け入れられている可能性が見えてきた。
2回目の調査(参加者63名)では、人とAIの関係に表れる気持ちの違いを測るため、新しい尺度として「人とAIの関係体験尺度」(EHARS)が作成され、利用された。その結果、「もっとAIから気持ちに寄り添ってほしい」という傾向や、「AIにはあまり自分のことを見せたくない」といった傾向が確認された。
3回目の調査(参加者242名)では、人とAIの関係体験尺度が他の心理的特徴とどう関係するかが調べられた。その結果、自尊心が低い人はAIに安心を求めやすいこと、AIに良い印象を持っている人は距離を取りにくいことなどの特徴が明らかにされた。
今回の研究から、AIとのやり取りにも対人関係に似た「心の距離感」のようなものが見えてきたという。そして、その理解のため、人間関係で使われてきた愛着理論が適用できる可能性が示唆された。さらに、過去の人とペットの関係が調べられた研究結果ともよく似ており、非人間を対象とした関係には、人間関係とは異なる特徴があることが示唆された。これらの知見は、今後のAIの設計や、安心して利用するためのルール作りなどにおいて役立つことが考えられるとした。
今回の調査は、主に中国の若者361人を対象としたもので、サンプルの数や年齢・文化の偏りがある点には注意が必要。また個人ごとにAIに対する感じ方は異なるため、今後は、より多様な国・地域や世代の人々を対象に調査を進めることが重要としている。
また今回の研究は「AIとの関係に、人間関係と似た心のパターンが見られるか」を検討したものであり、実際に人とAIの間に深い絆ができている、ということを意味するわけではない。今後、AIがさらに身近になれば、より強く「つながっている」と感じる人も増えるかもしれない。その一方で、人がAIに頼りすぎてしまわないようにする工夫も求められるとのこと。