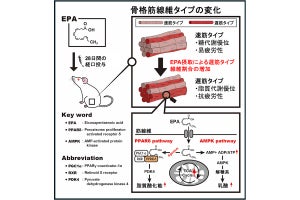麻布大学は4月15日、社会的疎外感を抱えつつもウェルビーイングが高い人は、イヌやネコなどの伴侶動物(ペット)に対する親密な愛着が強く、心のうちを打ち明けるような関係性を築いていることを明らかにしたと発表した。
-

社会的疎外感を抱えつつもウェルビーイングが高い人は、イヌやネコに心のうちを打ち明けていることが明らかに。created by Canva AI, Text to Image(出所:麻布大学Webサイト)
同成果は、麻布大 獣医学部 介在動物学研究室の子安ひかり特任助教、同・永澤美保教授、同・菊水健史教授、京都大学 医学研究科の村井俊哉教授、東京都医学総合研究所の西田淳志センター長らの共同研究チームによるもの。詳細は、心理学を扱う学術誌「Frontiers in Psychology」に掲載された。
思春期の精神的健康は、成人後の人生にまで大きな影響を及ぼす可能性があり、特に社会や文化との価値観の不一致を経験した若者は生きづらさを感じる傾向にある。そのため、思春期の精神的健康のサポートが重要視されている。
精神的健康をサポートする方法の1つとして、ペットとの関わりが広く認識されつつある。ヒトとペットの関係性は多様であり、ペットの飼い主なら多くのヒトが体験していることだが、時にヒトはペットに無条件に受け入れられている感覚を覚えることもある。このような関係性は、個人が社会との価値観の不一致を認識した際にも、精神的健康への影響を軽減できる可能性が示唆されている。そこで研究チームは今回、思春期におけるイヌやネコなどのペットとの関わり方が、社会との価値観の不一致とウェルビーイングの関係に与える影響について解明を試みたという。
なお本来ウェルビーイングとは、単に肉体的または精神的な“健康”を意味するのではなく、心身に加えて社会的な側面も満たされた状態を意味する。したがって、「友達がいない」「趣味が合う人がいない」など、社会との価値観が一致しない状態は、本来はその時点でウェルビーイングとはいえない。しかし今回の研究では、ウェルビーイングをそれらとは切り離し、「精神的に満たされた状態」として扱っている。
今回の研究では、社会との価値観の不一致を測る指標として「文化的離反尺度」が用いられた。文化的離反とは、個人が自身の周囲の文化における主流な価値観から隔たりを感じたり、拒絶されていると感じたりする感覚を指す。文化的離反尺度の例としては、周囲の人との共通の話題が多い場合は文化的離反は低く、「私の世界観は、他のほとんどの人たちのそれと同じように思う」となる一方、周囲とは話が合わず孤独を感じてる場合は文化的離反が高く、「私はよく、自分が周りに何となくなじんでいないように感じる」といった具合になる。そして今回の研究では、この文化的離反が高い、つまりマイノリティ感が高い人の中で、ウェルビーイングが高い人と低い人におけるイヌやネコとの関わり方の差異に焦点が当てられた。
高校生と大学生を対象に、イヌやネコとの関わり方、文化的離反尺度、ウェルビーイングに関するアンケート調査が実施され、得られたデータが解析された。文化的離反とウェルビーイングの平均値に基づき、参加者は4つのグループに分類された。その中で、文化的離反が高い群において、ウェルビーイングが高い群と低い群を比較し、動物観やイヌやネコへの愛着の差異が調査された。なお、ウェルビーイングは、世界保健機関(WHO)が精神的健康の測定指標として推奨する「WHO-5精神的健康状態表」を用いて測定された。
文化的離反が高い群において、ウェルビーイングが高い群は低い群と比較して、環境や野生動物に対して人間中心的な考えを持ち、生態や環境への関心が高く、イヌやネコに対して親密な愛着を示すことが明らかにされた。また、大事なことを話したり、心のうちを打ち明けたりするような、自己開示の対象としてペットが機能することで、思春期の精神的健康をサポートしている可能性が示唆された。
「人間中心的な考え方」と「イヌやネコに対する親密な愛着」は、一見矛盾するように思われる。しかし、イヌやネコを相談相手とする関わり方は、イヌやネコを自分の投影あるいは延長として捉え、自分の価値観に基づいて関係を構築しており、人間中心的と解釈することも可能であるという。内なる親密な対象のイヌやネコと、外なる環境や野生動物への態度を区別し、多角的に動物から恩恵を受けている可能性が示唆される。研究チームは今後、イヌやネコに心のうちを打ち明けることによる個人の心理的・生理的変化を調査する実証的な研究や、より詳細な動物観の分析を進めることで、イヌやネコが人の精神的健康にもたらすサポートのメカニズムの解明が期待されるとしている。